労務法規集 更新情報(2026年2月度)
対象期間:2026年1月6日から同年2月3日まで
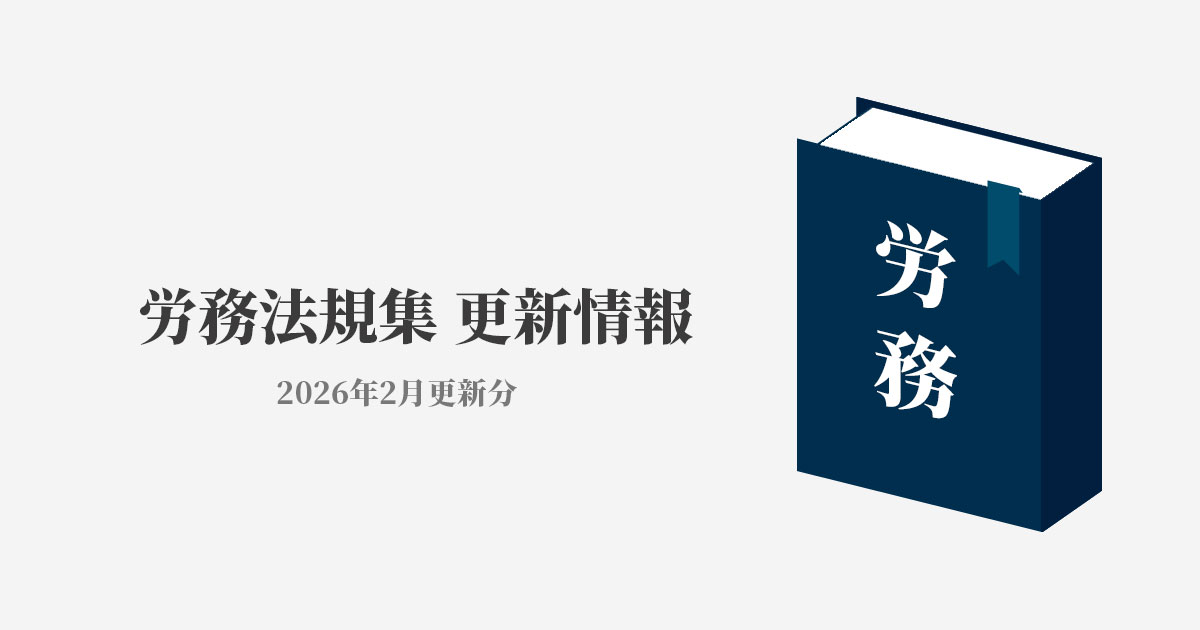
今回更新された法令等は以下のとおりです。
以下の法令は更新されていましたが、附則・様式等の変更のみで内容に変更はありませんでした。
-
石綿による健康被害の救済に関する法律
-
健康保険法
-
国民健康保険法
-
介護保険法
-
高齢者の医療の確保に関する法律
-
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
施行令
子ども・子育て支援法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十四条の二(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合) | |
|
第二十四条の二 法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の二百八・六とする。
|
第二十四条の二 法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の二百とする。
|
施行規則
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第九条(認定の申請) | |
|
6 第二項の申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項、第十四条第四項及び第十七条第四項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
|
6 第二項の申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項及び第十四条第四項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
|
| 第十七条(立替払賃金の請求) | |
|
2 前項の請求書には、同項第四号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五条の通知書又は同項第五号に掲げる事項を証明する同条の通知書を添付しなければならない。ただし、独立行政法人労働者健康安全機構が立替払賃金の支給に関する処分を行う上で必要がないと認める場合には、この限りでない。
|
2 前項の請求書には、同項第四号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五条の通知書又は同項第五号に掲げる事項を証明する同条の通知書を添付しなければならない。
|
|
3 第一項に規定する者が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の請求書を提出する場合には、当該請求書における請求者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該請求者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。
|
3 第一項の請求書の提出は、第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、同条第二号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。
|
|
4 第一項の請求書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該請求書の提出に関する手続を請求者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
|
(新設)
|
|
5 第一項の請求書の提出は、第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、同条第二号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。
|
(新設)
|
障害者雇用促進法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三十六条の十五(準用) | |
|
第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条」と、同令第九条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
|
第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室
|
雇用保険法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第百二条の三(雇用調整助成金) | |
|
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
|
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
|
国民健康保険法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第七条の三(資格情報通知書による通知) | |
|
3 前二項の規定は、第一項各号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。
|
3 前二項の規定は、第一項各号
|
| 第十六条(事業勘定及び直営診療施設勘定) | |
|
第十六条 令第一条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
|
第十六条 令第二条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
|
|
2 令第一条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
|
2 令第二条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
|
アプリの改修
特にありません。

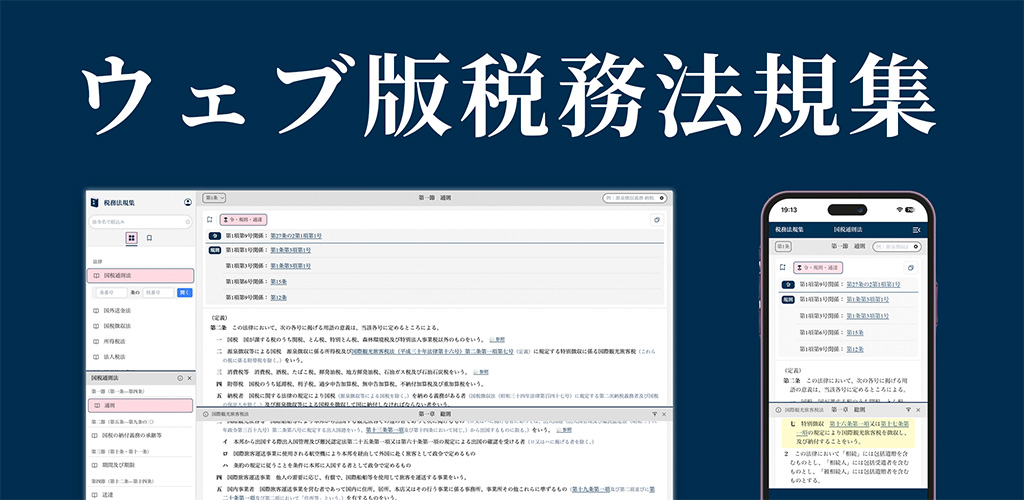



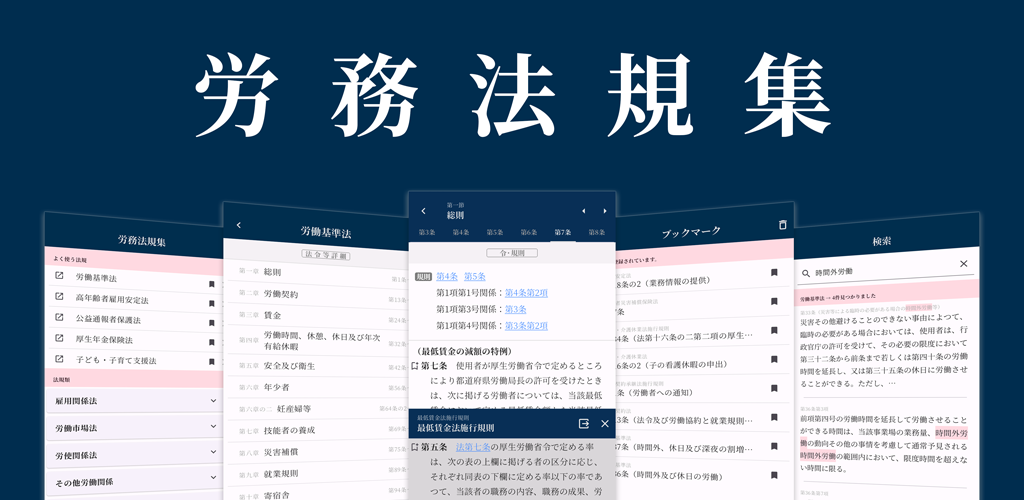

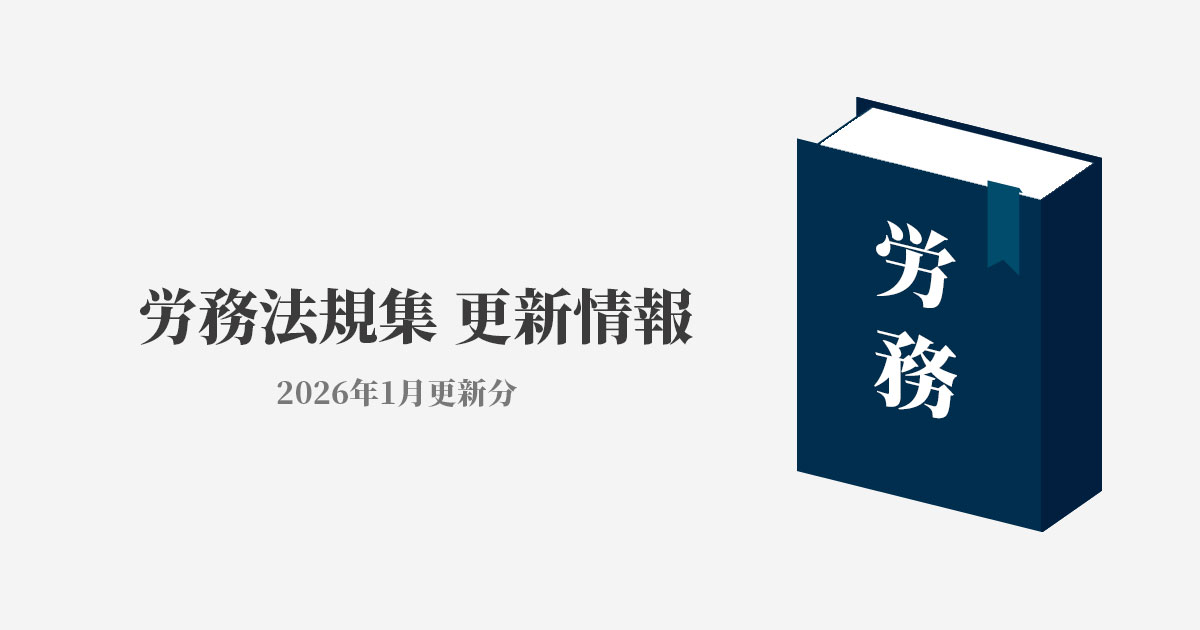
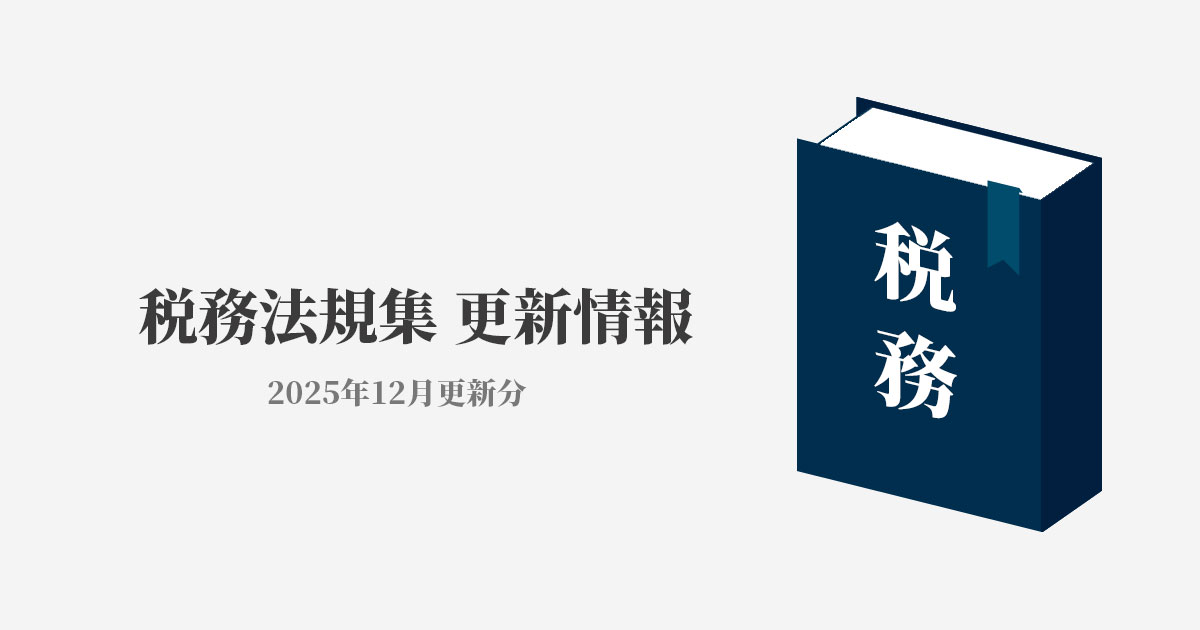
この記事をシェアする
Twitter
Google+
Facebook
はてなブックマーク
Reddit
LinkedIn
StumbleUpon
Email