労務法規集 更新情報(2025年10月度)
対象期間:2025年9月3日から2025年10月2日まで
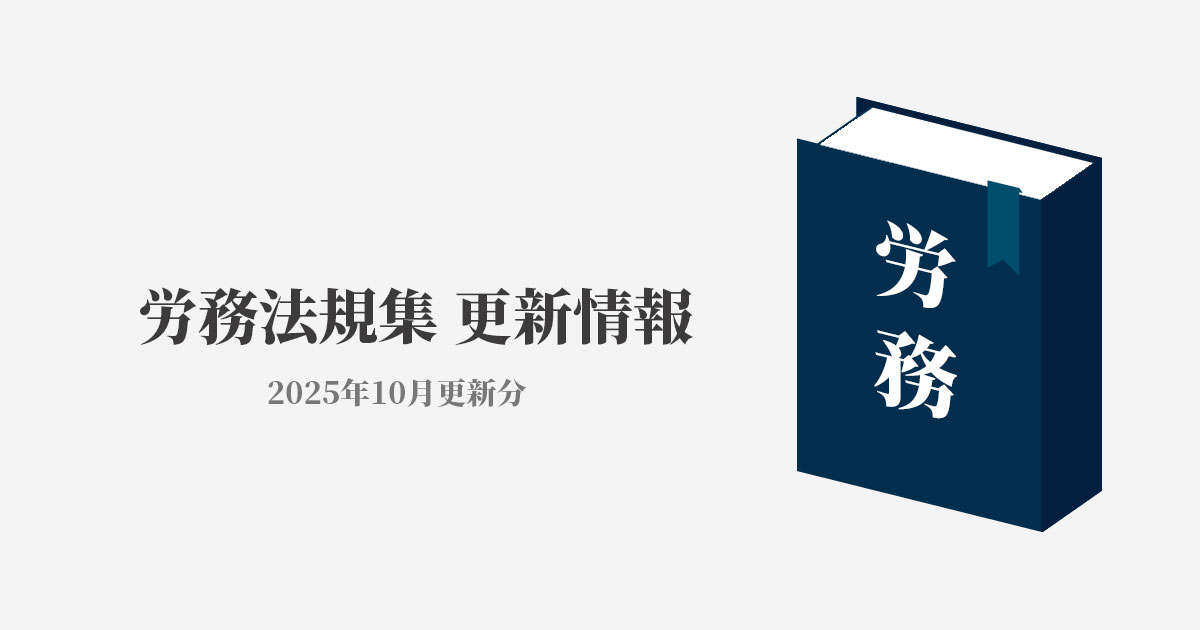
目次
今回更新された法令等は以下のとおりです。
以下の法令は更新されていましたが、附則ないし様式等の変更のみで内容に変更はありませんでした。
- 労働者協同組合法
- 労働審判法
- ADR法
- 国民健康保険法
- 子ども・子育て支援法
法律
育児・介護休業法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条(目的) | |
|
第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
|
第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
|
| 第二条(定義) | |
|
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七、第六十一条第二十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十五項並びに第六十一条の二第二十三項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
|
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七並びに第六十一条第三十三
|
|
一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
|
一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって
|
| 第十六条の二(子の看護等休暇の申出) | 第十六条の二(子の看護休暇の申出) |
|
第十六条の二 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を取得することができる。
|
第十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
|
|
2 子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
|
2 子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
|
|
3 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
|
3 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
|
| 第十六条の三(子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等) | 第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等) |
|
第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
|
第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
|
|
2 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。
|
2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、
|
| 第十六条の四(準用) | |
|
第十六条の四 第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。
|
第十六条の四 第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護休暇について準用する。
|
| 第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等) | |
|
2 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。
|
2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、
|
| 第十六条の八 | |
|
第十六条の八 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
|
第十六条の八 事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
|
|
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
|
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。
|
| 第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等) | 第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) |
|
第二十一条 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
|
第二十一条 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
|
|
2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない。
|
2 事業主は、労働者が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者
|
|
3 事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
|
(新設)
|
|
4 事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
|
(新設)
|
|
5 事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
|
(新設)
|
|
6 事業主は、労働者が第一項若しくは第四項の規定による申出をしたこと又は第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
|
(新設)
|
| 第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置) | |
|
第二十一条の二 前条第一項、第四項及び第五項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。
|
第二十一条の二 前条第一項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。
|
| 第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置) | |
|
2 事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
|
2
|
|
一 その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施
|
(新設)
|
|
二 介護休業に関する相談体制の整備
|
(新設)
|
|
三 その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置
|
(新設)
|
|
3 前二項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
|
(新設)
|
|
4 事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
|
(新設)
|
|
一 その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
|
(新設)
|
|
二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
|
(新設)
|
|
三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置
|
(新設)
|
| 第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表) | |
|
第二十二条の二 常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
|
第二十二条の二 常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
|
| 第二十三条(所定労働時間の短縮措置等) | |
|
第二十三条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十三条の三第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
|
第二十三条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
|
|
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
|
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)を講じなければならない。
|
|
一 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)
|
(新設)
|
|
二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号において「始業時刻変更等の措置」という。)
|
(新設)
|
|
3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第三項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
|
3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第二項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
|
| 第二十三条の三(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) | |
|
第二十三条の三 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。
|
(新設)
|
|
一 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
|
(新設)
|
|
二 在宅勤務等の措置
|
(新設)
|
|
三 育児のための所定労働時間の短縮措置
|
(新設)
|
|
四 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
|
(新設)
|
|
五 前各号に掲げるもののほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
|
(新設)
|
|
2 前項の規定により事業主が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
|
(新設)
|
|
3 第一項の規定(第三号に掲げる労働者にあっては、同項第四号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち第一項の規定による措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これを適用しない。
|
(新設)
|
|
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
|
(新設)
|
|
二 前号に掲げるもののほか、第一項に掲げる措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
|
(新設)
|
|
三 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で第一項第四号に規定する休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(前項の規定により同項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)
|
(新設)
|
|
4 事業主は、第一項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
|
(新設)
|
|
5 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第一項の規定により当該事業主が講じた措置(以下この項及び第七項において「対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
|
(新設)
|
|
6 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定による申出」とあるのは「第二十三条の三第五項に規定する対象措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当該対象措置の対象となる」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
|
7 事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、若しくは第一項の規定により当該労働者に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
|
(新設)
|
| 第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) | |
|
第二十四条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない。
|
第二十四条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
|
|
三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度
|
三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度
|
|
2 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
|
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、
|
|
3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
|
(新設)
|
|
4 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
|
(新設)
|
| 第二十九条(職業家庭両立推進者) | |
|
第二十九条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項及び第五項、第二十一条の二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条並びに第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
|
第二十九条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、第二十一条の二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条及び第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
|
| 第五十二条の二(苦情の自主的解決) | |
|
第五十二条の二 事業主は、第二章から第八章まで、第二十一条、第二十三条から第二十三条の三まで及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
|
第五十二条の二 事業主は、第二章から第八章まで、第二十一条、第二十三条、第二十三条の二及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
|
| 第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例) | |
|
二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第三項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
|
二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第二項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
|
| 第五十六条の二(公表) | |
|
第五十六条の二 厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項から第六項まで、第二十二条第一項、第二項若しくは第四項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項、第四項、第五項若しくは第七項、第二十五条第一項若しくは第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
|
第五十六条の二 厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項若しくは第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
|
| 第五十七条(労働政策審議会への諮問) | |
|
第五十七条 厚生労働大臣は、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。)及び第三項(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第五項並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
|
第五十七条 厚生労働大臣は、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項
|
| 第六十条(船員に関する特例) | |
|
2 船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第三号、第五項並びに第六項、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の五第六項第四号、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の六第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二十三条第二項第一号中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「在宅勤務等」」とあるのは「陸上勤務」」と、同号、第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸上勤務の措置」と、第二十三条第二項第二号中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同号、第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、第二十三条の三第一項第四号及び第二十四条第一項中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同条第四項中「在宅勤務等」とあるのは「陸上勤務」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
|
2 船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の五第六項第四号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の六第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第二十三条第二項中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同項第三号中「制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
|
| 第六十一条(公務員に関する特例) | |
|
第六十一条 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、国家公務員に関しては、適用しない。
|
第六十一条 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、国家公務員
|
|
2 国家公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
|
2 国家
|
|
3 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員(以下この条において「特定非常勤職員」という。)にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。第五項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の対象家族であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条及び次条において「要介護家族」という。)の介護をするための休業(以下この条において「行政執行法人介護休業」という。)をすることができる。
|
3 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母若しくは子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定める
|
|
4 行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
|
4 前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
|
|
5 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、特定非常勤職員のうち、行政執行法人介護休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
|
5 行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常
|
|
6 行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第八項及び第九項において同じ。)であって小学校第三学年修了前の子(第十六条の二第一項に規定する小学校第三学年修了前の子をいう。次項並びに次条第六項及び第七項において同じ。)を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下この条において「行政執行法人子の看護等休暇」という。)を取得することができる。
|
6 前三項の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項及び第五項において同じ。)」と、第四項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。
|
|
7 行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(前項に規定する職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
|
7 行政執行法人
|
|
8 行政執行法人子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
|
8 前項の規定により休暇を取得することができる
|
|
9 行政執行法人の長は、行政執行法人子の看護等休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
|
9
|
|
10 行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うための休暇(以下この条において「行政執行法人介護休暇」という。)を取得することができる。
|
10 行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認め
|
|
11 行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
|
11
|
|
12 行政執行法人介護休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
|
12 行政執行法人
|
|
13 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
|
13 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
|
|
14 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
|
14
|
|
15 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
|
15 行政執行法人の長は、第十二項の規定による
|
|
16 行政執行法人の長は、職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。次条第十六項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
|
16 第十二項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間
|
|
17 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項の」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
|
17 行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条
|
|
18 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。次条第十八項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
|
18
|
|
19 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
|
19 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
|
|
20 行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、第五項の規定による承認の請求(以下この条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び介護両立支援制度等の利用に係る承認の請求(第二十七項において「介護両立支援制度等の承認の請求」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
|
20 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において
|
|
21 行政執行法人の長は、職員が第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、当該期間内に、行政執行法人介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせなければならない。
|
21 行政執行法人の長は、
|
|
22 行政執行法人の長は、職員が第二十項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
|
22
|
|
23 第二十項及び第二十一項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを職員に周知させるための措置(職員が対象家族を介護していることを知ったときに、当該職員に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。
|
23 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するため
|
|
一 職員の行政執行法人介護休業中における待遇に関する事項
|
(新設)
|
|
二 行政執行法人介護休業後における賃金、配置その他の勤務条件に関する事項
|
(新設)
|
|
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
|
(新設)
|
|
24 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人介護休業の承認の請求をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該職員に係る取扱いを明示するように努めなければならない。
|
24 前項の規定は、
|
|
25 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
|
25 行政執行法人の長は、
|
|
一 職員に対する行政執行法人介護休業に係る研修の実施
|
(新設)
|
|
二 行政執行法人介護休業に関する相談体制の整備
|
(新設)
|
|
三 その他厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置
|
(新設)
|
|
26 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求及び行政執行法人介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、行政執行法人介護休業をする職員が勤務する事業所における職員の配置その他の雇用管理、行政執行法人介護休業をしている職員の能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
|
26 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは
|
|
27 行政執行法人の長は、介護両立支援制度等の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
|
27 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達する
|
|
一 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
|
(新設)
|
|
二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
|
(新設)
|
|
三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
|
(新設)
|
|
28 行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員であって国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づき所定労働時間を短縮することにより当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(次項及び第三十四項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれかに該当する特定非常勤職員については、この限りでない。
|
28 前項の規定は、
|
|
29 行政執行法人の長は、職員のうち、前項ただし書の規定により第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書第三号に該当する特定非常勤職員であってその三歳に満たない子を養育するもの(以下この条において「特定職員」という。)について育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該特定職員に関して、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
|
29 行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しない
|
|
一 職員の承認の請求に基づき、当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第四十四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第三十四項第二号及び第四十二項において「在宅勤務等の措置」という。)
|
(新設)
|
|
二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により勤務させることその他の職員の承認の請求に基づく厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第三十四項第一号及び第四十一項において「始業時刻変更等の措置」という。)
|
(新設)
|
|
30 行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第三十二項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないこと(以下この条において「介護時間休業」という。)ができる。
|
30 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の
|
|
31 介護時間休業ができる時間は、要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
|
31 行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったとき
|
|
32 行政執行法人の長は、第三十項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
|
32
|
|
33 行政執行法人の長は、職員が第二十八項、第二十九項各号若しくは前項の規定による承認の請求をし、第二十八項若しくは第二十九項の規定により当該職員に措置が講じられ、又は職員が介護時間休業をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
|
33 行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、第三項の規定
|
|
34 行政執行法人の長は、職員(特定非常勤職員にあっては、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたならば同項第一号及び第二号のいずれにも該当しないものに限る。)のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。
|
34
|
|
一 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
|
(新設)
|
|
二 在宅勤務等の措置
|
(新設)
|
|
三 育児のための所定労働時間の短縮措置
|
(新設)
|
|
四 職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
|
(新設)
|
|
五 前各号に掲げるもののほか、職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
|
(新設)
|
|
35 前項の規定により行政執行法人の長が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
|
35 第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「当該行政執行法人の職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第三十三項」と読み替えるものとする。
|
|
36 第三十四項の規定(同項第四号に係る部分に限る。)は、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたならば同項第三号に該当する特定非常勤職員については、これを適用しない。
|
36
|
|
37 行政執行法人の長は、第三十四項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該行政執行法人の事業所に職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
|
37 第二十五条第二項の規定
|
|
38 行政執行法人の長は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員に対して、当該職員が第三十四項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置(以下この項及び第四十項において「行政執行法人対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、行政執行法人対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、行政執行法人対象措置に係る承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
|
38 第二十五条の二の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。この場合において、第二十五条の二第一項中「事業主」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「その雇用する労働者」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員は」と、「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第三十六項」と読み替えるものとする。
|
|
39 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「同項の規定による申出」とあるのは「第六十一条第三十八項に規定する行政執行法人対象措置」と、「当該申出をした労働者」とあるのは「当該行政執行法人対象措置の対象となる職員」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「労働者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
|
40 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人対象措置に係る承認の請求をし、若しくは第三十四項の規定により当該職員に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
|
(新設)
|
|
41 行政執行法人の長は、職員のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に関して、職員の承認の請求に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇、第三十四項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるように努めるとともに、次に掲げる職員に関して、始業時刻変更等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
|
(新設)
|
|
一 その一歳(当該職員が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては一歳六か月、当該職員が同条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。同号において同じ。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの
|
(新設)
|
|
二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する職員(国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をすることができる者を除く。)
|
(新設)
|
|
42 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
|
(新設)
|
|
43 行政執行法人の長は、職員のうち、その家族を介護する職員に関して、行政執行法人介護休業、行政執行法人介護休暇又は介護時間休業に関する制度に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
|
(新設)
|
|
44 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その要介護家族を介護する職員で行政執行法人介護休業をしていないものに関して、職員の承認の請求に基づく在宅勤務等をさせることにより当該職員が就業しつつその要介護家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
|
(新設)
|
|
45 行政執行法人の長は、職場において行われる職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、行政執行法人介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
|
(新設)
|
|
46 第二十五条第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
|
47 第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第四十五項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第四十五項」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
|
48 行政執行法人の長は、その講じた措置に関して、職員から第二十八項、第二十九項各号、第三十四項、第四十一項又は第四十四項の規定による承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
|
(新設)
|
| 第六十一条の二 | |
|
第六十一条の二 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、第六十条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、地方公務員に関しては、適用しない。
|
(新設)
|
|
2 地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
|
(新設)
|
|
3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(以下この条において「地方公共団体等の職員」という。)(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。)以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。次項及び第五項において同じ。)は、同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において「任命権者等」という。)の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護をするため、休業をすることができる。
|
(新設)
|
|
4 前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
|
(新設)
|
|
5 任命権者等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、短時間勤務職員以外の非常勤職員のうち、同項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
|
(新設)
|
|
6 地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。次項から第九項までにおいて同じ。)であって小学校第三学年修了前の子を養育するものは、任命権者等の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするため、休暇を取得することができる。
|
(新設)
|
|
7 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
|
(新設)
|
|
8 第六項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
|
(新設)
|
|
9 任命権者等は、第六項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
|
(新設)
|
|
10 地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。
|
(新設)
|
|
11 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
|
(新設)
|
|
12 第十項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
|
(新設)
|
|
13 任命権者等は、第十項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
|
(新設)
|
|
14 任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
|
(新設)
|
|
15 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
|
16 任命権者等は、地方公共団体等の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公共団体等の職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
|
(新設)
|
|
17 前項の規定は、地方公共団体等の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
|
18 任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
|
(新設)
|
|
19 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
|
20 地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第二十二項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。
|
(新設)
|
|
21 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
|
(新設)
|
|
22 任命権者等は、第二十項の規定による承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
|
(新設)
|
|
23 任命権者等は、職場において行われる地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該地方公共団体等の職員の勤務環境が害されることのないよう、当該地方公共団体等の職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
|
(新設)
|
|
24 第二十五条第二項の規定は、地方公共団体等の職員が前項の相談を行い、又は任命権者等による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
|
25 第二十五条の二の規定は、地方公共団体等の職員に係る第二十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する任命権者等(以下この条において「任命権者等」という。)」と、同条第二項及び第四項中「事業主」とあり、並びに同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第二項中「その雇用する労働者」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する地方公共団体等の職員(以下この項及び第四項において「地方公共団体等の職員」という。)」と、「当該労働者」とあるのは「当該地方公共団体等の職員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公共団体等の職員は」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条の二第二十三項」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
労働者派遣法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第四十七条の三(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例) | |
|
第四十七条の三 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条の二、第二十三条の三第七項、第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
|
第四十七条の三 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第二項、第二十三条の二、第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
|
障害者雇用促進法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十二条(障害者職業センターとの連携等) | 第十二条(障害者職業センターとの連携) |
|
第十二条 公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
|
第十二条 公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
|
|
2 公共職業安定所及び第十九条第一項に規定する障害者職業センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労選択支援を受けた者から同項の結果の提供を受けたときは、その結果を参考として、前条及び前項の適性検査、職業指導等を行うものとする。
|
(新設)
|
| 第二十条(障害者職業総合センター) | |
|
四 広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号において同じ。)その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導、研修その他の援助を行うこと。
|
四 広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
|
| 第七十条(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例) | |
|
第七十条 第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四十三条第三項及び第五項、第四十四条第三項並びに第四十五条の二第四項及び第六項(第四十五条の三第六項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス(同法第五条第十五項に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
|
第七十条 第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四十三条第三項及び第五項、第四十四条第三項並びに第四十五条の二第四項及び第六項(第四十五条の三第六項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス(同法第五条第十四項に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
|
雇用保険法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条(目的) | |
|
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
|
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
|
| 第三条(雇用保険事業) | |
|
第三条 雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
|
第三条 雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
|
| 第十条(失業等給付) | |
|
5 教育訓練給付は、次のとおりとする。
|
5 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
|
|
一 教育訓練給付金
|
(新設)
|
|
二 教育訓練休暇給付金
|
(新設)
|
| 第十四条(被保険者期間) | |
|
三 当該被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、第六十条の三第一項に規定する休暇開始日前における被保険者であつた期間
|
(新設)
|
| 第二十二条(所定給付日数) | |
|
3 前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。
|
3 前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
|
|
三 教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある者については、第六十条の三第一項に規定する休暇開始日前の被保険者であつた期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間
|
(新設)
|
|
四 育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間
|
(新設)
|
| 第二十三条 | |
|
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
|
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
|
|
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
|
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
|
| 第三十三条 | |
|
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。
|
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
|
|
一 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。)
|
(新設)
|
|
二 第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。)
|
(新設)
|
|
三 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。)
|
(新設)
|
| 第三十七条の六(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例) | |
|
第三十七条の六 前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項及び第六十一条の十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする。
|
第三十七条の六 前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項及び第六十一条の八第一項の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする。
|
|
2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び第五十六条の三第三項第二号の規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、第五十六条の三第三項第二号ロ中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。
|
2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び第五十六条の三第三項第三号の規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、第五十六条の三第三項第三号ロ中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。
|
| 第四十条(特例一時金) | |
|
4 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
|
4 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
|
| 第五十六条の三(就業促進手当) | |
|
一 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
|
一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
|
|
2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
|
2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項第一号ロ又は同項第二号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当
|
|
一 第一項第一号に該当する者 第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である者にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の二を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
|
一 第一項第一号
|
|
二 第一項第二号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
|
二 第一項第
|
|
イ 受給資格者 基本手当日額
|
(新設)
|
|
ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
|
(新設)
|
|
ハ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
|
(新設)
|
|
ニ 日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
|
(新設)
|
|
4 第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
|
4 第一項第一号
|
| 第五十七条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例) | |
|
一 就業促進手当(前条第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
|
一 就業促進手当(前条第一項第一号
|
|
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
|
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
|
| 第六十条(給付制限) | |
|
5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。
|
5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項
|
| 第六十条の二(教育訓練給付金) | |
|
第六十条の二 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
|
第六十条の二 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
|
|
一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者である者
|
一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
|
|
2 前項の支給要件期間は、教育訓練給付金支給対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。
|
2 前項の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。
|
|
4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
|
4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の七十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
|
|
5 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
|
5 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
|
| 第六十条の三(教育訓練休暇給付金) | 第六十条の三(給付制限) |
|
第六十条の三 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して一年の期間内の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る。)について、第六項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
|
第六十条の三
|
|
一 休暇開始日前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して十二箇月に満たないとき。
|
(新設)
|
|
二 当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
|
(新設)
|
|
2 前項第一号の「みなし被保険者期間」は、休暇開始日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
|
2 前項の規定
|
|
3 休暇開始日から起算して一年の期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上教育訓練を受けることができない一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合における第一項の規定の適用については、同項中「一年を」とあるのは「第三項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年)を」と、「一年の期間」とあるのは「同項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)」とする。
|
3 第一項の規定により教育訓練
|
|
4 第一項の教育訓練休暇を取得していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が、休暇開始日から起算して三十日に一回ずつ直前の三十日の各日について行うものとする。
|
(新設)
|
|
5 教育訓練休暇給付金の日額は、教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる一般被保険者(次項において「教育訓練休暇給付金支給対象者」という。)を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額とする。
|
(新設)
|
|
6 教育訓練休暇給付金を支給する日数は、教育訓練休暇給付金支給対象者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第一項、第三項及び第四項の規定を適用した場合の所定給付日数に相当する日数とする。
|
(新設)
|
| 第六十条の四(特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例) | |
|
第六十条の四 特定教育訓練休暇給付金受給者に対する第十四条第二項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定の適用については、第十四条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第二号に」と、第二十二条第一項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「九十日」と、同条第二項中「その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日」とあるのは「百五十日」とし、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
|
(新設)
|
|
2 前項の特定教育訓練休暇給付金受給者とは、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して六箇月を経過する日までに離職した者のうち、受給資格者以外の者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
|
(新設)
|
|
一 当該離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
|
(新設)
|
|
二 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
|
(新設)
|
|
3 前条第三項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「前条第三項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年)」とする。
|
(新設)
|
| 第六十条の五(給付制限) | |
|
第六十条の五 偽りその他不正の行為により教育訓練給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付の全部又は一部を支給することができる。
|
(新設)
|
|
2 前項の規定により教育訓練給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付を支給する。
|
(新設)
|
|
3 第一項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、第六十条の二第二項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。
|
(新設)
|
|
4 第一項の規定により教育訓練休暇給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、第十四条第二項及び第二十二条第三項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。
|
(新設)
|
| 第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金) | |
|
2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
|
2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
|
| 第六十一条の二(高年齢再就職給付金) | |
|
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
|
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
|
|
4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
|
4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号
|
| 第六十一条の四(介護休業給付金) | |
|
2 前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
|
2 前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
|
|
4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ロに定める額」とする。
|
4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ロに定める額」とする。
|
| 第六十一条の六 | 第六十一条の六 |
|
第六十一条の六 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
|
第六十一条の六 育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付
|
|
2 育児休業給付は、次のとおりとする。
|
2
|
|
一 育児休業給付金
|
(新設)
|
|
二 出生時育児休業給付金
|
(新設)
|
|
3 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
|
(新設)
|
|
4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
|
(新設)
|
|
5 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。
|
(新設)
|
| 第六十一条の七(育児休業給付金) | |
|
第六十一条の七 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この章において同じ。)(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳に満たない子))を養育するための休業(以下この節並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号において「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
|
第六十一条の七 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて
|
|
2 被保険者が育児休業についてこの節の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。
|
2 被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。
|
|
3 第一項の「みなし被保険者期間」は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
|
3 第一項の「みなし被保険者期間」は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
|
|
6 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から育児休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
|
6 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から育児休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
|
|
8 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十一条の十第一項第三号及び第二項において同じ。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
|
8 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
|
| 第六十一条の八(出生時育児休業給付金) | |
|
第六十一条の八 出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。第六十一条の十において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。
|
第六十一条の八 出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。
|
|
2 被保険者が出生時育児休業についてこの節の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
|
2 被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
|
|
3 第一項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
|
3 第一項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
|
|
4 出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
|
4 出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
|
|
6 出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、第一項中「限る」とあるのは「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、「当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)」とあるのは「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、「(当該出生時育児休業」とあるのは「(当該育児休業」と、第三項中「出生時育児休業」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」と、第四項中「当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」とする。
|
6
|
|
7 育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「育児休業(」とあるのは「育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業及び」と、同条第五項中「、育児休業」とあるのは「、育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業を除く。)」と、同条第六項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第一項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」とする。
|
7
|
| 第六十一条の十(出生後休業支援給付金) | |
|
第六十一条の十 出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という。)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。
|
(新設)
|
|
一 当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生後休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき。
|
(新設)
|
|
二 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるとき。
|
(新設)
|
|
三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
|
(新設)
|
|
2 被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「第一号及び第二号」とする。
|
(新設)
|
|
一 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
|
(新設)
|
|
二 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合
|
(新設)
|
|
三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業をした場合
|
(新設)
|
|
四 前三号に掲げる場合のほか、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合
|
(新設)
|
|
3 被保険者が出生後休業についてこの節の定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、前二項の規定にかかわらず、出生後休業支援給付金は、支給しない。
|
(新設)
|
|
一 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の出生後休業
|
(新設)
|
|
二 同一の子について当該被保険者が五回以上の出生後休業(当該出生後休業を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の出生後休業
|
(新設)
|
|
三 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生後休業
|
(新設)
|
|
4 第一項第一号の「みなし被保険者期間」は、出生後休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
|
(新設)
|
|
5 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号中「当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日」とあるのは「特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この号及び第四項において同じ。)」と、「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、同項中「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
|
(新設)
|
|
6 出生後休業支援給付金の額は、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業(同一の子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)を乗じて得た額の百分の十三に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
|
(新設)
|
|
7 第一項及び前項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
|
(新設)
|
|
一 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしなかつたとき その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間
|
(新設)
|
|
二 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしたとき 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める期間
|
(新設)
|
|
イ 出産予定日に当該子が出生したとき 当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
|
(新設)
|
|
ロ 出産予定日前に当該子が出生したとき 当該出生の日から当該出産予定日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
|
(新設)
|
|
ハ 出産予定日後に当該子が出生したとき 当該出産予定日から当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
|
(新設)
|
| 第六十一条の十一(給付制限) | |
|
第六十一条の十一 第六十一条の九の規定は、出生後休業支援給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る出生後休業(次条第一項に規定する出生後休業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに出生後休業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「出生後休業に」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
| 第六十一条の十二(育児時短就業給付金) | |
|
第六十一条の十二 育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「育児時短就業」という。)をした場合において、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))にみなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき、又は当該被保険者が育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)をしたとき、若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときに、支給対象月について支給する。
|
(新設)
|
|
2 前項の規定にかかわらず、支給対象月に支払われた賃金の額が、厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定める額(第六項及び第九項において「支給限度額」という。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
|
(新設)
|
|
3 第一項の「みなし被保険者期間」は、育児時短就業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
|
(新設)
|
|
4 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「、特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、「(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「(特例基準日」と、前項中「育児時短就業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
|
(新設)
|
|
5 この条において「支給対象月」とは、被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
|
(新設)
|
|
6 育児時短就業給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
|
(新設)
|
|
一 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額(育児時短就業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(当該被保険者が、当該育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の七第六項に規定する休業開始時賃金日額とし、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の八第四項に規定する休業開始時賃金日額とする。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額未満であるとき 百分の十
|
(新設)
|
|
二 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき 育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
|
(新設)
|
|
7 前項第一号の規定により育児時短就業開始時賃金日額を算定する場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
|
(新設)
|
|
8 第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
|
(新設)
|
|
9 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が令和五年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。
|
(新設)
|
|
10 育児時短就業給付金の支給を受けることができる者が、同一の就業につき高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合において、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けたときは育児時短就業給付金を支給せず、育児時短就業給付金の支給を受けたときは高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を支給しない。
|
(新設)
|
| 第六十一条の十三(給付制限) | |
|
第六十一条の十三 第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る育児時短就業(第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに育児時短就業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「育児時短就業に」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
| 第六十六条(国庫の負担) | |
|
第六十六条 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)、教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る。第三号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第四号において同じ。)、育児休業給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
|
第六十六条 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第三号において同じ。)、育児休業給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
|
|
三 教育訓練給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
|
三 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
|
|
イ 第一号イに掲げる場合 当該教育訓練給付に要する費用の四分の一
|
(新設)
|
|
ロ 第一号ロに掲げる場合 当該教育訓練給付に要する費用の四十分の一
|
(新設)
|
|
四 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
|
四 育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
|
|
五 育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
|
五 第六十四条に規定する職業
|
|
六 第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
|
(新設)
|
|
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち同条第四項に規定する雇用保険率(第三号及び第四号において単に「雇用保険率」という。)に応ずる部分の額
|
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(
|
|
三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
|
三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
|
|
四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第四項第三号に規定する二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
|
四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に
|
|
4 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
|
4 徴収法第十二条第八項の規定によ
|
|
一 次に掲げる額を合計した額
|
(新設)
|
|
イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
|
(新設)
|
|
ロ イの額に相当する額に前項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
|
(新設)
|
|
二 支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
|
(新設)
|
|
5 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第六号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。第六十八条第一項において同じ。)の事務の執行に要する経費を負担する。
|
5
|
| 第六十七条の二 | |
|
第六十七条の二 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び第四項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。
|
第六十七条の二 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(
|
| 第六十八条の二(子ども・子育て支援納付金) | |
|
第六十八条の二 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。
|
(新設)
|
| 第六十九条(不服申立て) | |
|
第六十九条 第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
|
第六十九条 第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
|
| 第七十二条(労働政策審議会への諮問) | |
|
第七十二条 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十条の三第一項第一号若しくは第三項、第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項第一号(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の十二第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項若しくは第六十一条の十第三項第二号の場合又は第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項、第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号若しくは第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
|
第七十二条 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の八第一項の理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項の場合又は同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
|
| 第七十四条(時効) | |
|
第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
|
第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
|
|
2 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額又は第六十一条第一項第二号若しくは第六十一条の十二第二項に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三(第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。
|
2 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額又は第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三(第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。
|
| 第七十六条(報告等) | |
|
第七十六条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
|
第七十六条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
|
|
2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
|
2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
|
|
4 前項の規定は、教育訓練給付、雇用継続給付又は育児休業等給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
|
4 前項の規定は、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
|
| 第七十七条 | |
|
第七十七条 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
|
第七十七条 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
|
| 第七十九条(立入検査) | |
|
第七十九条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
|
第七十九条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
|
| 第八十五条 | |
|
第八十五条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
|
第八十五条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
|
| 第五十六条の三(就業促進手当) | |
|
(削除)
|
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
|
|
(削除)
|
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
|
|
(削除)
|
三 第一項第二号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
|
|
(削除)
|
イ 受給資格者 基本手当日額
|
|
(削除)
|
ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
|
|
(削除)
|
ハ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
|
|
(削除)
|
ニ 日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
|
|
(削除)
|
5 第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
|
| 第六十一条の七(育児休業給付金) | |
|
(削除)
|
9 育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項及び第三十七条の四第三項の規定の適用については、第二十二条第三項中「とする。ただし、当該期間」とあるのは「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間」と、第三十七条の四第三項中「第二十二条第三項」とあるのは「第二十二条第三項(第六十一条の七第九項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
|
| 第六十一条の八(出生時育児休業給付金) | |
|
(削除)
|
8 育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「育児休業(」とあるのは「育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業及び」と、同条第五項中「、育児休業」とあるのは「、育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業を除く。)」と、同条第六項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第一項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」とする。
|
| 第六十六条(国庫の負担) | |
|
(削除)
|
一 次に掲げる額を合計した額
|
|
(削除)
|
イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
|
|
(削除)
|
ロ イの額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
|
|
(削除)
|
二 支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
|
|
(削除)
|
6 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
|
労働保険徴収法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十二条(一般保険料に係る保険料率) | |
|
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
|
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率
|
|
4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。
|
4 雇用保険率は、
|
|
一 失業等給付費等充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第六十四条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の八(次に掲げる事業(イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については、千分の十とし、次項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
|
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
|
|
イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
|
(新設)
|
|
ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
|
(新設)
|
|
ハ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
|
(新設)
|
|
ニ 清酒の製造の事業
|
(新設)
|
|
ホ イからニまでに掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
|
(新設)
|
|
二 育児休業給付費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の五(第八項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
|
二
|
|
三 二事業費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の三・五(第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五とし、第十項又は第十一項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
|
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
|
|
5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫の負担額(同条第一項第五号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第五項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、失業等給付費等充当徴収保険率を千分の四から千分の十二まで(前項第一号に規定する事業については、千分の六から千分の十四まで)の範囲内において変更することができる。
|
5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項の規定による国庫の負担額(同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、雇用保険率を千分の十一・五から千分の十九・五まで(前項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業
|
|
6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(第八項第一号において「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(第三十一条第一項において「二事業率」という。)を乗じて得た額(第十項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
|
6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第八項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率(千分の四の率を雇用保険率で除して得た率を
|
|
7 厚生労働大臣は、第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
|
7 厚生労働大臣は、第五項の規定により雇用保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
|
|
8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。
|
8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、
|
|
一 イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額
|
(新設)
|
|
イ 当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」という。)及びその額を当該会計年度の前年度の育児休業給付額で除して得た率(ロにおいて「育児休業給付額変化率」という。)に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(イにおいて「翌年度育児休業給付額予想額」という。)に係る同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額と翌年度育児休業給付額予想額との差額を当該会計年度末における子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に置かれる育児休業給付資金に加減した額
|
(新設)
|
|
ロ 当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における育児休業給付額及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(次号において「翌々年度育児休業給付額予想額」という。)に係る雇用保険法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額
|
(新設)
|
|
二 翌々年度育児休業給付額予想額
|
(新設)
|
|
9 厚生労働大臣は、前項の規定により育児休業給付費充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る。)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
|
9
|
|
10 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、二事業費充当徴収保険率を一年間千分の三・五の率(同号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。
|
10 第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十三から千分の二十一まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十四から千分の二十二まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
|
|
11 前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、二事業費充当徴収保険率を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更することができる。
|
11 前項の
|
| 第二十二条(印紙保険料の額) | |
|
2 厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
|
2 厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
|
| 第十二条(一般保険料に係る保険料率) | |
|
(削除)
|
四 清酒の製造の事業
|
|
(削除)
|
五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
|
労働組合法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十七条の十四(和解) | |
|
6 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、労働委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条後段の送達も、同様とする。
|
6 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、労働委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条後段の
|
|
8 第四項の和解調書の送達及び第六項後段の送達に関して必要な事項は、政令で定める。
|
8 第四項の和解調書並び
|
厚生年金保険法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) | |
|
3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
|
3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
|
社会保険労務士法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二条の二 | |
|
第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
|
第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である
|
|
2 前項の陳述は、当事者又は代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
|
2 前項の陳述は、当事者又は
|
施行令
職業安定法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条(法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定) | |
|
六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項及び第七項、第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)
|
六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第四項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)
|
労働組合法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十九条(和解調書の正本等の送達等) | |
|
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条の規定は、前項の和解調書の正本の送達及び法第二十七条の十四第六項後段の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣が」と読み替えるものとする。
|
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条の規定は、和解調書の正本等(前項の和解調書の正本並びに法第二十七条の十四第六項後段
|
| 第三十条 | |
|
2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。
|
2 公示送達は、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。
|
国民年金法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第五条の四(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等) | |
|
第五条の四 法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百七十六万千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十六万千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
|
第五条の四 法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百七十万
|
|
2 法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百七十九万四千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百七十九万四千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
|
2 法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百七十二万千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百七十二万千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百七十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
|
年金生活者支援給付金法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条(法第二条第一項に規定する政令で定める額) | |
|
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については八十万九千円とする。
|
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については
|
| 第六条(法第十条第一項に規定する政令で定める額) | |
|
第六条 法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については九十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については九十万九千円とする。
|
第六条 法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十
|
| 第八条(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額) | |
|
第八条 法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額は、法第十五条第一項に規定する扶養親族等(以下この条及び第十九条第一項第二号ロにおいて単に「扶養親族等」という。)がないときは、四百七十九万四千円とし、扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。同号ロにおいて「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(同号ロにおいて単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
|
第八条 法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額は、法第十五条第一項に規定する扶養親族等(以下この条及び第十九条第一項第二号ロにおいて単に「扶養親族等」という。)がないときは、四百七十二万千円とし、扶養親族等があるときは、四百七十二万千円に当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。同号ロにおいて「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(同号ロにおいて単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
|
施行規則
育児・介護休業法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第六十九条の六(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法) | 第六十九条の六(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) |
|
第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認する場合について準用する。
|
第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、第六十九条
|
| 第六十九条の七(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件) | 第六十九条の七(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置) |
|
第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
|
第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
|
|
一 始業及び終業の時刻
|
一 介護休暇に関する制度
|
|
二 就業の場所
|
二 法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所
|
|
三 育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
|
三 法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度
|
|
四 その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
|
四 法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業
|
| 第六十九条の八(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | 第六十九条の八(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項) |
|
第六十九条の八 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第四項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十に定める事項を知らせる場合について準用する。
|
第六十九条の八 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
|
| 第六十九条の九(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | 第六十九条の九(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置) |
|
第六十九条の九 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
|
第六十九条の九
|
|
一 介護休暇に関する制度
|
(新設)
|
|
二 法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
|
(新設)
|
|
三 法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度
|
(新設)
|
|
四 法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
|
(新設)
|
|
五 法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
|
(新設)
|
| 第六十九条の十(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項) | 第六十九条の十(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項) |
|
第六十九条の十 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
|
第六十九条の十
|
|
一 介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
|
(新設)
|
|
二 介護休業申出及び法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先
|
(新設)
|
|
三 雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
|
(新設)
|
| 第六十九条の十一(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置) | 第六十九条の十一(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間) |
|
第六十九条の十一 第六十九条の五の規定は、法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
|
第六十九条の十一 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
|
| 第六十九条の十二(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項) | 第六十九条の十二(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項 |
|
第六十九条の十二 第六十九条の十の規定は、法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
|
第六十九条の十二
|
| 第六十九条の十三(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間) | |
|
第六十九条の十三 法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
|
(新設)
|
|
一 四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
|
(新設)
|
|
二 四十歳に達した日の翌日から起算して一年間
|
(新設)
|
| 第六十九条の十四(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | |
|
第六十九条の十四 法第二十一条第五項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
|
(新設)
|
|
一 面談による方法
|
(新設)
|
|
二 書面を交付する方法
|
(新設)
|
|
三 ファクシミリを利用して送信する方法
|
(新設)
|
|
四 電子メール等の送信の方法
|
(新設)
|
|
2 第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
|
(新設)
|
| 第七十一条の六(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの) | |
|
二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
|
二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
|
| 第七十五条の二(法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの) | |
|
第七十五条の二 法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。
|
(新設)
|
|
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
|
(新設)
|
|
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
|
(新設)
|
| 第七十五条の三(法第二十三条の三第一項の措置) | |
|
第七十五条の三 法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
|
(新設)
|
|
一 一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
|
(新設)
|
|
二 利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
|
(新設)
|
|
イ 一週間の所定労働日数が五日の労働者については、十労働日以上の日数
|
(新設)
|
|
ロ 一週間の所定労働日数が五日以外の労働者については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
|
(新設)
|
|
三 時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。
|
(新設)
|
|
2 前項第三号に規定する単位で利用する法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
(新設)
|
|
3 法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
|
(新設)
|
|
4 法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。
|
(新設)
|
| 第七十五条の四(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの) | |
|
第七十五条の四 法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。
|
(新設)
|
| 第七十五条の五(法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | |
|
第七十五条の五 法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
|
(新設)
|
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
(新設)
|
| 第七十五条の六(法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの) | |
|
第七十五条の六 法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
|
(新設)
|
| 第七十五条の七(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | |
|
第七十五条の七 第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。
|
(新設)
|
| 第七十五条の八(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間) | |
|
第七十五条の八 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
|
(新設)
|
| 第七十五条の九(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項) | |
|
第七十五条の九 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
|
(新設)
|
|
一 法第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。)
|
(新設)
|
|
二 対象措置に係る申出の申出先
|
(新設)
|
|
三 法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
|
(新設)
|
| 第七十五条の十(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置) | |
|
第七十五条の十 第六十九条の五の規定は、法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
|
(新設)
|
| 第七十六条(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | |
|
十一 法第二十三条の三第一項の規定による措置
|
(新設)
|
| 第九十条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | |
|
五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度
|
五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度
|
| 第百一条(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの) | 第百一条(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定める場合) |
|
第百一条 法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。
|
第百一条 法第六十一条第三十四項第一号の
|
|
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
|
(新設)
|
|
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
|
(新設)
|
| 第百二条(法第六十一条第三十四項の措置) | 第百二条(法第六十一条第三十八項の |
|
第百二条 法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
|
第百二条 法第六十一条第三十八項の子の
|
|
一 一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
|
一 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
|
|
二 利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
|
二 国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
|
|
イ 一週間の所定労働日数が五日の行政執行法人の職員については、十日以上の日数
|
(新設)
|
|
ロ 一週間の所定労働日数が五日以外の行政執行法人の職員については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
|
(新設)
|
|
三 時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。
|
三 行政執行法人介護休業
|
|
2 前項第三号に規定する単位で利用する法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
(新設)
|
|
3 法第六十一条第三十四項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
|
(新設)
|
|
4 法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。
|
(新設)
|
| 第百三条(法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの) | 第百三条(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの) |
|
第百三条 法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるものは、行政執行法人の職員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。
|
第百三条 法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
|
| 第百四条(法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | 第百四条(法第六十一条 |
|
第百四条 法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
|
第百四条 法第六十一条
|
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条
|
| 第百五条(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | 第百五条(法第六十一条 |
|
第百五条 第八十九条の規定は、法第六十一条第三十八項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第百七条に定める事項を知らせる場合について準用する。
|
第百五条 法第六十一条
|
| 第百六条(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間) | 第百六条(法第六十一条 |
|
第百六条 法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間は、当該行政執行法人の職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
|
第百六条 法第六十一条
|
| 第百七条(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項) | |
|
第百七条 法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
|
(新設)
|
|
一 法第六十一条第三十八項の行政執行法人対象措置(次号において「行政執行法人対象措置」という。)
|
(新設)
|
|
二 行政執行法人対象措置に係る承認の請求の請求先
|
(新設)
|
|
三 法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度及び同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度
|
(新設)
|
| 第百八条(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置) | |
|
第百八条 第九十二条の規定は、法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
|
(新設)
|
| 第百九条(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法) | |
|
第百九条 第八十九条の規定は、法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認する場合について準用する。
|
(新設)
|
| 第百十条(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件) | |
|
第百十条 法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
|
(新設)
|
|
一 始業及び終業の時刻
|
(新設)
|
|
二 就業の場所
|
(新設)
|
|
三 国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項に規定する育児休業に関する制度、行政執行法人子の看護等休暇に関する制度、法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度、同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度、同条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置、同条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、同条第三十四項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
|
(新設)
|
|
四 その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
|
(新設)
|
| 第百十一条(法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合) | |
|
第百十一条 法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
|
(新設)
|
|
2 法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
|
(新設)
|
| 第百十二条(法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | |
|
第百十二条 法第六十一条第四十一項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
|
(新設)
|
|
一 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
|
(新設)
|
|
二 国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
|
(新設)
|
|
三 行政執行法人介護休業
|
(新設)
|
|
四 行政執行法人子の看護等休暇
|
(新設)
|
|
五 行政執行法人介護休暇
|
(新設)
|
|
六 法第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
|
(新設)
|
|
七 法第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
|
(新設)
|
|
八 法第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
|
(新設)
|
|
九 法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
|
(新設)
|
|
十 法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置
|
(新設)
|
|
十一 介護時間休業
|
(新設)
|
|
十二 法第六十一条第三十四項の規定による措置
|
(新設)
|
| 第百十三条(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの) | |
|
第百十三条 法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
|
(新設)
|
| 第百十四条(法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | |
|
第百十四条 法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
|
(新設)
|
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条の二第六項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
(新設)
|
| 第百十五条(法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | |
|
第百十五条 法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
|
(新設)
|
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一の二第十項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
(新設)
|
| 第百十六条(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度) | |
|
第百十六条 法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
|
(新設)
|
|
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
|
(新設)
|
|
二 地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
|
(新設)
|
|
三 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
|
(新設)
|
|
四 法第六十一条の二第三項の規定による休業
|
(新設)
|
|
五 法第六十一条の二第六項の規定による休暇
|
(新設)
|
|
六 法第六十一条の二第十項の規定による休暇
|
(新設)
|
|
七 法第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
|
(新設)
|
|
八 法第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
|
(新設)
|
|
九 法第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
|
(新設)
|
|
十 法第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
|
(新設)
|
| 第六十九条の七(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | |
|
(削除)
|
五 法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
|
| 第六十九条の八(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項) | |
|
(削除)
|
一 介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
|
|
(削除)
|
二 介護休業申出及び法第二十一条第二項の介護両立支援制度等申出の申出先
|
|
(削除)
|
三 雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
|
| 第六十九条の十一(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間) | |
|
(削除)
|
一 四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
|
|
(削除)
|
二 四十歳に達した日の翌日から起算して一年間
|
| 第六十九条の十二(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) | |
|
(削除)
|
一 面談による方法
|
|
(削除)
|
二 書面を交付する方法
|
|
(削除)
|
三 ファクシミリを利用して送信する方法
|
|
(削除)
|
四 電子メール等の送信の方法
|
|
(削除)
|
2 第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
|
| 第百一条(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定める場合) | |
|
(削除)
|
2 法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
|
| 第百二条(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める制度又は措置) | |
|
(削除)
|
四 行政執行法人子の看護等休暇
|
|
(削除)
|
五 行政執行法人介護休暇
|
|
(削除)
|
六 法第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
|
|
(削除)
|
七 法第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
|
|
(削除)
|
八 法第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
|
|
(削除)
|
九 法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
|
|
(削除)
|
十 法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置
|
|
(削除)
|
十一 介護時間休業
|
| 第百五条(法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) | |
|
(削除)
|
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一の二第十項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
|
| 第百六条(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度) | |
|
(削除)
|
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
|
|
(削除)
|
二 地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
|
|
(削除)
|
三 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
|
|
(削除)
|
四 法第六十一条の二第三項の規定による休業
|
|
(削除)
|
五 法第六十一条の二第六項の規定による休暇
|
|
(削除)
|
六 法第六十一条の二第十項の規定による休暇
|
|
(削除)
|
七 法第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
|
|
(削除)
|
八 法第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
|
|
(削除)
|
九 法第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
|
|
(削除)
|
十 法第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
|
障害者雇用促進法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十三条の二(障害者能力開発助成金) | |
|
一 法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号において「事業主等」という。)であつて、障害者(障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である者に限る。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(次号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十四項に規定する就労移行支援若しくは同条第十五項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。次号において同じ。)に関する計画を、機構に提出し、認定を受けたもの
|
一 法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号において「事業主等」という。)であつて、障害者(障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である者に限る。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(次号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。次号において同じ。)に関する計画を、機構に提出し、認定を受けたもの
|
介護労働者法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条(介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス) | |
|
四十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十八項に規定する地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練
|
四十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十七項に規定する地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練
|
雇用保険法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条(事務の管轄) | |
|
一 法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)、法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金支給対象者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)、法第六十条の三第五項に規定する教育訓練休暇給付金支給対象者(以下「教育訓練休暇給付金支給対象者」という。)並びに法附則第十一条の二第一項に規定する者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務(第十四条の二の規定による事務を除く。)、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
|
一 法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
|
|
五 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
|
五 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付
|
| 第十条(被保険者証の交付) | |
|
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることを証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
|
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であること
|
| 第十四条の二(一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出) | 第十四条の二(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出) |
|
第十四条の二 事業主は、その雇用する一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)が第百一条の二の十八第一項に規定する教育訓練休暇を開始したときは、法第七条の規定により、法第六十条の三第一項に規定する休暇開始日(以下「休暇開始日」という。)の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書(様式第十号の二の二)に雇用契約書、賃金台帳その他の休暇開始日及びその日前の賃金の額を証明することができる書類並びに就業規則その他の当該事業主が教育訓練休暇制度を設けていることを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
第十四条の二 事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額
|
|
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書の提出を受けたときは、当該雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票(様式第十号の二の二)を当該一般被保険者に交付しなければならない。
|
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票
|
| 第十四条の三(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出) | 第十四条の三(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児 |
|
第十四条の三 事業主は、法第七条の規定により、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の三。以下「休業等開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間
|
|
一 その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
|
(新設)
|
|
二 その雇用する被保険者が法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六、第百一条の二十九の二、第百一条の三十、第百一条の四十及び第百一条の四十三において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合 第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日
|
(新設)
|
|
三 その雇用する被保険者が法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(同一の子について二回以上の同項に規定する就業をした場合にあつては、初回の就業に限る。以下この条及び第六十五条の十二において「初回育児時短就業」という。)を開始した場合(当該被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。) 第百一条の四十八第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日
|
(新設)
|
|
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三。次条並びに次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業等開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
|
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。
|
| 第十四条の四(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出) | |
|
第十四条の四 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、法第七条の規定により、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
(新設)
|
|
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
|
(新設)
|
|
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。
|
(新設)
|
|
4 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
|
(新設)
|
| 第十七条の二(未支給失業等給付の請求手続) | |
|
第十七条の二 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十三第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
|
第十七条の二 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付
|
|
五 就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
|
五 教育訓練給付
|
|
六 教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
|
六 就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
|
|
七 教育訓練休暇給付金 死亡した教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる者に係る第百一条の二の十九第二項の教育訓練休暇給付金受給資格決定通知その他の職業安定局長が定める書類
|
(新設)
|
|
4 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第七十七条及び第百一条の二の二十八において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
4 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
| 第十九条(受給資格の決定) | |
|
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当することを証明することができる書類の提出を命ずることができる。
|
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する
|
| 第二十条(受給期間内に再就職した場合の受給手続) | |
|
第二十条 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下この条において「受給期間」という。)内に就職したときは、当該受給期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
|
第二十条 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
|
|
2 受給資格者は、受給期間内に就職し、当該受給期間内に再び離職し、当該受給期間に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
|
2 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間
|
| 第二十七条 | |
|
第二十七条 法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下この節において「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
第二十七条 法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
| 第三十一条(受給期間延長の申出) | |
|
第三十一条 法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
|
第三十一条 法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当すること
|
|
7 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けたときは、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
|
7 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
|
| 第三十一条の六(支給の期間の特例の申出) | |
|
第三十一条の六 法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
|
第三十一条の六 法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当すること
|
| 第六十五条の五(準用) | |
|
第六十五条の五 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格に」とあるのは「高年齢受給資格に」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該高年齢受給資格者」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「失業の認定日」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定日」と、「失業の認定を」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「、受給資格者に」とあるのは「、高年齢受給資格者に」と、「受給資格者の」とあるのは「高年齢受給資格者の」と、「受給資格者(」とあるのは「高年齢受給資格者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「高年齢受給資格者について」と、「失業の認定又は」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定又は」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と、第二十条、第二十二条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「高年齢受給資格者は」と読み替えるものとする。
|
第六十五条の五 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「
|
| 第六十五条の十二(特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例) | |
|
第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の三第一項の規定は、適用しない。
|
第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
|
| 第六十九条(準用) | |
|
第六十九条 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格に」とあるのは「特例受給資格に」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該特例受給資格者」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「失業の認定日」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定日」と、「失業の認定を」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定を」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「、受給資格者に」とあるのは「、特例受給資格者に」と、「受給資格者の」とあるのは「特例受給資格者の」と、「受給資格者(」とあるのは「特例受給資格者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「特例受給資格者について」と、「失業の認定又は」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定又は」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と、第二十条、第二十二条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「特例受給資格者は」と読み替えるものとする。
|
第六十九条 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「
|
| 第七十七条(準用) | |
|
第七十七条 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者について」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「、受給資格者」とあるのは「、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
|
第七十七条 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
|
| 第八十一条の二 | |
|
第八十一条の二 法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
|
第八十一条の二 法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
|
| 第八十二条の五(再就職手当の支給申請手続) | |
|
一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することを証明することができる書類
|
一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当すること
|
|
二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことを証明することができる書類
|
二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したこと
|
| 第八十四条(常用就職支度手当の支給申請手続) | |
|
第八十四条 受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、法第五十六条の三第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者であるときは、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者に該当することを証明することができる書類を添えなければならない。
|
第八十四条 受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当すること
|
| 第百一条の二の四(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明) | |
|
三 第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十三第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。第百一条の二の十三第五項第一号において「受講証明書」という。))
|
三 第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
|
| 第百一条の二の五(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間) | |
|
第百一条の二の五 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二十年とする。)とする。
|
第百一条の二の五 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者
|
|
2 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付金適用対象期間延長申請書(様式第十六号)に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことを証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
2 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第十六号)に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないこと
|
|
3 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付金適用対象期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。
|
3 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。
|
| 第百一条の二の七(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率) | |
|
イ 当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日までの間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)における連続する六箇月間(第百一条の二の十三第七項第一号において「対象期間」という。)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
|
イ 当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日までの間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)における連続する六箇月間(第百一条の二の十二第七項第一号において「対象期間」という。)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
|
| 第百一条の二の八(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額) | |
|
四 前条第四号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十三第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
|
四 前条第四号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
|
| 第百一条の二の十一(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) | |
|
第百一条の二の十一 教育訓練給付金支給対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金(第百一条の二の七第一号及び第二号関係)支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
第百一条の二の十一
|
|
2 教育訓練給付金支給対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
|
2 教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
|
| 第百一条の二の十二(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) | 第百一条の二の十二(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) |
|
第百一条の二の十二 教育訓練給付金支給対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
第百一条の二の十二 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、
|
|
一 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
|
一 担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
|
|
二 運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
|
二 過去に特定一般教育訓練
|
|
三 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
|
三 その他職業安定局長が定める書類
|
|
四 その他職業安定局長が定める書類
|
(新設)
|
|
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付金支給対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
|
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当するものと認めたときは
|
|
一 教育訓練給付金を支給する旨
|
一
|
|
二 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
|
二 第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき
|
|
3 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金(第百一条の二の七第一号及び第二号関係)支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
3
|
|
一 特定一般教育訓練修了証明書
|
(新設)
|
|
二 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。次項において同じ。)の額を証明することができる書類
|
(新設)
|
|
三 前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
|
(新設)
|
|
四 当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
|
(新設)
|
|
五 その他厚生労働大臣が定める書類
|
(新設)
|
|
4 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書(様式第三十三号の二の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
4 この条及び第百一条の二の十五において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
|
|
一 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
|
(新設)
|
|
二 当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
|
(新設)
|
|
三 第二項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
|
(新設)
|
|
四 当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
|
(新設)
|
|
五 その他厚生労働大臣が定める書類
|
(新設)
|
|
5 教育訓練給付金支給対象者は、第一項、第三項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号、第三項第五号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
|
5 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、
|
|
6 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
|
6 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第五号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする
|
|
一 特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
|
一 全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
|
|
二 特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
|
二 当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
|
| 第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) | 第百一条の二の十三(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) |
|
第百一条の二の十三 教育訓練給付金支給対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
第百一条の二の十三
|
|
一 担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
|
(新設)
|
|
二 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
|
(新設)
|
|
三 その他職業安定局長が定める書類
|
(新設)
|
|
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付金支給対象者であつて第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の四)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付金支給対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
|
(新設)
|
|
一 支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
|
(新設)
|
|
二 第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべきそれぞれの期間
|
(新設)
|
|
3 管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
|
(新設)
|
|
4 この条及び第百一条の二の十六において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
|
(新設)
|
|
5 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付金支給対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金(第百一条の二の七第四号関係)支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
(新設)
|
|
一 受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
|
(新設)
|
|
二 当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
|
(新設)
|
|
三 当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
|
(新設)
|
|
四 その他厚生労働大臣が定める書類
|
(新設)
|
|
6 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第五号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付金支給対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金(第百一条の二の七第五号関係)支給申請書(様式第三十三号の二の六)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
(新設)
|
|
一 全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
|
(新設)
|
|
二 当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
|
(新設)
|
|
三 当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
|
(新設)
|
|
四 その他厚生労働大臣が定める書類
|
(新設)
|
|
7 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付金支給対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金(第百一条の二の七第六号関係)支給申請書(様式第三十三号の二の七)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
(新設)
|
|
一 対象期間に支払われた賃金の額及び当該被保険者の基準日の直前の離職の日前の賃金の額(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、基準日前の賃金の額)を証明することができる書類
|
(新設)
|
|
二 その他厚生労働大臣が定める書類
|
(新設)
|
|
8 教育訓練給付金支給対象者は、第一項、第五項、第六項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号、第六項第四号及び前項各号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
|
(新設)
|
|
9 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
|
(新設)
|
|
一 専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
|
(新設)
|
|
二 専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) | 第百一条の二の十四( |
|
第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
|
第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、
|
| 第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) | 第百一条の二の十五(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) |
|
第百一条の二の十五 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
|
第百一条の二の十五 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に
|
|
2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
|
2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
|
| 第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) | 第百一条の二の十六(準用) |
|
第百一条の二の十六 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
|
第百一条の二の十六 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
|
|
2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の十七(準用) | |
|
第百一条の二の十七 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「、受給資格者に」とあるのは「、教育訓練給付金の支給を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十三第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「又は住所若しくは居所」とあるのは「、住所若しくは居所又は電話番号」と、「受給資格者氏名変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者について」と、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者は」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の十八(法第六十条の三第一項の休暇) | |
|
第百一条の二の十八 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労働その他の職業安定局長が定める理由(第百一条の二の二十五において「自己の労働等」という。)によつて収入を得ていない日について支給する。
|
(新設)
|
|
2 前項の教育訓練休暇は、法第六十条の三第一項に規定する教育訓練休暇であつて、当該休暇の期間が三十日以上であり、かつ、次に掲げる訓練を受けるものとして、事業主の承認を受けたものとする。
|
(新設)
|
|
一 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が行う教育訓練
|
(新設)
|
|
二 第百一条の二の二の規定による通知を受けた指定教育訓練実施者が行う教育訓練
|
(新設)
|
|
三 前二号に掲げるもののほか、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
|
(新設)
|
| 第百一条の二の十九(教育訓練休暇給付金の受給資格の決定) | |
|
第百一条の二の十九 教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、運転免許証その他の教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類、休暇開始日前に教育訓練休暇(前条第二項に規定する教育訓練休暇をいう。以下同じ。)を取得することについて事業主の承認を受けたことを証明することができる書類及び雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票を添えて教育訓練休暇給付金支給申請書(様式第三十三号の二の十)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、その者が第百一条の二の二十四第五項の規定により教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
|
(新設)
|
|
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練休暇給付金支給申請書を提出した者が、法第六十条の三第一項本文(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の二の二十一において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第六十条の三第四項の規定によりその者が教育訓練休暇を取得していることについての認定(以下「教育訓練休暇取得の認定」という。)を受けるべき日(以下「教育訓練休暇取得認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知(様式第三十三号の二の十一)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十(教育訓練休暇給付金の支給に係る事項の変更の届出) | |
|
第百一条の二の二十 教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇給付金支給申請書その他前条第一項に規定する書類の記載事項に変更があつたときは、速やかに、変更の事実を証明することができる書類及び変更内容について事業主の承認を受けたことを証明することができる書類を添えて、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十一(法第六十条の三第一項に規定する期間内に再び教育訓練休暇を取得した場合の受給手続) | |
|
第百一条の二の二十一 教育訓練休暇給付金支給対象者は、法第六十条の三第一項本文に規定する期間内に教育訓練休暇を終了したときは、当該期間内に再び教育訓練休暇を開始し、当該期間に係る受給資格に基づき教育訓練休暇給付金の支給を受ける場合のために、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知を保管しなければならない。
|
(新設)
|
|
2 教育訓練休暇給付金支給対象者は、前項の期間内に教育訓練休暇を終了し、当該期間内に再び教育訓練休暇を開始し、当該期間に係る受給資格に基づき教育訓練休暇給付金の支給を受けようとするときは、その保管する教育訓練休暇給付金受給資格決定通知を添えて教育訓練休暇給付金支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、法第六十条の三第一項本文の規定に該当すると認めたときは、その者について新たに教育訓練休暇取得認定日を定め、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十二(法第六十条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) | |
|
第百一条の二の二十二 法第六十条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
|
(新設)
|
|
一 事業所の休業
|
(新設)
|
|
二 出産
|
(新設)
|
|
三 事業主の命による外国における勤務
|
(新設)
|
|
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
(新設)
|
|
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十三(法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由) | |
|
第百一条の二の二十三 法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
|
(新設)
|
|
一 疾病又は負傷
|
(新設)
|
|
二 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十四(法第六十条の三第三項に規定する申出) | |
|
第百一条の二の二十四 法第六十条の三第三項の申出は、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することを証明することができる書類その他の職業安定局長が定める書類を添えて教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
|
(新設)
|
|
2 前項の申出は、当該申出に係る者が法第六十条の三第三項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、休暇開始日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
|
(新設)
|
|
3 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
|
(新設)
|
|
4 第二項ただし書の場合における第一項の申出は、教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
|
(新設)
|
|
5 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第六十条の三第三項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合において、当該申出をした者が第百一条の二の十九第二項の規定により教育訓練休暇給付金受給資格決定通知の交付を受けているときは、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
|
(新設)
|
|
6 前項の規定により教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、交付を受けた教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が教育訓練休暇給付金受給資格決定通知の交付を受けたときは、提出を受けた教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
|
(新設)
|
|
一 その者が提出した教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合
|
(新設)
|
|
二 法第六十条の三第三項に規定する理由がやんだ場合
|
(新設)
|
|
7 第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第二項ただし書の場合における第一項の申出に準用する。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十五(教育訓練休暇取得の認定) | |
|
第百一条の二の二十五 教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所の長が定める教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書(様式第三十三号の二の十二)に教育訓練休暇の取得を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該教育訓練休暇取得認定日に提出することが困難である場合は、当該教育訓練休暇取得認定日から七日以内に提出することができる。
|
(新設)
|
|
2 教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けた期間中に自己の労働等によつて収入を得たときは、当該収入を得るに至つた日の後における最初の教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書により、収入のあつた日数その他の事項を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
|
(新設)
|
|
3 管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない教育訓練休暇給付金支給対象者について、自己の労働等による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、教育訓練休暇取得認定日において教育訓練休暇取得の認定をした日分の教育訓練休暇給付金の支給の決定を次の教育訓練休暇給付金を支給すべき日まで延期することができる。
|
(新設)
|
|
4 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その処分に関する事項を教育訓練休暇給付金支給決定通知(様式第三十三号の二の十一)に記載した上、交付しなければならない。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十六(教育訓練休暇取得の認定の方法等) | |
|
第百一条の二の二十六 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇取得の認定に当たつては、前条第一項の規定により提出された教育訓練休暇取得認定申告書に記載された訓練内容を確認するものとする。
|
(新設)
|
|
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、教育訓練休暇給付金支給対象者に対し、運転免許証その他の教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提示を命ずることができる。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給) | |
|
第百一条の二の二十七 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十八(準用) | |
|
第百一条の二の二十八 第二十五条、第二十八条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)及び第五十四条の規定は、教育訓練休暇給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「疾病又は負傷のために第百一条の二の二十五に規定する手続を行うことができなかつた教育訓練休暇給付金支給対象者であつて、その期間が継続して十五日未満であるもの」と、「失業の認定を」とあるのは「教育訓練休暇取得の認定を」と、「失業の認定日」とあるのは「教育訓練休暇取得認定日」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者の」と、「法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者」とあるのは「天災その他やむを得ない理由のために第百一条の二の二十五に規定する手続を行うことができなかつた教育訓練休暇給付金支給対象者」と、「、受給資格者に」とあるのは「、教育訓練休暇給付金支給対象者に」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練休暇給付金の支給を受ける者」と、「当該受給資格者に」とあるのは「当該教育訓練休暇給付金支給対象者に」と、「法第三十一条第一項に規定する者」とあるのは「、教育訓練休暇給付金支給対象者が死亡したため教育訓練休暇取得の認定を受けることができなかつた期間に係る教育訓練休暇給付金の支給を請求する者」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者について」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「交付」と、「又は住所若しくは居所」とあるのは「、住所若しくは居所又は電話番号」と、「失業の認定又は」とあるのは「教育訓練休暇取得の認定又は」と、「受給資格者氏名変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練休暇給付金支給対象者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者氏名変更届又は教育訓練休暇給付金支給対象者住所変更届」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「交付」と、第二十五条、第二十八条及び第四十七条中「に出頭し」とあるのは「の長に対して」と、第二十五条、第二十八条、第四十四条、第四十七条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練休暇給付金受給資格決定通知」と、第二十八条中「に出頭する」とあるのは「の長に対して、教育訓練休暇取得認定申告書を提出する」と、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者は」と、第四十五条及び第四十六条中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給決定通知」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の二十九(法第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの) | |
|
第百一条の二の二十九 法第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。
|
(新設)
|
| 第百一条の二の三十(法第六十条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) | |
|
第百一条の二の三十 法第六十条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十六条各号に掲げる理由とする。
|
(新設)
|
| 第百一条の十(準用) | |
|
第百一条の十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該高年齢雇用継続給付を受けることができる者が」と読み替えるものとする。
|
第百一条の十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と読み替えるものとする。
|
| 第百一条の十八(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由) | |
|
四 教育訓練休暇
|
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
|
五 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
|
六 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
(新設)
|
| 第百一条の二十(準用) | |
|
第百一条の二十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該介護休業給付金を受けることができる者が」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
|
第百一条の二十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
|
| 第百一条の二十一(通則) | |
|
第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業等給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
|
第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業等給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付
|
| 第百一条の二十九(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由) | |
|
四 教育訓練休暇
|
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
|
五 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
|
六 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
(新設)
|
| 第百一条の三十二(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由) | |
|
四 教育訓練休暇
|
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
|
五 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
|
六 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
(新設)
|
| 第百一条の三十六(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) | |
|
四 教育訓練休暇
|
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
|
五 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
|
六 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
(新設)
|
| 第百一条の四十四(法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由) | |
|
四 教育訓練休暇
|
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
|
五 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
|
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
|
六 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
|
(新設)
|
| 第百二条(準用) | |
|
第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該育児休業等給付を受けることができる者が」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
|
第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
|
| 第百十六条(両立支援等助成金) | |
|
ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇及び育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
|
ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
|
|
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
|
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主
|
|
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
|
イ
|
|
(1) その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
|
(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置
|
|
(i) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第一号に掲げる措置
|
(新設)
|
|
(ii) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第二号に掲げる措置
|
(新設)
|
|
(iii) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第三号に掲げる措置
|
(新設)
|
|
(iv) 育児・介護休業法施行規則第七十五条の四に規定する措置
|
(新設)
|
|
(v) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に掲げる措置であつて、次の(イ)及び(ロ)に該当するもの
|
(新設)
|
|
(イ) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
|
(新設)
|
|
(ロ) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認めるものであること。
|
(新設)
|
|
(2) その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、(1)(i)、(ii)、(iv)又は(v)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者が(1)(i)から(v)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この(2)及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
|
(2) 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
|
|
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
|
(3) 所定労働時間短縮措置
|
|
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
|
ロ
|
|
(1) その雇用する労働者のうち、その九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇であつて、次のいずれにも該当する制度を設けた中小企業事業主
|
(新設)
|
|
(i) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
|
(新設)
|
|
(ii) 一の年度において十労働日以上が付与されるものであること。
|
(新設)
|
|
(iii) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位で取得することができるものであること。
|
(新設)
|
|
(iv) 所定労働時間を変更することなく利用できるものであること。
|
(新設)
|
|
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
|
(新設)
|
|
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号イ(2)に該当する被保険者(同一の子に係る同一の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用について、既に同号イ(2)に該当するものとして次のイ又はロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下この号において同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
|
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が五人を超える場合
|
|
イ 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
|
イ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
|
|
ロ 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
|
ロ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
|
|
ハ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円
|
(新設)
|
|
14 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
|
14 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号
|
|
一 前項第一号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置をその雇用する労働者のうち、その三歳から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(次号において「中学校修了前の子」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
|
(新設)
|
|
二 前項第一号ロ(1)の制度をその雇用する労働者のうち、その中学校修了前の子を養育するものについて利用できるものとした場合
|
(新設)
|
|
15 第十三項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十三項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
|
15 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
|
|
16 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
|
(新設)
|
|
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
|
(新設)
|
|
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
(1) その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下このイにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
(i) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
|
(新設)
|
|
(ii) 所定外労働の制限の制度
|
(新設)
|
|
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
|
(新設)
|
|
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
|
(新設)
|
|
(v) 所定労働時間の短縮の制度
|
(新設)
|
|
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
|
(新設)
|
|
(2) 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
(1) その雇用する被保険者であつて、月経に起因する症状への対応を図るもの(以下このロにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、月経に起因する症状への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
(i) 月経に起因する症状への対応のための休暇制度(月経に起因する症状への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇及び労働基準法第六十八条の規定による生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(生理日の就業が著しく困難な女性に有給休暇(年次有給休暇を除く。)を付与する場合を除く。)を除く。)
|
(新設)
|
|
(ii) 所定外労働の制限の制度
|
(新設)
|
|
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
|
(新設)
|
|
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
|
(新設)
|
|
(v) 所定労働時間の短縮の制度
|
(新設)
|
|
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
|
(新設)
|
|
(2) 月経に起因する症状への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの月経に起因する症状への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
(1) その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、更年期における心身の不調への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
(i) 更年期における心身の不調への対応のための休暇制度(更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
|
(新設)
|
|
(ii) 所定外労働の制限の制度
|
(新設)
|
|
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
|
(新設)
|
|
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
|
(新設)
|
|
(v) 所定労働時間の短縮の制度
|
(新設)
|
|
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
|
(新設)
|
|
(2) 更年期における心身の不調への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
|
(新設)
|
|
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
|
(新設)
|
|
イ 前号イに該当する中小企業事業主 三十万円
|
(新設)
|
|
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円
|
(新設)
|
|
ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 三十万円
|
(新設)
|
| 第百二十条(国等に対する不支給) | |
|
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
|
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十五項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
|
| 第百四十五条(代理人) | |
|
5 第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
|
5 第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
|
| 第十四条の二(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出) | |
|
(削除)
|
一 その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
|
|
(削除)
|
二 その雇用する被保険者が法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六、第百一条の二十九の二、第百一条の三十、第百一条の四十及び第百一条の四十三において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合 第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日
|
|
(削除)
|
三 その雇用する被保険者が法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(同一の子について二回以上の同項に規定する就業をした場合にあつては、初回の就業に限る。以下この条及び第六十五条の十二において「初回育児時短就業」という。)を開始した場合(当該被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。) 第百一条の四十八第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日
|
| 第百一条の二の十一の二(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) | |
|
(削除)
|
第百一条の二の十一の二 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
|
(削除)
|
一 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
|
|
(削除)
|
二 運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
|
|
(削除)
|
三 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
|
|
(削除)
|
四 その他職業安定局長が定める書類
|
|
(削除)
|
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
|
|
(削除)
|
一 教育訓練給付金を支給する旨
|
|
(削除)
|
二 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
|
|
(削除)
|
3 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
|
(削除)
|
一 特定一般教育訓練修了証明書
|
|
(削除)
|
二 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。次項において同じ。)の額を証明することができる書類
|
|
(削除)
|
三 前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
|
|
(削除)
|
四 当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
|
|
(削除)
|
五 その他厚生労働大臣が定める書類
|
|
(削除)
|
4 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
|
(削除)
|
一 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
|
|
(削除)
|
二 当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
|
|
(削除)
|
三 第二項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
|
|
(削除)
|
四 当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
|
|
(削除)
|
五 その他厚生労働大臣が定める書類
|
|
(削除)
|
5 教育訓練給付対象者は、第一項、第三項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号、第三項第五号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
|
|
(削除)
|
6 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
|
|
(削除)
|
一 特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
|
|
(削除)
|
二 特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
|
| 第百一条の二の十二(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) | |
|
(削除)
|
一 受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
|
|
(削除)
|
二 当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
|
|
(削除)
|
三 当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
|
|
(削除)
|
四 その他厚生労働大臣が定める書類
|
|
(削除)
|
三 当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
|
|
(削除)
|
四 その他厚生労働大臣が定める書類
|
|
(削除)
|
7 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の七)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
|
|
(削除)
|
一 対象期間に支払われた賃金の額及び当該被保険者の基準日の直前の離職の日前の賃金の額(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、基準日前の賃金の額)を証明することができる書類
|
|
(削除)
|
二 その他厚生労働大臣が定める書類
|
|
(削除)
|
8 教育訓練給付対象者は、第一項、第五項、第六項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号、第六項第四号及び前項各号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
|
|
(削除)
|
9 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
|
|
(削除)
|
一 専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
|
|
(削除)
|
二 専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
|
| 第百一条の二の十四(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) | |
|
(削除)
|
2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
|
| 第百十六条(両立支援等助成金) | |
|
(削除)
|
(4) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置
|
|
(削除)
|
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるものを整備する措置
|
|
(削除)
|
ハ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
|
|
(削除)
|
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
|
|
(削除)
|
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
(1) その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下このイにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
(i) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
|
|
(削除)
|
(ii) 所定外労働の制限の制度
|
|
(削除)
|
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
|
|
(削除)
|
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
|
|
(削除)
|
(v) 所定労働時間の短縮の制度
|
|
(削除)
|
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
|
|
(削除)
|
(2) 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
(1) その雇用する被保険者であつて、月経に起因する症状への対応を図るもの(以下このロにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、月経に起因する症状への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
(i) 月経に起因する症状への対応のための休暇制度(月経に起因する症状への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇及び労働基準法第六十八条の規定による生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(生理日の就業が著しく困難な女性に有給休暇(年次有給休暇を除く。)を付与する場合を除く。)を除く。)
|
|
(削除)
|
(ii) 所定外労働の制限の制度
|
|
(削除)
|
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
|
|
(削除)
|
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
|
|
(削除)
|
(v) 所定労働時間の短縮の制度
|
|
(削除)
|
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
|
|
(削除)
|
(2) 月経に起因する症状への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの月経に起因する症状への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
(1) その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、更年期における心身の不調への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
(i) 更年期における心身の不調への対応のための休暇制度(更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
|
|
(削除)
|
(ii) 所定外労働の制限の制度
|
|
(削除)
|
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
|
|
(削除)
|
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
|
|
(削除)
|
(v) 所定労働時間の短縮の制度
|
|
(削除)
|
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
|
|
(削除)
|
(2) 更年期における心身の不調への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
|
|
(削除)
|
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
|
|
(削除)
|
イ 前号イに該当する中小企業事業主 三十万円
|
|
(削除)
|
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円
|
|
(削除)
|
ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 三十万円
|
求職者支援法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十六条の二(教育訓練等を受講する特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助) | |
|
第十六条の二 前条に規定するもののほか、特定求職者の職業に関する教育訓練その他の訓練であって職業安定局長が定めるものの受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
|
(新設)
|
国民年金法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三十一条(裁定の請求) | |
|
ハ 受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
|
ハ 受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十万
|
|
一 前年の所得が三百七十六万千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
|
一 前年の所得が三百七十万
|
|
二 前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
|
二 前年の所得が三百七十万
|
年金生活者支援給付金法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三十二条(認定の請求) | |
|
三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の障害年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得(令第十条第一項の規定によって計算した所得の額をいう。次項並びに第四十七条第二項及び第三項において同じ。)が四百七十九万四千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
|
三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の障害年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得(令第十条第一項の規定によって計算した所得の額をいう。次項並びに第四十七条第二項及び第三項において同じ。)が四百七十二万千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
|
|
一 前年の所得が四百七十九万四千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
|
一 前年の所得が四百七十二万千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
|
|
二 前年の所得が四百七十九万四千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
|
二 前年の所得が四百七十二万千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
|
| 第四十七条(認定の請求) | |
|
三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得が四百七十九万四千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
|
三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得が四百七十二万千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
|
|
一 前年の所得が四百七十九万四千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
|
一 前年の所得が四百七十二万千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
|
|
二 前年の所得が四百七十九万四千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
|
二 前年の所得が四百七十二万千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
|
社会保険労務士法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十三条(審査事項等の記載) | |
|
二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書、同令第十四条の三第一項及び同令第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書
|
二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書
|
介護保険法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第百十三条の二(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験) | |
|
ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する計画相談支援、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
|
ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する計画相談支援、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
|
アプリの改修
特にありません。

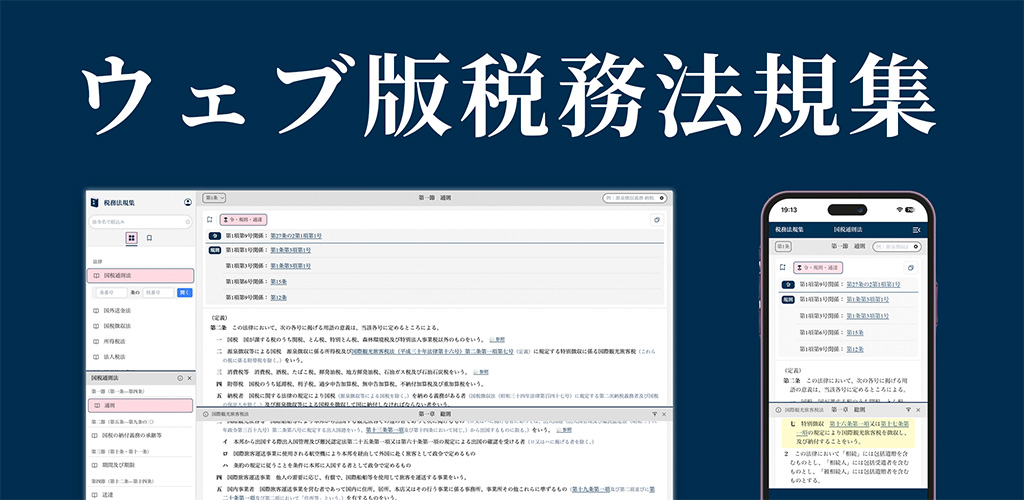



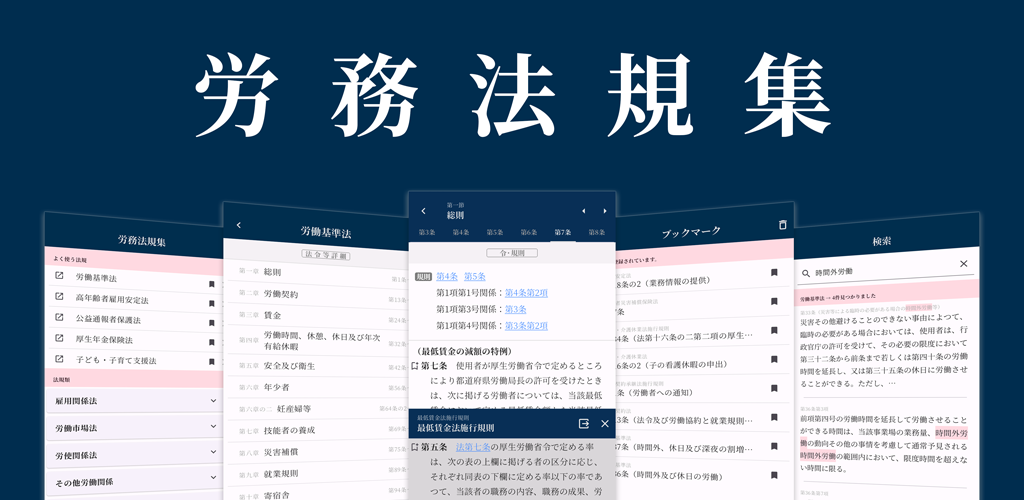
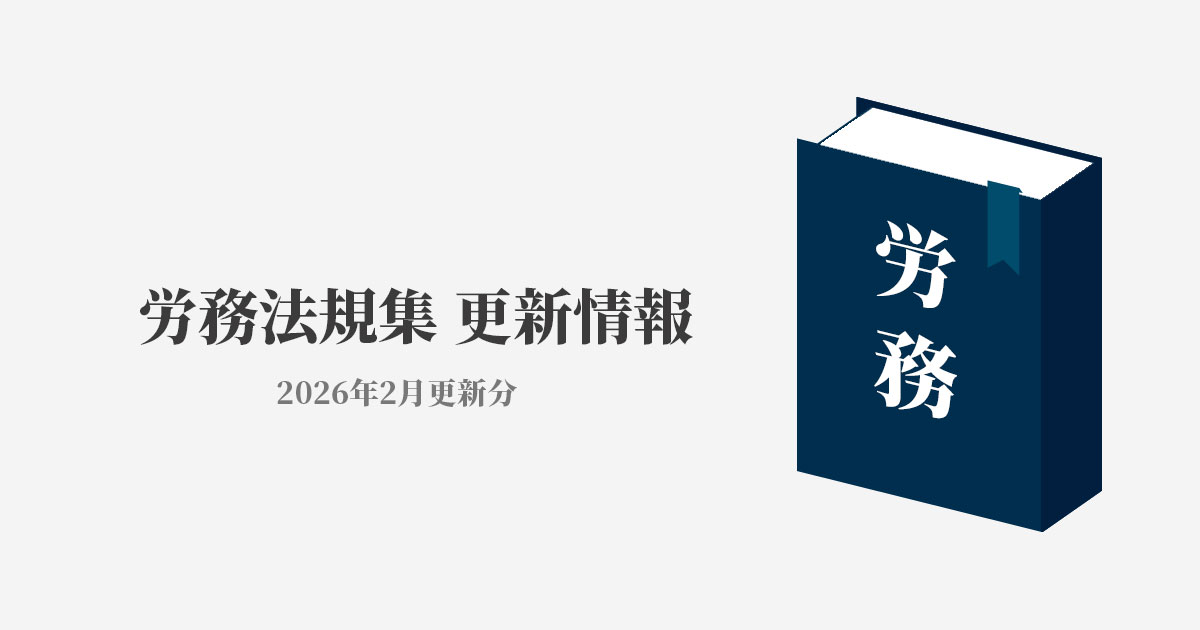

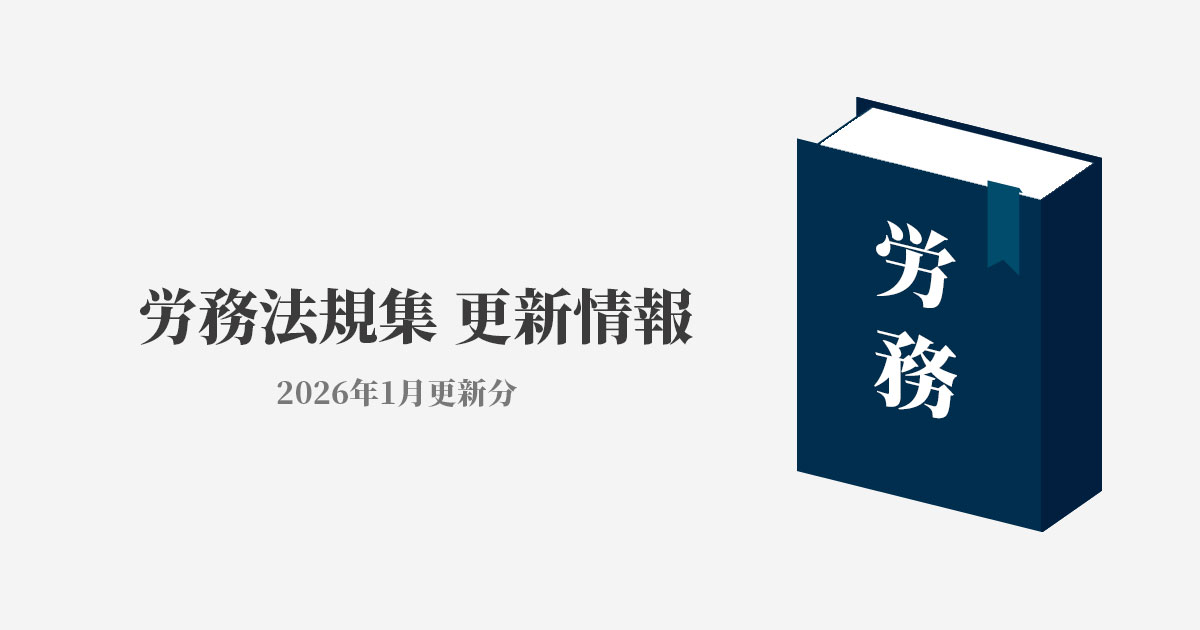
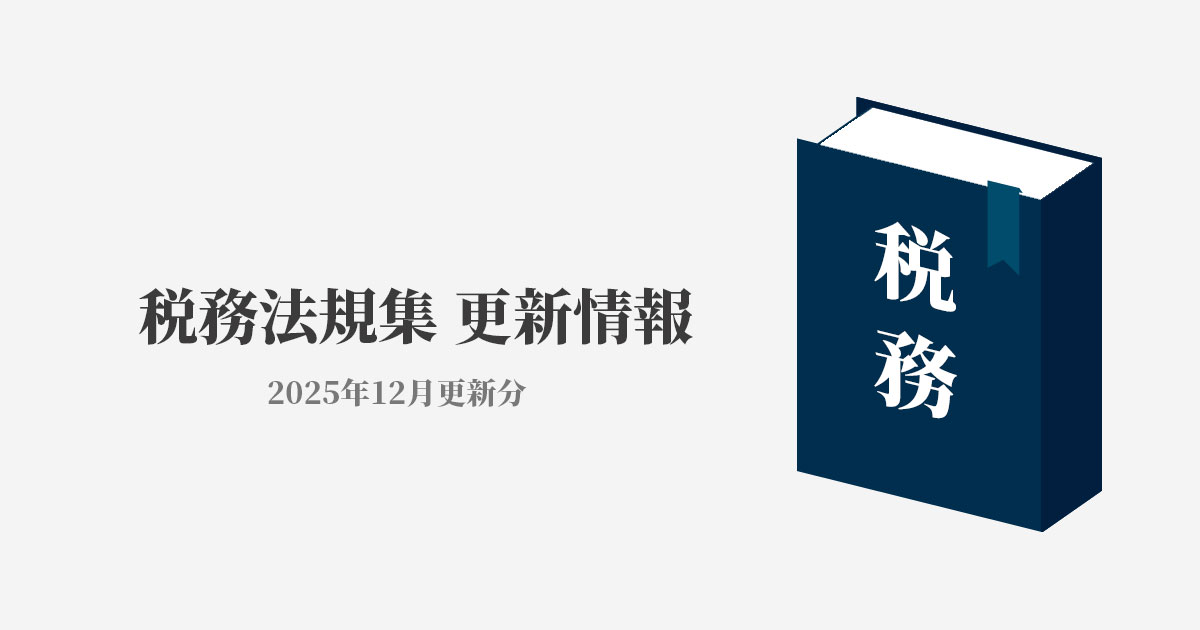
この記事をシェアする
Twitter
Google+
Facebook
はてなブックマーク
Reddit
LinkedIn
StumbleUpon
Email