税務法規集 更新情報(2025年9月度)
対象期間:2025年8月19日から同年9月17日まで
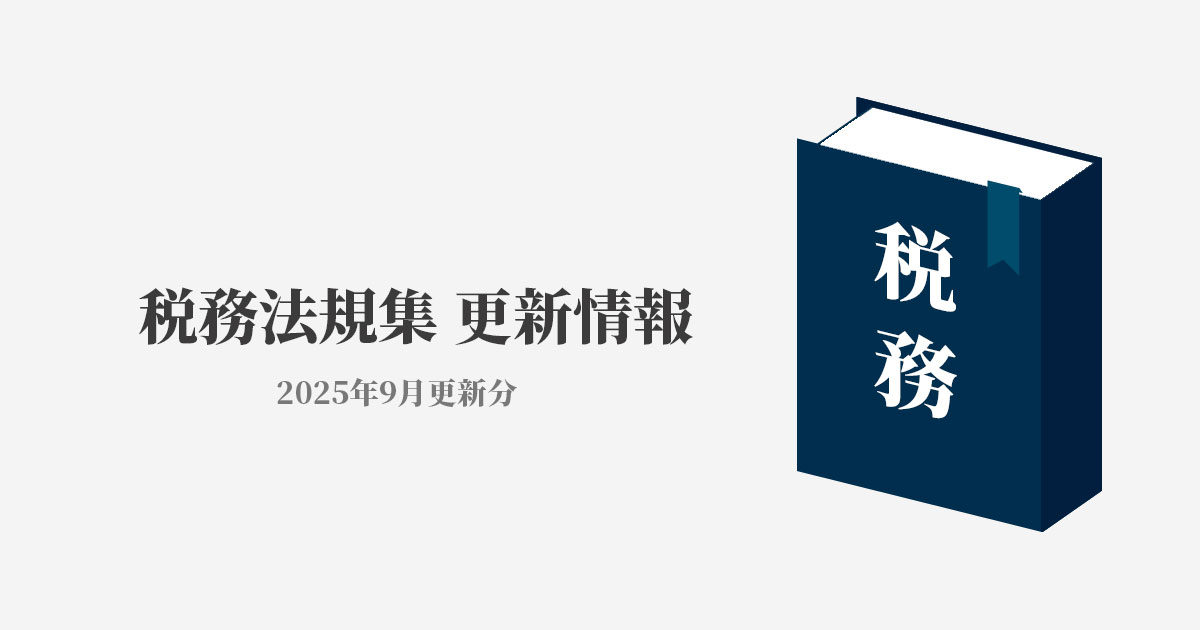
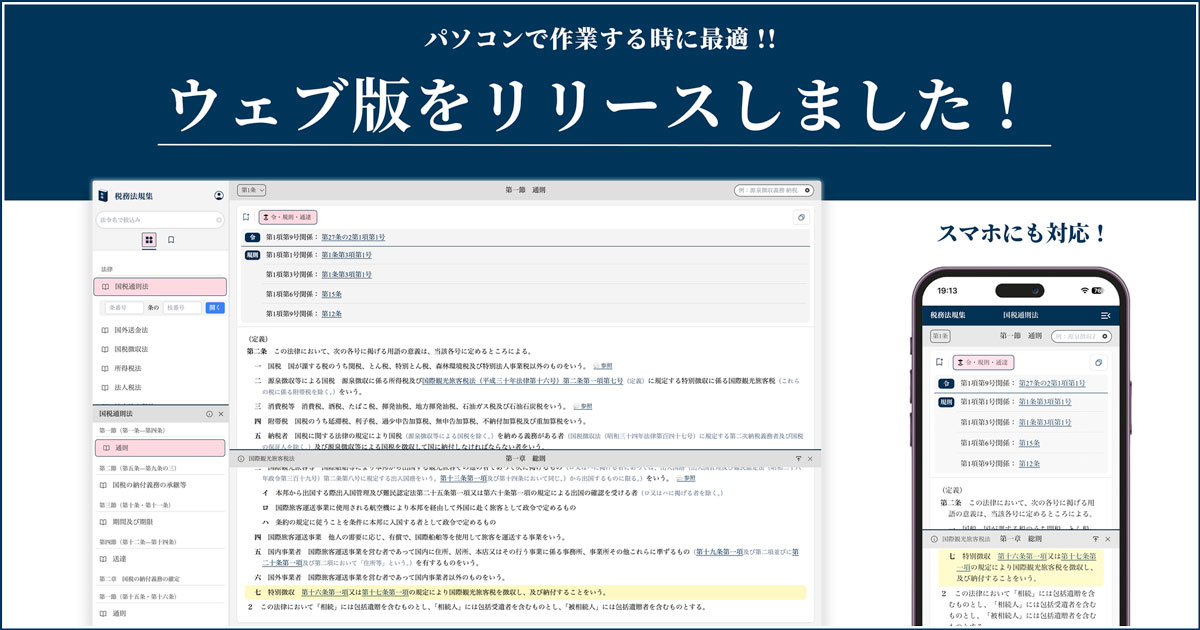
目次
2025年9月度に更新された法令等は以下のとおりです。
以下の法令は改正がありましたが、附則の変更のみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。
- 印紙税法
- 登録免許税法
- 地方税法
- 地方税法施行令
- 地方税法施行規則
法律
租税特別措置法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減) | |
|
4 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十五条の規定により選定された同法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者が、資本金の額の増加(合併による資本金の額の増加及び分割による資本金の額の増加を除く。)について登記を受ける場合において、当該資本金の額の増加が、同法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
|
(新設)
|
施行令
租税特別措置法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第五条の五(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
|
二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
|
二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が令和七年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
|
|
三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
|
三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が令和七年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
|
施行規則
租税特別措置法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第五条の六(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) | |
|
三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号ハに掲げる出資を受ける同号ハに規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
|
三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる
|
|
二 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二項第二号ロに掲げる研究開発
|
二 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発
|
| 第二十条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | |
|
三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号ハに掲げる出資を受ける同号ハに規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
|
三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる
|
|
二 地方独立行政法人法施行令第四条第二項第二号ロに掲げる研究開発
|
二 地方独立行政法人法施行令第四条第二号ロに掲げる研究開発
|
通達
法人税基本通達
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 1-2-3(非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度) | |
|
1-2-3 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条第2項(事業報告等の提出)及び第69条第1項(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)に定める期間をいうのであるから、当該事業年度は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。(平20年課法2-5「三」により追加、令7年課法2-7「二」により改正)
|
1-2-3 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項(事業報告等の提出)及び第50条
|
| 1-2-5 | |
|
1-2-5 削除(平14年課法2-1「二」により追加、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」により改正、平22年課法2-1「三」により削除)
|
1-2-5 削除(平14年課法2-1「二」により追加、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」により改正、
|
| 2-1-1(収益の計上の単位の通則) | |
|
2-1-1 資産の販売若しくは譲渡若しくは役務の提供(2-1-1の10(資産の引渡しの時の価額等の通則)及び2-1-40の2(返金不要の支払の帰属の時期)を除き、平成30年3月30日付企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識基準」という。)の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下この節において「資産の販売等」という。)又は資産の賃貸借に係る収益の額は、原則として個々の契約ごとに計上する。ただし、次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによりその収益の額を計上することができる。(平30年課法2-8「二」、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-1 資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(2-1-1の10及び2-1-40の2を除き、平成30年3月30日付企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下
|
|
(1) 資産の販売等 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。
|
(1)
|
|
イ 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、当該複数の契約において約束した資産の販売等を組み合わせて初めて単一の履行義務(収益認識基準第7項に定める履行義務をいう。以下2-1-21の7までにおいて同じ。)となる場合 当該複数の契約による資産の販売等の組合せ
|
(新設)
|
|
ロ 一の契約の中に複数の履行義務が含まれている場合 それぞれの履行義務に係る資産の販売等
|
(新設)
|
|
(注) 1 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、次のいずれかに該当する場合には、当該複数の契約を結合したものを一の契約とみなしてロを適用する。
|
(新設)
|
|
(1) 当該複数の契約が同一の商業目的を有するものとして交渉されたこと。
|
(2) 一の契約の中に複数の履行義務が含まれている場合 それぞれの履行義務に係る資産の販売等
|
|
(2) 一の契約において支払を受ける対価の額が、他の契約の価格又は履行により影響を受けること。
|
(注)
|
|
(1) 当事者間で合意された実質的な取引の単位を反映するように複数の契約(異なる相手方と締結した複数の契約又は異なる時点に締結した複数の契約を含む。)を結合した場合のその複数の契約において約束した工事の組合せ
|
(新設)
|
|
(2) 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、イ又はロに掲げる場合に該当する場合(ロにあっては、上記(注)1においてみなして適用される場合に限る。)におけるそれぞれイ又はロに定めるところにより区分した単位
|
(新設)
|
|
3 一の資産の販売等に係る契約につきただし書の(1)の適用を受けた場合には、同様の資産の販売等に係る契約については、継続してその適用を受けたイ又はロに定めるところにより区分した単位ごとに収益の額を計上することに留意する。
|
(新設)
|
|
(2) 資産の賃貸借 資産の賃貸借に係る契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合(当該契約における対価の中に、原資産の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用が含まれる場合を含む。)において、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法により経理しているときは、その方法により区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。
|
(新設)
|
|
(注) 次に掲げる用語の意義については、それぞれ次による。以下この節において同じ。
|
(新設)
|
|
(1) リース 原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。
|
(新設)
|
|
(2) 原資産 リースの対象となる資産で賃貸人によって賃借人に当該資産を使用する権利が移転されているものをいう。
|
(新設)
|
| 2-1-1の2(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の計上の単位) | |
|
2-1-1の2 法人が機械設備等の販売をしたことに伴いその据付工事を行った場合(法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用がある場合及び同条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その据付工事が相当の規模のものであり、かつ、契約その他に基づいて機械設備等の販売に係る対価の額とその据付工事に係る対価の額とを合理的に区分することができるときは、2-1-1ただし書の(1)ロ(収益の計上の単位の通則)に掲げる場合に該当するかどうかにかかわらず、その区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-1の2 法人が機械設備等の販売をしたことに伴いその据付工事を行った場合(法第64条第1項(
|
| 2-1-1の4(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位) | |
|
2-1-1の4 法人が請け負った建設工事等(建設、造船その他これらに類する工事をいう。以下2-1-21の8までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合(法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用がある場合及び同条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、2-1-1(収益の計上の単位の通則)にかかわらず、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-1の4 法人が請け負った建設工事等(建設、造船その他これらに類する工事をいう。以下2-1-21の8までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合(法第64条第1項(
|
| 2-1-1の6(ノウハウの頭金等の収益の計上の単位) | |
|
(注) 1 ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の額がノウハウの開示のために現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、その期間に係る部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。
|
(注)
|
|
2 ノウハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与する場合には、その選択権の提供を当該ノウハウの設定とは別の取引の単位としてその収益の額を計上する。
|
(新設)
|
| 2-1-1の8(資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分) | 2-1-1の8(資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分) |
|
2-1-1の8 法人が資産の販売等又は資産の賃貸借(令和6年9月13日付企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「リース基準」という。)の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下2-1-1の8において同じ。)を行った場合において、次の(1)に掲げる額及び次の(2)に掲げる事実並びにその他のこれらに関連する全ての事実及び状況を総合的に勘案して、当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれていると認められるときは、継続適用を条件として、当該取引に係る利息相当額を当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-1の8 法人が資産の販売等を行った場合において、次の(1)に掲げる額及び次の(2)に掲げる事実並びにその他のこれらに関連する全ての事実及び状況を総合的に勘案して、当該資産の販売等に係る契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれていると認められるときは、継続適用を条件として、当該取引に係る利息相当額を当該資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加)
|
|
(1) 資産の販売等又は資産の賃貸借に係る契約の対価の額と現金販売価格(資産の販売等又は資産の賃貸借と同時にその対価の全額の支払を受ける場合の価格をいう。)との差額
|
(1) 資産の販売等に係る契約の対価の額と現金販売価格(資産の販売等と同時にその対価の全額の支払を受ける場合の価格をいう。)との差額
|
|
(2) 資産の販売等又は資産の賃貸借に係る目的物の引渡し又は役務の提供をしてから相手方が当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る対価の支払を行うまでの予想される期間及び市場金利の影響
|
(2) 資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供をしてから相手方が当該資産の販売等に係る対価の支払を行うまでの予想される期間及び市場金利の影響
|
| 2-1-1の9(割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分) | |
|
2-1-1の9 法人が割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下2-1-1の9において同じ。)を行った場合において、当該割賦販売等に係る販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが区分されているときは、当該利息に相当する金額を当該割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-1の9 法人が割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下2-1-1の9において同じ。)
|
| 2-1-1の10(資産の引渡しの時の価額等の通則) | |
|
(注) 1 なお書の場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、令第18条の2第1項(収益の額)の規定の適用を受ける場合を除き、その差額に相当する金額につきその確定した日の属する事業年度の収益の額を減額し、又は増額する。
|
(注)
|
|
2 引渡し時の価額等が、当該取引に関して支払を受ける対価の額を超える場合において、その超える部分が、寄附金又は交際費等その他のその法人の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの、剰余金の配当等及びその法人の資産の増加又は負債の減少を伴い生ずるもの(以下2-1-1の16までにおいて「損金不算入費用等」という。)に該当しない場合には、その超える部分の金額を益金の額及び損金の額に算入する必要はないことに留意する。
|
(新設)
|
| 2-1-1の11(変動対価) | |
|
(注) 1 引渡し等事業年度終了の日後に生じた事情により令第18条の2第3項(収益の額)に規定する収益基礎額が変動した場合において、資産の販売等に係る収益の額につき同条第1項に規定する当初益金算入額に同項に規定する修正の経理(同条第2項においてみなされる場合を含む。以下2-1-1の11において「修正の経理」という。)により増加した収益の額を加算し、又は当該当初益金算入額からその修正の経理により減少した収益の額を控除した金額が当該資産の販売等に係る法第22条の2第4項に規定する価額又は対価の額に相当しないときは、令第18条の2第3項の規定の適用によりその変動することが確定した事業年度の収益の額を減額し、又は増額することとなることに留意する。
|
(注)
|
|
2 引渡し等事業年度における資産の販売等に係る収益の額につき、その引渡し等事業年度の収益の額として経理していない場合において、その後の事業年度の確定した決算において行う受入れの経理(その後の事業年度の確定申告書における益金算入に関する申告の記載を含む。)は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って行う修正の経理には該当しないことに留意する。
|
(新設)
|
| 2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期) | |
|
2-1-21の2 役務の提供(法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用があるもの及び同条第2項の規定の適用を受けるものを除くものとし、収益認識基準の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下2-1-21の3までにおいて同じ。)のうちその履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの(以下2-1-30までにおいて「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」という。)については、その履行に着手した日から引渡し等の日(物の引渡しを要する取引にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日をいい、物の引渡しを要しない取引にあってはその約した役務の全部を完了した日をいう。以下2-1-21の7までにおいて同じ。)までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、その履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-21の2 役務の提供(法第64条第1項(
|
| 2-1-21の5(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の額の算定の通則) | |
|
(注) 1 本文の取扱いは、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる場合に限り適用する。
|
1 本文の取扱いは、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる場合に限り適用する。
|
| 2-1-21の6(履行義務の充足に係る進捗度) | |
|
(注) 1 2-1-21の4(1)(注)の日常的又は反復的なサービスの場合には、例えば、契約期間の全体のうち、当該事業年度終了の日までに既に経過した期間の占める割合は、履行義務の進捗の度合を示すものとして合理的と認められるものに該当する。
|
1 2-1-21の4(1)(注)の日常的又は反復的なサービスの場合には、例えば、契約期間の全体のうち、当該事業年度終了の日までに既に経過した期間の占める割合は、履行義務の進捗の度合を示すものとして合理的と認められるものに該当する。
|
| 2-1-21の7(請負に係る収益の帰属の時期) | |
|
2-1-21の7 請負(法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用があるもの及び同条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-21の7において同じ。)については、別に定めるものを除き、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)にかかわらず、その引渡し等の日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。ただし、当該請負が2-1-21の4(1)から(3)まで(履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの)のいずれかを満たす場合において、その請負に係る履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度において2-1-21の5(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の額の算定の通則)に準じて算定される額を益金の額に算入しているときは、これを認める。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-21の7 請負(法第64条第1項(
|
|
(注) 1 例えば、委任事務又は準委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約している場合についても、同様とする。
|
1 例えば、委任事務又は準委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約している場合についても同様とする。
|
|
2 2-1-1の4(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)の取扱いを適用する場合には、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金の額をその事業年度の益金の額に算入する。
|
2 2-1-1の4の取扱いを適用する場合には、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金の額をその事業年度の益金の額に算入する。
|
| 2-1-21の12(短期売買商品等の譲渡に係る損益の計上時期の特例) | |
|
(注) 1 短期売買商品等の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品等を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、令第118条の6第1項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定の適用についても同様とする。
|
(注)
|
|
2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。
|
(新設)
|
| 2-1-22(有価証券の譲渡による損益の計上時期) | |
|
2-1-22 有価証券の譲渡による法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下2-1-23の3までにおいて「譲渡損益の額」という。)の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立した日に行うこととなるのであるから、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日に譲渡損益の額を計上する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「七」、平27年課法2-8「三」、令3年課法2-21「四」、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-22 有価証券の譲渡による法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下2-1-23の3までにおいて「譲渡損益の額」という。)の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立した日に行うこととなるのであるから、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日に譲渡損益の額を計上する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「七」、平27年課法2-8「三」、令3年課法2-21「四」により改正)
|
|
(2) 相対取引により有価証券を売却している場合 金融商品取引法第37条の4(契約締結時等の情報の提供)に規定する事項に係る情報として提供される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日
|
(2) 相対取引により有価証券を売却している場合 金融商品取引法第37条の4(契約締結時等の書面の交付)に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日
|
| 2-1-23(有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例) | |
|
(注) 1 有価証券の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、同条第1項の規定の適用についても同様とする。
|
(注)
|
|
2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。
|
(新設)
|
| 2-1-23の4(売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引) | |
|
(注) 1 同時の契約がない場合であっても、これらの契約があらかじめ予定されたものであり、かつ、売却価額と購入価額が同一となるよう売買価額が設定されているとき又はこれらの価額が売却の決済日と購入の決済日との間に係る金利調整のみを行った価額となるよう設定されているときは、同時の契約があるものとして取り扱う。
|
(注)
|
|
2 本文の適用を受ける取引に伴い支出する委託手数料その他の費用は、当該有価証券の取得価額に含めない。
|
(新設)
|
|
3 購入の直後に売却が行われた場合の当該購入についても同様に取り扱う。
|
(新設)
|
| 2-1-24(貸付金利子等の帰属の時期) | |
|
2-1-24 貸付金、預金、貯金若しくは有価証券(以下2-1-24において「貸付金等」という。)から生ずる利子の額又は法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この節において「リース取引」という。)について2-1-1の8(資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)により当該リース取引に係る販売収益の額に含めないこととされた利息相当部分(以下2-1-24において「利息相当部分」という。)の金額は、その利子又は利息相当部分の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入する。ただし、主として金融及び保険業を営む法人以外の法人が、その有する貸付金等(当該法人が金融及び保険業を兼業する場合には、当該金融及び保険業に係るものを除く。)から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき、継続してその支払期日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、昭61年直法2-12「一」、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-5「二」、平30年課法2-8「二」、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-24 貸付金、預金、貯金又は有価証券(以下2-1-24において「貸付金等」という。)から生ずる利子の額は、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入する。ただし、主として金融及び保険業を営む法人以外の法人が、その有する貸付金等(当該法人が金融及び保険業を兼業する場合には、当該金融及び保険業に係るものを除く。)から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき、継続してその支払期日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、昭61年直法2-12「一」、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-5「二」、平30年課法2-8「二」により改正)
|
|
(注) 1 例えば借入金とその運用資産としての貸付金、預金、貯金又は有価証券(法第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(以下「受益者等課税信託」という。)の信託財産に属するこれらの資産を含む。)がひも付きの見合関係にある場合のように、その借入金に係る支払利子の額と運用資産から生ずる利子の額を対応させて計上すべき場合には、その運用資産から生ずる利子の額については、ただし書の適用はないものとする。
|
(注)
|
|
2 資産の販売等又は2-1-1の8に定める資産の賃貸借(以下2-1-24において「資産の賃貸借」という。)に伴い発生する売上債権(受取手形を含む。)又はその他の金銭債権について、その現在価値と当該債権に含まれる金利要素とを区分経理している場合の当該金利要素に相当する部分の金額は、2-1-1の8又は2-1-1の9の取扱いを適用する場合を除き、当該債権の発生の基となる資産の販売等又は資産の賃貸借に係る売上の額等に含まれることに留意する。
|
(新設)
|
| 2-1-25(相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例) | |
|
(注) 1 この取扱いにより益金の額に算入しなかった利子の額については、その後これにつき実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
|
(注)
|
|
2 法人の有する債券又は債券の発行者に上記(1)から(4)までと同様の事実が生じた場合にも、当該債券に係る利子につき同様に取り扱う。
|
(新設)
|
| 2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期) | |
|
2-1-29 資産の賃貸借(平成11年1月22日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引(以下この章において「金融商品」という。)に係る取引、リース取引並びに2-3-62(暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額)の対象となる取引に該当するものを除くものとし、知的財産のライセンスの供与に係る取引にあっては、その収益の額を賃貸人の会計リース期間にわたり定額で計上する場合における当該取引に該当するもの(リース取引に該当するものを除く。)に限る。以下2-1-29において同じ。)は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)の事業年度の益金の額に算入する。ただし、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)について、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日において収益計上を行っている場合には、その支払を受けるべき日は、その資産の賃貸借に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「二」、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-29 資産の賃貸借(
|
|
(注) 1 当該賃貸借契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまで当該使用料等の額を益金の額に算入することを見合わせることができるものとする。
|
(注)
|
|
2 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には(注)1の取扱いによらないのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。
|
(新設)
|
|
3 収入する金額が期間のみに応じて定まっている資産の賃貸借に係る収益の額の算定に要する2-1-21の6(履行義務の充足に係る進捗度)の進捗度の見積りに使用されるのに適切な指標は、通常は経過期間となるため、その収益は毎事業年度定額で益金の額に算入されることになる。
|
(新設)
|
|
4 本文の賃貸人の会計リース期間とは、その賃貸人が選択した次のいずれかの期間をいう。
|
(新設)
|
|
(1) 賃借人のリース期間(解約不能期間(リースに係る契約に基づく賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないこととされている期間をいう。以下この節において同じ。)に7-6の2-10の2(注)(1)及び(2)(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)の期間を加えた期間をいう。以下この節において同じ。)と同様の方法により決定した期間
|
(新設)
|
|
(2) 賃借人が原資産を使用する権利を有する解約不能期間にリースが置かれている状況からみて賃借人が再リースする意思が明らかな場合の再リースに係る賃貸借期間を加えた期間
|
(新設)
|
| 2-1-30(知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期) | |
|
2-1-30 知的財産のライセンスの供与(2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)又は2-1-30の4(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)の取扱いの適用があるものを除く。)に係る収益の額については、次に掲げる知的財産のライセンスの性質に応じ、それぞれ次に定める取引に該当するものとして、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)の取扱いを適用する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-30 知的財産のライセンスの供与に係る収益の額については、次に掲げる知的財産のライセンスの性質に応じ、それぞれ次に定める取引に該当するものとして、2-1-21の2及び2-1-21の3の取扱いを適用する。(平30年課法2-8「二」により追加)
|
| 2-1-30の3(ノウハウの頭金等の帰属の時期) | |
|
(注) 1 2-1-1の6(注)1の取扱いを適用する場合には、その一時金又は頭金の支払を受けるべき金額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
|
(注)
|
|
2 2-1-1の6(注)2の取扱いを適用する場合には、ノウハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与するために支払を受けるいわゆるオプション料の額については、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
|
(新設)
|
| 2-1-30の4(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期) | |
|
2-1-30の4 知的財産のライセンスの供与(2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)の取扱いの適用があるものを除く。)に対して受け取る売上高又は使用量に基づく使用料が知的財産のライセンスのみに関連している場合又は当該使用料において知的財産のライセンスが主な項目である場合には、2-1-1の11(変動対価)の取扱いは適用せず、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)にかかわらず、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度において当該使用料についての収益の額を益金の額に算入する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
|
2-1-30の4 知的財産のライセンスの供与に対して受け取る売上高又は使用量に基づく使用料が知的財産のライセンスのみに関連している場合又は当該使用料において知的財産のライセンスが主な項目である場合には、2-1-1の11の取扱いは適用せず、2-1-21の2及び2-1-21の3にかかわらず、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度において当該使用料についての収益の額を益金の額に算入する。(平30年課法2-8「二」により追加)
|
| 2-3-4の2 | |
|
2-3-4の2 法人が、法第24条第1項(第4号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を受ける場合において、そのみなされる金額が令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額(以下この節において「対象配当等の額」という。)に該当することにより同項(令第119条の4第1項後段(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定(以下この節において「子会社株式簿価減額特例」という。)の適用を受けるときは、そのみなされる金額の基因となった法第61条の2第18項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する払戻し等に係る令第119条の9第1項(資本の払戻しの場合の株式の譲渡原価の額)に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額は、令第119条の3第10項の規定によりそのみなされる金額に係る基準時(同条第12項第3号に規定する基準時をいう。以下この節において同じ。)の直前における帳簿価額から同条第10項に規定する益金の額に算入されない金額(以下この節において「益金不算入相当額」という。)を減算した金額となる。(令2年課法2-17「三」により追加、令4年課法2-14「九」により改正)
|
2-3-4の2 法人が、法第24条第1項(第4号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を受ける場合において、そのみなされる金額が令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額(以下この節において「対象配当等の額」という。)に該当することにより同項(令第119条の4第1項後段(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定(以下この節において「子会社株式簿価減額特例」という。)の適用を受けるときは、そのみなされる金額の基因となった法第61条の2第18項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する払戻し等に係る令第119条の9第1項(資本の払戻しの場合の株式の譲渡原価の額)に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額は、令第119条の3第10項の規定によりそのみなされる金額に係る基準時(同条第12項第3号に規定する基準時をいう。以下この節において同じ。)の直前における帳簿価額から同条第10項に規定する益金の額に算入されない金額(以下この節において「益金不算入相当額」という。)を減算した金額となる。(令2年課法2-17「三」、令4年課法2-14「九」により追加)
|
| 2-3-4の3(対象配当等の額が自己株式の取得によるものである場合の譲渡原価の計算) | |
|
2-3-4の3 法人が、法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を受ける場合において、そのみなされる金額が対象配当等の額に該当することにより子会社株式簿価減額特例の適用を受けるときは、当該対象配当等の額の基因となった株式又は出資の譲渡に係る法第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の「その有価証券の譲渡に係る原価の額(……)」は、令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定によりそのみなされる金額に係る基準時の直前における帳簿価額から益金不算入相当額を減算した金額をその有する株式等の数で除して計算した金額にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額による。(令2年課法2-17「三」により追加、令4年課法2-14「九」により改正)
|
2-3-4の3 法人が、法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を受ける場合において、そのみなされる金額が対象配当等の額に該当することにより子会社株式簿価減額特例の適用を受けるときは、当該対象配当等の額の基因となった株式又は出資の譲渡に係る法第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の「その有価証券の譲渡に係る原価の額(……)」は、令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定によりそのみなされる金額に係る基準時の直前における帳簿価額から益金不算入相当額を減算した金額をその有する株式等の数で除して計算した金額にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額による。(令2年課法2-17「三」、令4年課法2-14「九」により追加)
|
| 2-4-1(工事の請負の範囲) | 2-4-1(賦払の方法) |
|
2-4-1 法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する工事(以下この節において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」、令7年課法2-7「四」により改正)
|
2-4-1
|
| 2-4-2(契約の意義) | 2-4-2(売買があったものとされたリース取引) |
|
2-4-2 法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されているかどうかを問わないことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、令7年課法2-7「四」により改正)
|
2-4-2
|
| 2-4-3(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位) | 2-4-3(延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲) |
|
2-4-3 請け負った工事が法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、複数の契約書により工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、当該契約に至った事情等からみてそれらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、当該工事に係る契約全体を一の契約として長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」、令7年課法2-7「四」により改正)
|
2-4-3 令第124条第1項
|
|
(注) 2-1-1ただし書の(1)イ(収益の計上の単位の通則)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合には、当該単位により判定を行うことに留意する。
|
(注) この取扱いにより延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、その額が確定する都度その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
|
| 2-4-4(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い) | 2-4-4 |
|
2-4-4 工事の請負に係る一の契約においてその目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、当該工事が法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該一の契約ごとに判定することに留意する。
ただし、その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、個々に独立した契約が一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、当該個々に独立した契約ごとに長期大規模工事の判定を行うことができる。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」、令7年課法2-7「四」により改正) |
2-4-4 削除(昭48年直法2-81「2」、「5」、「6」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」
|
|
(注) 2-1-1ただし書の(1)ロ(収益の計上の単位の通則)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合(当該区分した単位ごとに対価の額が区分されている場合に限る。)には、当該単位により判定を行うことに留意する。
|
(新設)
|
| 2-4-5(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い) | 2-4-5(延払基準の計算単位) |
|
2-4-5 長期大規模工事に該当する工事について、請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、その着工事業年度後の事業年度において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、その適用しないこととした事業年度前の各事業年度において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を既往に遡って修正することはしないのであるから留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」、平23年課法2-17「七」、令4年課法2-14「五」、令7年課法2-7「四」により改正)
|
2-4-5 令第124条第1項(延払基準の方法)の規定による延払基準の方法による収益の額及び費用の額の計算は
|
| 2-4-6(長期大規模工事の着手の日等の判定) | 2-4-6(時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額) |
|
2-4-6 令第129条第7項(工事の請負)(同条第10項の規定により準用される場合を含む。)に規定する「その請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」を開始した日がいつであるかについては、当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じその「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、令7年課法2-7「四」により改正)
|
2-4-6 法人がリース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産につきその取得の時における価額を超える価額を取得価額としているときは、その超える部分の金額については取得価額に含めないものとし、その超える部分の金額に相当する値引きをしてリース譲渡を行ったものとして取り扱う。(
|
| 2-4-7(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い) | 2-4-7(支払期日前に受領した手形) |
|
2-4-7 令第129条第2項(工事の請負)に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、令7年課法2-7「四」により改正)
|
2-4-7
|
| 2-4-8(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用) | 2-4-8(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理) |
|
2-4-8 2-1-21の6(注)2(履行義務の充足に係る進捗度)は、令第129条第3項(工事の請負)に規定する「進行割合」の算定について準用する。(平30年課法2-8「五」により追加、令7年課法2-7「四」により改正)
|
2-4-8 法人がリース譲渡を行った後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除してリース期間の中途において当該リース譲渡をした資産を取り戻した場合には、原則としてその資産を取り戻した日の属する事業年度において、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から当該合計額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額をもって資産に計上するものとするが、法人がまだ支払の行われていないリース料の額の合計額又はその資産を取り戻した時における処分見込価額をもって資産に計上したときは、その計算を認めるものとする。(
|
| 2-4-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用) | 2-4-9(契約の変更があった場合の取扱い) |
|
2-4-9 法人が、当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、その請負に係る収益の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)のうち当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額(以下「工事損失引当金相当額」という。)を、当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、そのことをもって、法第63条第2項(工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない。
この場合において、当該工事損失引当金相当額は、同項の規定により当該事業年度において損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る費用の額には含まれないことに留意する。(平20年課法2-5「九」により追加、平30年課法2-12「二」、令7年課法2-7「四」により改正) |
2-4-9 法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり、賦払金の支払期日又は各支払期日ごとの賦払金の額が異動した場合には、その変更後の支払期日及び各支払期日ごとの賦払金の額に基づいて同項の規定による延払基準の計算を行う。ただし、その変更前に既に支払期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。(昭55年直法2-8「八」により追加、平
|
| 2-4-10(外貨建工事に係る契約の時における為替相場) | 2-4-10(対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整) |
|
2-4-10 令第129条第1項(工事の請負)に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、その外貨建工事(請負の対価の額の支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事をいう。以下2-4-12までにおいて同じ。)の請負の対価の額を13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)の本文及び(注)1から3までに定める為替相場(当該外貨建工事の契約の日を同通達に定める取引日とした場合の為替相場をいう。)により円換算した金額とする。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平12年課法2-19「四」、令7年課法2-7「四」により改正)
|
2-4-10 法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し、値引き等があったため当該リース譲渡に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、その異動を生じた日の属する事業年度(以下2-4-10において「異動事業年度」という。)
同条第2項の規定の適用についても同様とする。( |
|
(注) 契約の日までに当該外貨建工事の請負の対価の額の全部又は一部について先物外国為替契約等(法第61条の8第2項(外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等をいう。)により円換算額を確定させている場合であっても、令第129条第1項に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、本通達の本文により円換算した金額とすることに留意する。
|
(新設)
|
| 2-4-11(外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い) | 2-4-11(通算制度の開始等に伴う繰延長期割賦損益額の判定) |
|
2-4-11 外貨建工事について、契約後、値増しや追加工事等又は値引きや工事の削減等があったことによりその請負の対価の額が増額又は減額された場合における令第129条第1項(工事の請負)の規定の適用については、当該外貨建工事に係る当該増額後又は減額後の請負の対価の額を、当該外貨建工事に係る契約時の外国為替の売買相場(当該外貨建工事につき2-4-10(外貨建工事に係る契約の時における為替相場)による円換算に用いた外国為替の売買相場をいう。)により円換算した金額とすることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、令7年課法2-7「四」により改正)
|
2-4-11 令第127条第1項(通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の
|
| 2-4-12(外貨建工事の工事進行基準の計算) | 2-4-12(工事の請負の範囲) |
|
2-4-12 外貨建工事における令第129条第3項(工事の請負)の規定による計算は、例えば、当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法など、法人が当該外貨建工事につき継続して適用する合理的な方法によるものとする。
また、当該計算の基礎となる金額について円換算を行う場合には、13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)、13の2-1-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)、13の2-1-4(先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等)及び13の2-1-5(前渡金等の振替え)によることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、平23年課法2-17「七」、令7年課法2-7「四」により改正) |
2-4-12 法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する工事(以下この款において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平
|
|
(注) 同項に規定する「工事に係る進行割合」の計算については、工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合によることができるのであるから留意する。
|
(新設)
|
| 7-1-9(電気通信施設利用権の範囲) | |
|
7-1-9 令第13条第8号ナ(減価償却資産の範囲)に規定する電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭48年直法2-81「18」、昭49年直法2-71「5」、昭58年直法2-11「五」、昭60年直法2-11「一」、平2年直法2-6「二」、平8年課法2-7「一」、平11年課法2-9「八」、平14年課法2-1「十五」、平16年課法2-14「五」、平23年課法2-17「十二」、平28年課法2-11「三」、令2年課法2-17「五」、令6年課法2-14「四」、令7年課法2-7「五」により改正)
|
7-1-9 令第13条第8号ネ(減価償却資産の範囲)に規定する電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭48年直法2-81「18」、昭49年直法2-71「5」、昭58年直法2-11「五」、昭60年直法2-11「一」、平2年直法2-6「二」、平8年課法2-7「一」、平11年課法2-9「八」、平14年課法2-1「十五」、平16年課法2-14「五」、平23年課法2-17「十二」、平28年課法2-11「三」、令2年課法2-17「五」、令6年課法2-14「四」により改正)
|
| 7-5-3(減価償却資産の償却費の損金経理額に含まれるもの) | |
|
7-5-3 法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース資産に係る法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する「その償却費として損金経理をした金額」には、内国法人が当該リース資産についてその確定した決算において当該リース資産に係る使用権資産(賃借人が原資産(2-1-1ただし書の(2)(注)(2)(収益の計上の単位の通則)に定める原資産をいう。)をリース期間(7-6の2-10の2(注)(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)に定める賃借人の会計リース期間をいう。)にわたり使用する権利を表す資産として財務諸表に記載されるものをいう。)の減価償却費として経理した金額が含まれることに留意する。(令7年課法2-7「六」により追加)
|
(新設)
|
| 7-6の2-1(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義) | |
|
7-6の2-1 令第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する「これらに準ずるもの」として同号に規定する所有権移転外リース取引(以下この節において「所有権移転外リース取引」という。)に該当しないものとは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-1 令第48条の2第5項第5号(所有権移転外リース取引)に規定する「これらに準ずるもの」として同号に規定する所有権移転外リース取引(以下この節において「所有権移転外リース取引」という。)に該当しないものとは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
|
(1) リース期間(法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この節において「リース取引」という。)に係る契約において定められたリース資産(同条第1項に規定するリース資産をいう。以下この節において同じ。)の賃貸借期間をいう。以下この節において同じ。)の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース契約(リース取引に係る契約をいう。以下この節において同じ。)において定められているリース取引(リース契約書上そのことが明示されていないリース取引であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)
|
(1) リース期間(法第64条の2第3項(リース取引の範囲)に規定するリース取引(以下この節において「リース取引」という。)に係る契約において定められたリース資産(同条第1項に規定するリース資産をいう。以下この節において同じ。)の賃貸借期間をいう。以下この節において同じ。)の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース契約(リース取引に係る契約をいう。以下この節において同じ。)において定められているリース取引(リース契約書上そのことが明示されていないリース取引であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)
|
| 7-6の2-2(著しく有利な価額で買い取るものであることにより権利行使が確実と見込まれるものに該当するものの例示) | 7-6の2-2(著しく有利な価額) |
|
7-6の2-2 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引のうち、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この節において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額を下回る場合には、当該5%相当額)以上の金額とされているものであっても、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものについては、令第48条の2第5項第5号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであること……により当該権利が行使されることが確実であると見込まれるもの」に該当する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-2 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引について、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この節において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額を下回る場合には、当該5%相当額)以上の金額とされている場合は、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものでない限り、当該対価の額は令第48条の2第5項第5号ロ(所有権移転外リース取引)に規定する「著しく有利な価額」に該当しないものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
| 7-6の2-3(専属使用のリース資産) | |
|
7-6の2-3 次に掲げるリース取引は、令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-3 次に掲げるリース取引は、令第48条の2第5項第5号ハ(所有権移転外リース取引)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
| 7-6の2-4(専用機械装置等に該当しないもの) | |
|
7-6の2-4 次に掲げる機械装置等を対象とするリース取引は、7-6の2-3(2)(専属使用のリース資産)に掲げるリース取引には該当しないものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-4 次に掲げる機械装置等を対象とするリース取引は、7-6の2-3
|
| 7-6の2-5(形式基準による専用機械装置等の判定) | |
|
7-6の2-5 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-5 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第48条の2第5項第5号ハ(所有権移転外リース取引)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
| 7-6の2-6(識別困難なリース資産) | |
|
7-6の2-6 令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「当該目的資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-6 令第48条の2第5項第5号ハ(所有権移転外リース取引)に規定する「当該目的資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
| 7-6の2-7(相当短いものの意義) | |
|
7-6の2-7 令第48条の2第5項第5号ニ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については、100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を下回る期間であるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-7 令第48条の2第5項第5号ニ(所有権移転外リース取引)に規定する「相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については、100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を下回る期間であるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
|
(注) 1 一のリース取引において耐用年数の異なる数種の資産を取引の対象としている場合(当該数種の資産について、同一のリース期間を設定している場合に限る。)において、それぞれの資産につき耐用年数を加重平均した年数(賃借人における取得価額をそれぞれの資産ごとに区分した上で、その金額ウェイトを計算の基礎として算定した年数をいう。)により判定を行っているときは、これを認めるものとする。
|
(注)
|
|
2 再リースをすることが明らかな場合には、リース期間に再リースの期間を含めて判定する。
|
(新設)
|
| 7-6の2-8(税負担を著しく軽減することになると認められないもの) | |
|
7-6の2-8 賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなリース取引については、令第48条の2第5項第5号ニ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-8 賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなリース取引については、令第48条の2第5項第5号ニ(所有権移転外リース取引)に規定する「賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
| 7-6の2-9(賃借人におけるリース資産の取得価額) | |
|
7-6の2-9 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則としてそのリース期間中のリース料の額の合計額による。ただし、リース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-9 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則としてそのリース期間中に支払うべきリース料の額の合計額による。ただし、リース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
|
(注) 1 再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、再リースをすることが明らかな場合には、当該再リース料の額は、リース資産の取得価額に含まれる。
|
1 再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、再リースをすることが明らかな場合には、当該再リース料の額は、リース資産の取得価額に含まれる。
|
|
2 リース資産を事業の用に供するために賃借人が支出する付随費用の額は、リース資産の取得価額に含まれる。
|
(新設)
|
|
3 本文ただし書の適用を受ける場合には、当該利息相当額は、リース期間の経過に応じて利息法又は定額法により損金の額に算入する。
|
(新設)
|
| 7-6の2-10(リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等) | |
|
7-6の2-10 賃借人がリース期間終了の時にそのリース取引の目的物であった資産を購入した場合(そのリース取引が令第48条の2第5項第5号イ(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの若しくは同号ロの権利が当該資産を著しく有利な価額で買い取るものである場合における同号ロに掲げるもの又はこれらに準ずるものに該当する場合を除く。)には、その購入の直前における当該資産の取得価額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額とし、当該資産に係るその後の償却限度額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次により計算する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-10 賃借人がリース期間終了の時にそのリース取引の目的物であった資産を購入した場合(そのリース取引が令第48条の2第5項第5号イ
|
| 7-6の2-10の2(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い) | |
|
7-6の2-10の2 賃借人が、賃借人の会計リース期間を用いて経理を行っているリース資産に係る令第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)の規定又はこの節における各通達の適用に当たっては、当該賃借人の会計リース期間を同号の「リース期間」又は当該各通達の「リース期間」とする。(令7年課法2-7「七」により追加)
|
(新設)
|
|
(注) 本文の賃借人の会計リース期間とは、賃借人が原資産(2-1-1ただし書の(2)(注)(2)(収益の計上の単位の通則)に定める原資産をいう。以下この節において同じ。)を使用する権利を有する解約不能期間(2-1-29(注)4(1)(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)に定める解約不能期間をいう。)に次の(1)及び(2)の期間を加えた期間をリース期間としている場合の当該リース期間をいう。
|
(新設)
|
|
(1) 賃借人が行使することが合理的に確実であるリース(2-1-1ただし書の(2)(注)(1)に定めるリースをいう。以下この節において同じ。)の延長オプションの対象期間
|
(新設)
|
|
(2) 賃借人が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間
|
(新設)
|
| 7-6の2-11(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額) | |
|
7-6の2-11 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。
リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても、同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正) |
7-6の2-11 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。
リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加) |
| 7-6の2-12(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等) | |
|
7-6の2-12 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産を取得した場合における当該資産の耐用年数は、次のいずれかの年数によることができる。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-12 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産を取得した場合における当該資産の耐用年数は、次のいずれかの年数によることができる。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
|
(1) 当該資産につき適正に見積もったその取得後の使用可能期間の年数
|
(1) 当該資産につき適正に見積ったその取得後の使用可能期間の年数
|
| 7-6の2-13(賃貸借期間等に含まれる再リース期間) | |
|
7-6の2-13 令第48条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下7-6の2-15において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。
令第48条の2第5項第7号(減価償却資産の償却の方法)に規定する「リース期間」、令第49条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する「改定リース期間」及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第121号)附則第7条第2項(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)に規定する「改定リース期間」についても、同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正) |
7-6の2-13 令第48条第1項第6号(旧国外リース期間定額法)に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下7-6の2-15において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。
令第48条の2第1項第6号(リース期間定額法)に規定する「リース期間」及び令第49条の2第1項(旧リース期間定額法)に規定する「改定リース期間」についても同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加) |
| 7-6の2-14(国外リース資産に係る見積残存価額) | |
|
7-6の2-14 賃貸人が、令第48条第5項第2号(減価償却資産の償却の方法)に規定する見積残存価額について、リース料の算定に当たって国外リース資産(同条第1項第6号に規定する国外リース資産をいう。以下7-6の2-15までにおいて同じ。)の取得価額及びその取引に係る付随費用(国外リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額としている場合は、これを認める。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-14 賃貸人が、令第48条第5項第2号(見積残存価額
|
| 7-6の2-16(減価償却に関する明細書) | |
|
7-6の2-16 令第63条第1項(減価償却に関する明細書の添付)の規定の適用において、同項に規定する「第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額」に該当するものであっても、例えば、リース期間におけるリース料の額が均等でないため、当該事業年度においてリース資産に係る償却費として損金経理をした金額とされた賃借料その他当該リース資産を賃借するために支出した費用の額と当該事業年度のリース資産に係る償却限度額とが異なることとなるものについては、減価償却に関する明細書を用いるなどして償却超過額又は償却不足額の計算をすることに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
|
7-6の2-16 令第63条第1項(減価償却に関する明細書の添付)の規定の適用において、同項に規定する「第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額」に該当するものであっても、例えば、リース期間におけるリース料の額が均等でないため、当該事業年度において償却費として損金経理をした金額とされた賃借料の額と当該事業年度のリース資産に係る償却限度額とが異なることとなるものについては、減価償却に関する明細書を用いるなどして償却超過額又は償却不足額の計算をすることに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加)
|
| 7-6の2-17(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い) | |
|
7-6の2-17 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係るリース資産の取得価額とされるべき金額について法第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)その他の減価償却に関する規定及びこの章の取扱いを適用する。(令7年課法2-7「七」により追加)
|
(新設)
|
|
(1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法
|
(新設)
|
|
(2) 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該法人の営業における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法
|
(新設)
|
| 12の5-1-1(資産の賃貸借の範囲) | 12の5-1-1(解除をすることができないものに準ずるものの意義) |
|
12の5-1-1 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)の「資産の賃貸借」には、民法第601条(賃貸借)の規定により効力を生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
|
12の5-1-1 法第64条の2第3項
|
| 12の5-1-2(解除をすることができないものに準ずるものの意義) | 12の5-1-2(おおむね100分の90の判定等) |
|
12の5-1-2 法第64条の2第3項第1号(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平10年課法2-15「4」により追加、平14年課法2-1「三十二」、平15年課法2-7「四十五」、平19年課法2-17「二十六」、令7年課法2-7「八」により改正)
|
12の5-1-2 令第131条の2第2項に規定する「おおむね100分の90」の判定に当たって、次の点については、次
|
|
(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているもの
|
(1) 資産の賃貸借に係る契約等において、賃借人が
|
|
(2) 資産の賃貸借に係る契約において、当該賃貸借期間中に解約をする場合の条項として次のような条件が付されているもの
|
(2) 資産の賃貸借に係る契約
12 |
|
イ 賃貸借資産(当該賃貸借の目的となる資産をいう。以下この節において同じ。)を更新するための解約で、その解約に伴いより性能の高い機種又はおおむね同一の機種を同一の賃貸人から賃貸を受ける場合は解約金の支払を要しないこと。
|
(新設)
|
|
ロ イ以外の場合には、未経過期間に対応するリース料の額の合計額(賃貸借資産を処分することができたときは、その処分価額の全部又は一部を控除した額)を解約金とすること。
|
(新設)
|
| 12の5-1-3(リース取引の判定) | 12の5-1-3(これらに準ずるものの意義) |
|
12の5-1-3 資産の賃貸借が法第64条の2第3項各号(リース取引に係る所得の金額の計算)に掲げる要件に該当するかどうかを判定する場合において、当該資産の賃貸借が次のいずれかに該当するときは、当該資産の賃貸借は、同項第2号に掲げる要件に該当することに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
|
12の5-1-3 令第131条の2第1項(リース取引の範囲)に規定する「これらに準ずるもの」に該当する土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-
|
|
(1) 賃貸人の会計リース料の現在価値が、原資産の現金購入価額のおおむね90%以上であること。
|
(1) 賃貸借期間の終了後、無償と変わらない名目的な賃料によって更新すること
|
|
(2) 賃貸人の会計リース期間が、原資産の経済的耐用年数のおおむね75%以上であること(原資産の特性、経済的耐用年数の長さ、原資産の中古市場の存在等を考慮した場合に、(1)による判定が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除く。)。
|
(2) 賃貸人
|
|
(注) 1 本文(1)及び(2)の次に掲げる用語の意義は、それぞれ次による。以下この章において同じ。
|
(新設)
|
|
(1) 賃貸人の会計リース料 賃借人が賃貸人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、リース(2-1-1ただし書の(2)(注)(1)(収益の計上の単位の通則)に定めるリースをいう。以下この章において同じ。)において合意された使用料をいう。ただし、残価保証(リース期間(リース契約において定められた賃貸借期間をいう。以下この章において同じ。)終了の時に賃貸借資産の処分価額が当該リースに係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リースに係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うことにつき保証がされている場合における当該保証をいう。以下この章において同じ。)がある場合には、当該残価保証の額を含むものとし、契約におけるリースを構成しない部分に配分する対価及び将来の業績等により変動する使用料が含まれる場合には、これを含まないものとする。
|
(新設)
|
|
(2) 原資産 2-1-1ただし書の(2)(注)(2)に定める原資産をいう。
|
(新設)
|
|
(3) 賃貸人の会計リース期間 2-1-29(注)4(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)に定める賃貸人の会計リース期間をいう。
|
(新設)
|
|
(4) 経済的耐用年数 資産の賃貸借の時における賃貸借資産の性能、規格、陳腐化の状況等を考慮して見積もった経済的使用可能予測期間を用いて計算した年数をいう。
|
(新設)
|
|
2 賃借人が本文の判定を行う場合には、それぞれ次のとおりとする。
|
(新設)
|
|
(1) 本文(1)の「賃貸人の会計リース料」を次のとおり読み替える。
|
(新設)
|
|
賃借人の会計リース料(賃借人が賃借人の会計リース期間(7-6の2-10の2(注)(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)に定める賃借人の会計リース期間をいう。以下この章において同じ。)中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、次のもので構成される使用料をいう。以下この章において同じ。)
|
(新設)
|
|
イ 賃借人の固定リース料(賃借人が賃借人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、賃借人の変動リース料(賃借人が賃借人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払である使用料のうち、リース開始日以後に発生する事象又は状況の変化で時の経過によるもの以外のものにより変動する部分をいう。以下12の5-1-3において同じ。)以外の使用料をいう。)
|
(新設)
|
|
ロ 指数又はレートに応じて決まる賃借人の変動リース料
|
(新設)
|
|
ハ 残価保証に係る賃借人による支払見込額
|
(新設)
|
|
ニ 賃借人が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額
|
(新設)
|
|
ホ リースの解約に対する違約金の賃借人による支払額(賃借人の会計リース期間に賃借人による解約オプションの行使を反映している場合に限る。)
|
(新設)
|
|
(2) 本文(2)の「賃貸人の会計リース期間」を「賃借人の会計リース期間」と読み替える。
|
(新設)
|
| 12の5-1-4(サブリースに係るリース取引の判定) | |
|
12の5-1-4 資産の賃貸借(サブリースに該当するものに限る。)が法第64条の2第3項各号(リース取引に係る所得の金額の計算)に掲げる要件に該当するかどうかを判定する場合において、当該資産の賃貸借が次のいずれかに該当するときは、当該資産の賃貸借は、12の5-1-3(リース取引の判定)にかかわらず、同項第2号に掲げる要件に該当することに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
|
(新設)
|
|
(1) サブリースにおける賃貸人の会計リース料の現在価値が、独立第三者間取引における使用権資産のリース料のおおむね90%以上であること。
|
(新設)
|
|
(2) サブリースにおける賃貸人の会計リース期間が、ヘッドリースにおける残りの賃借人の会計リース期間のおおむね75%以上であること((1)による判定が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除く。)。
|
(新設)
|
|
(注) 1 本文並びに本文(1)及び(2)の次に掲げる用語の意義は、それぞれ次による。以下この章において同じ。
|
(新設)
|
|
(1) サブリース サブリース取引(原資産が賃借人から第三者(以下12の5-1-4において「サブリースの賃借人」という。)にさらにリースされ、当初の賃貸人と賃借人との間のリースが依然として有効である取引をいう。以下同じ。)における当初の賃借人とサブリースの賃借人との間のリースをいう。
|
(新設)
|
|
(2) 独立第三者間取引における使用権資産のリース料 サブリース取引の対象とする原資産に係る使用権資産(7-5-3(減価償却資産の償却費の損金経理額に含まれるもの)に定める使用権資産をいう。)に係るサブリースのリース開始日に現金で全額が支払われるものと仮定した場合のリース料(当該サブリースを実行するために必要な知識を持つ自発的な独立第三者の当事者が行うと仮定した場合のリース料に限る。)をいう。
|
(新設)
|
|
(3) ヘッドリース サブリース取引における、当初の賃貸人と賃借人との間のリースをいう。
|
(新設)
|
|
2 サブリースの賃借人が本文の判定を行う場合には、本文(1)中「賃貸人の会計リース料」とあるのは「賃借人の会計リース料」と、本文(2)中「賃貸人の会計リース期間」とあるのは「賃借人の会計リース期間」と、それぞれ読み替える。
|
(新設)
|
| 12の5-1-5(これらに準ずるものの意義) | |
|
12の5-1-5 令第131条の2第1項(リース取引)に規定する「これらに準ずるもの」に該当する土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-17「二十六」により追加、令7年課法2-7「八」により改正)
|
(新設)
|
|
(1) 賃貸借期間の終了後、無償と変わらない名目的な賃料によって更新することが賃貸借契約において定められている賃貸借(契約書上そのことが明示されていない賃貸借であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)
|
(新設)
|
|
(2) 賃貸人に対してその賃貸借に係る土地の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人の賃借料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっている賃貸借
|
(新設)
|
| 12の5-1-6(おおむね100分の90の判定等) | |
|
12の5-1-6 令第131条の2第2項(リース取引)に規定する「おおむね100分の90」の判定に当たっては、同項の「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」については、それぞれ次のとおり取り扱うことに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
|
(新設)
|
|
(1) 資産の賃貸借に係る契約等において、賃借人が賃貸借資産を購入する権利を有し、当該権利の行使が確実であると認められる場合には、当該権利の行使により購入するときの購入価額を加算する。
|
(新設)
|
|
(注) この場合において、その契約書等に当該購入価額についての定めがないときは、残価(賃貸人におけるリース料の額の算定に当たって賃貸借資産の取得価額及びその取引に係る付随費用(賃貸借資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額をいう。)に相当する金額を購入価額とする。
|
(新設)
|
|
(2) 資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した金額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部を控除した金額に相当する金額を加算する。
|
(新設)
|
|
(3) 賃貸借資産の賃貸人に対して補助金等(国又は地方公共団体等から交付を受ける補助金又は助成金等をいい、その交付に当たり当該賃貸借資産に係るリース料の減額が条件とされているものに限る。)が交付される場合であっても、当該リース料の減額部分に相当する金額は、控除しない。
|
(新設)
|
|
(注) 当該リース料の減額部分に相当する金額は、7-6の2-9(賃借人におけるリース資産の取得価額)の「賃借人におけるリース資産の取得価額」に含まれない。
|
(新設)
|
|
12 の5-1-2(1)(解除をすることができないものに準ずるものの意義)に定める「おおむね全部」の判定並びに12の5-1-3(注)2(リース取引の判定)により読み替えられた場合の同通達(1)に定める「おおむね90%以上」の判定及び12の5-1-4(注)2(サブリースに係るリース取引の判定)により読み替えられた場合の同通達(1)に定める「おおむね90%以上」の判定に当たっても、同様とする。
|
(新設)
|
|
(注) 同項に規定する「賃貸借期間」には、再リースを行う意思が明らかな場合の当該再リースに係る賃貸借期間を含める。
|
(新設)
|
| 12の5-1-7(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い) | |
|
12の5-1-7 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係る資産の賃貸借について法第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)及び令第131条の2(リース取引)の規定並びにこの節及び第12章の5第2節(金銭の貸借とされるリース取引)の取扱いを適用する。(令7年課法2-7「八」により追加)
|
(新設)
|
|
(1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法
|
(新設)
|
|
(2) 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該法人の営業における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法
|
(新設)
|
| 12の5-2-1(金銭の貸借とされるリース取引の判定) | |
|
12の5-2-1 法第64条の2第2項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する「一連の取引」が同項に規定する「実質的に金銭の貸借であると認められるとき」に該当するかどうかは、取引当事者の意図、その資産の内容等から、その資産を担保とする金融取引を行うことを目的とするものであるかどうかにより判定する。したがって、例えば、次に掲げるようなものは、これに該当しないものとする。(平10年課法2-15「4」により追加、平14年課法2-1「三十二」、平15年課法2-7「四十七」、平19年課法2-17「二十八」、令7年課法2-7「九」により改正)
|
12の5-2-1 法第64条の2第2項(
|
|
(1) 譲渡人が資産を購入し、当該資産をリース契約(同条第3項に規定するリース取引に係る契約をいう。以下12の5-2-2において同じ。)により賃借するために譲受人に譲渡する場合において、譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することに次に掲げるような相当な理由があり、かつ、当該資産につき、立替金、仮払金等の仮勘定で経理し、譲渡人の購入価額により譲受人に譲渡するもの
|
(1) 譲渡人が資産を購入し、当該資産をリース契約(法第64条
|
| 12の5-2-2(借入金として取り扱う売買代金の額) | |
|
12の5-2-2 法第64条の2第2項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人のリース期間中のリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下12の5-2-2において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人の各事業年度のリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2-15「4」により追加、平14年課法2-1「三十二」、平15年課法2-7「四十七」、平19年課法2-17「二十八」、平20年課法2-5「二十六」、令4年課法2-14「四十五」、令7年課法2-7「九」により改正)
|
12の5-2-2 法第64条の2第2項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人がリース期間
|
| 12の5-2-3(貸付金として取り扱う売買代金の額) | |
|
12の5-2-3 法第64条の2第2項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱い、譲受人のリース期間中のリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において、譲受人の各事業年度のリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2-15「4」により追加、平14年課法2-1「三十二」、平15年課法2-7「四十七」、平19年課法2-17「二十八」、平20年課法2-5「二十六」、令4年課法2-14「四十五」、令7年課法2-7「九」により改正)
|
12の5-2-3 法第64条の2第2項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱い、譲受人がリース期間中に収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において、譲受人が各事業年度に収受するリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2-15「4」により追加、平14年課法2-1「三十二」、平15年課法2-7「四十七」、平19年課法2-17「二十八」、平20年課法2-5「二十六」、令4年課法2-14「四十五」により改正)
|
| 12の5-3-1(資産の賃貸借の範囲) | |
|
12の5-3-1 法第53条第1項(賃貸借取引に係る費用)の「資産の賃貸借」の範囲については、12の5-1-1(資産の賃貸借の範囲)の取扱いを準用する。(令7年課法2-7「十」により追加)
|
(新設)
|
| 12の5-3-2(無償等賃借期間を含む賃貸借取引に係る支払額の損金算入) | |
|
12の5-3-2 賃借期間のうち賃料の支払がない又は通常に比して少額である期間(以下12の5-3-2において「無償等賃借期間」という。)が定められた契約のうち、次に掲げる場合に該当するなどの課税上弊害があるもの以外のものに基づく法第53条第1項(賃貸借取引に係る費用)に規定する賃貸借取引(以下12の5-3-2において「賃貸借取引」という。)に係る当該契約に基づき支払うこととされている金額についての同項の規定の適用に当たっては、当該金額が当該賃借期間にわたり支払われるべきものとした場合に各事業年度中に支払われるべきこととなる金額(当該事業年度終了の日までに損金経理をした金額に限る。)を当該各事業年度の損金の額に算入するものとする。(令7年課法2-7「十」により追加)
|
(新設)
|
|
(1) 当該無償等賃借期間に関する定めがないとした場合に当該賃貸借取引につき支払うこととなる金額と当該契約に基づき支払うこととされている金額との差額が当該契約に基づき支払うこととされている金額のおおむね2割を超える場合
|
(新設)
|
|
(2) 当該賃借期間の開始の日の属する事業年度終了の日において、当該無償等賃借期間内の日の属する各事業年度のいずれかの事業年度で、当該事業年度における賃借期間のおおむね5割を超える期間が賃料の支払がない又は通常に比して少額であるものとなると見込まれる場合(当該契約に係る無償等賃借期間が4月を超える場合に限る。)
|
(新設)
|
| 12の5-3-3(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い) | |
|
12の5-3-3 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係る資産の賃貸借について法第53条(賃貸借取引に係る費用)の規定及びこの節の取扱いを適用する。(令7年課法2-7「十」により追加)
|
(新設)
|
|
(1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法
|
(新設)
|
|
(2) 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該法人の営業における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法
|
(新設)
|
| 12の7-1-6(償却費として損金経理をした金額の意義) | |
|
12の7-1-6 令第131条の8第6項第2号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)又は7-5-2(申告調整による償却費の損金算入)の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。
7-5-3(減価償却資産の償却費の損金経理額に含まれるもの)の取扱いにおけるその確定した決算において法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース資産に係る同通達に定める使用権資産の減価償却費として経理した金額についても、同様とする。(令4年課法2-14「四十八」により追加、令7年課法2-7「十一」により改正) |
12の7-1-6 令第131条の8第6項第2号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)又は7-5-2(申告調整による償却費の損金算入)の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)
|
| 12の7-2-7(譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等) | |
|
12の7-2-7 令第131条の13第1項(時価評価資産等の範囲)の規定の適用上、次に掲げる金額が1,000万円以上であるかどうかの判定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加、令7年課法2-7「十二」により改正)
|
12の7-2-7 令第131条の13第1項(時価評価資産等の範囲)の規定の適用上、次に掲げる金額が1,000万円以上であるかどうかの判定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)
|
|
(2) 同項第3号に規定する特別勘定の金額 その特別勘定の対象となる譲渡した資産又は取得した株式のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定する。
|
(2) 同項第3号
|
|
同条第2項又は第3項の規定による(1)又は(2)に掲げる金額がそれぞれ1,000万円に満たないかどうかの判定に当たっても、同様とする。
|
|
| 12の7-3-2(最初通算事業年度に離脱した法人の時価評価損益等) | |
|
12の7-3-2 法人が、当該法人に係る法第64条の9第1項(通算承認)に規定する親法人の最初通算事業年度(当該法人が同条第10項第1号の規定の適用を受ける法人である場合には、当該親法人の最初通算事業年度の翌事業年度)において、法第64条の10第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失ったため通算法人でなくなった場合であっても、法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定によりその通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産について益金の額に算入した評価益の額又は損金の額に算入した評価損の額は、当該通算開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令5年課法2-8「七」、令7年課法2-7「十三」により改正)
|
12の7-3-2 法人が、当該法人に係る法第64条の9第1項(通算承認)に規定する親法人の最初通算事業年度(当該法人が同条第10項第1号の規定の適用を受ける法人である場合には、当該親法人の最初通算事業年度の翌事業年度)において、法第64条の10第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失ったため通算法人でなくなった場合であっても、法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定によりその通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産について益金の額に算入した評価益の額又は損金の額に算入した評価損の額は、当該通算開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令5年課法2-8「七」により改正)
|
|
(注) 法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の譲渡利益額若しくは譲渡損失額又は次に掲げる規定により益金の額に算入される特別勘定の金額についても、同様とする。
|
(注) 法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の譲渡利益額若しくは譲渡損失額
|
| 12の7-3-3(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度の開始) | |
|
12の7-3-3 法第64条の9第2項(通算承認)に規定する他の内国法人(法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人に該当するものに限る。)が申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時において、時価評価資産を有しないが令第131条の13第2項(時価評価資産等の範囲)に掲げるもの(同項第1号に掲げるものを除く。)を有する場合には、当該申請特例年度終了の日の属する事業年度終了の時において当該他の内国法人の有する時価評価資産につき法第64条の11第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令7年課法2-7「十三」により改正)
|
12の7-3-3 法第64条の9第2項(通算承認)に規定する他の内国法人(法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人に該当するものに限る。)が申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時において、時価評価資産を有しないが令第131条の13第2項
|
| 12の7-3-13(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度への加入) | |
|
12の7-3-13 法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が法第64条の9第12項(通算承認)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時において、法第64条の12第1項に規定する時価評価資産(以下12の7-3-15までにおいて「時価評価資産」という。)を有しないが令第131条の13第3項(時価評価資産等の範囲)に掲げるもの(同項第1号に掲げるものを除く。)を有する場合には、通算加入直前事業年度終了の時において当該他の内国法人の有する時価評価資産につき法第64条の12第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令7年課法2-7「十三」により改正)
|
12の7-3-13 法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が法第64条の9第12項(通算承認)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時において、法第64条の12第1項に規定する時価評価資産(以下12の7-3-15までにおいて「時価評価資産」という。)を有しないが令第131条の13第3項
|
| 13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算) | |
|
(注) 1 本通達の本文の電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その法人の主たる取引金融機関のものによることとするが、法人が、同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
|
(新設)
|
|
2 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下この章において「為替相場」という。)も使用することができる。
|
(新設)
|
|
(1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値
|
1 本通達の本文の電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値
|
|
(2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値
|
2
|
|
3 円換算に係る当該日(為替相場の算出の基礎とする日をいう。以下この(注)3において同じ。)の為替相場については、次に掲げる場合には、それぞれ次によるものとする。以下この章において同じ。
|
(新設)
|
|
(1) 当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による。
|
3
|
|
(2) 当該日に為替相場が2以上ある場合には、その当該日の最終の相場(当該日が取引日である場合には、取引発生時の相場)による。ただし、取引日の相場については、取引日の最終の相場によっているときもこれを認める。
|
4 本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産を取得し若しくは発生させる場合の当該資産、又は外国通貨による借入金(社債を含む。以下この(
|
|
4 本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産を取得し若しくは発生させる場合の当該資産、又は外国通貨による借入金(社債を含む。以下この(注)4において同じ。)に係る当該外国通貨を直ちに売却して本邦通貨を受け入れる場合の当該借入金については、現にその支出し、又は受け入れた本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
|
(新設)
|
|
5 法第61条の9第1項(外貨建資産等の換算額)に規定する外貨建資産等(以下この章において「外貨建資産等」という。)の取得又は発生に係る取引は、当該取得又は発生の時における支払が本邦通貨により行われている場合であっても、本通達の本文及び(注)2から4までを適用し、当該外貨建資産等の円換算を行う。
|
(新設)
|
|
6 いわゆる外貨建て円払いの取引は、当該取引の円換算額を外貨建取引の円換算の例に準じて見積もるものとする。この場合、その見積額と当該取引に係る債権債務の実際の決済額との間に差額が生じたときは、その差額は、13の2-1-11(製造業者等が負担する為替損失相当額等)により益金の額又は損金の額に算入される部分の金額を除き、当該債権債務の決済をした日(同日前にその決済額が確定する場合には、その確定した日)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
|
(新設)
|
| 13の2-1-4(先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等) | 13の2-1-4 |
|
(注) 1 事業年度終了の時において、この取扱いの適用を受けた外貨建取引に係る外貨建資産等で決済時の円換算額を確定させたものを有する場合には、当該外貨建資産等に係る法第61条の10第1項(為替予約差額の配分)に規定する為替予約差額に相当する金額を同条第1項から第3項までの規定に基づき各事業年度に配分することに留意する。この場合、当該事業年度終了の日における当該為替予約差額に相当する金額の計上は、課税上弊害がない限り、為替差損益の調整勘定として処理することができるものとする。
|
1 事業年度終了の時において、この取扱いの適用を受けた外貨建取引に係る外貨建資産等で決済時の円換算額を確定させたものを有する場合には、当該外貨建資産等に係る法第61条の10第1項(為替予約差額の配分)に規定する為替予約差額に相当する金額を同条第1項から第3項までの規定に基づき各事業年度に配分することに留意する。この場合、当該事業年度終了の日における当該為替予約差額に相当する金額の計上は、課税上弊害がない限り、為替差損益の調整勘定として処理することができるものとする。
|
| 13の2-1-6 | 13の2-1-6 |
|
13の2-1-6 削除(平12年課法2-7「十九」により追加、平14年課法2-1「三十四」、平30年課法2-8「十八」により改正、令7年課法2-7「十四」により削除)
|
13の2-1-6 令第124条(延払基準の方法)の規定による延払基準の方法を適用するリース譲渡(以下13の2-1-7までにおいて「リース譲渡」という。)の対価の一部につき前受金を受け入れている場合において、その対価の全額につき13の2-1-2により円換算を行い、これを基として延払基準を適用しているときは、当該前受金の帳簿価額と当該前受金についての円換算額との差額に相当する金額は、当該リース譲渡に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入し、同条第2項に規定する賦払金割合の算定に含めることに留意する。(平12年課法2-7「十九」により追加、平14年課法2-1「三十四」、平30年課法2-8「十八」により改正)
|
| 13の2-1-7 | 13の2-1-7 |
|
13の2-1-7 削除(平12年課法2-7「十九」により追加、平30年課法2-8「十八」により改正、令7年課法2-7「十四」により削除)
|
13の2-1-7 リース譲渡について債権総額を計上するとともにその未実現利益を繰延計上する経理を行っている法人が、当該リース譲渡に係る外貨建債権(法第61条の9第1項第1号(外貨建資産等の換算額)に規定する外貨建債権をいう。以下この章において同じ。)を当該事業年度終了の時の為替相場により円換算を行った場合において、その円換算による為替差損益を計上しているときは、繰延経理をした当該未実現利益の額を調整するものとする。(平12年課法2-7「十九」により追加、平30年課法2-8「十八」により改正)
|
| 13の2-1-11(製造業者等が負担する為替損失相当額等) | 13の2-1-11 |
|
13の2-1-11 製造業者等が商社等を通じて行った輸出入等の取引に関して生ずる為替差損益の全部又は一部を製造業者等に負担させ又は帰属させる契約を締結している場合における商社等及び製造業者等の取扱いについては、次による。(平12年課法2-7「十九」により追加、平14年課法2-1「三十四」、平22年課法2-1「三十六」、平23年課法2-17「二十八」、令7年課法2-7「十四」により改正)
|
13の2-1-11
|
|
(1) 商社等 外貨建債権債務(外貨建債権(法第 61 条の9第1項第1号(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建債権をいう。以下この章において同じ。)又は外貨建債務をいう。以下この章において同じ。)について同号ロに規定する期末時換算法(以下この章において「期末時換算法」という。)を選定している場合(同号イに規定する発生時換算法(以下この章において「発生時換算法」という。)を選定している外貨建債権債務につき令第122条の3第1項(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)の規定の適用を受けたときを含む。)において、当該契約に係る外貨建債権債務につき当該事業年度終了の時にその決済が行われたものと仮定した場合において製造業者等に負担させ又は帰属させることとなる金額(当該外貨建債権債務に係る換算差額又は法第61条の10第1項から第3項まで(為替予約差額の配分)に規定する各事業年度に配分すべき金額に相当する金額のうち、負担させ又は帰属させることとなる金額に限る。)を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
|
(1) 商社等 外貨建債権
|
| 13の2-2-5(期末時換算法-事業年度終了の時における為替相場) | |
|
(注) 1 当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場は、継続適用を条件として、当該事業年度終了の日を含む1月以内の一定期間におけるそれぞれの平均値によることができる。
|
(注)
|
|
2 当該事業年度終了の日の電信買相場又は電信売相場が異常に高騰し、又は下落しているため、これらの相場又はその仲値によることが適当でないと認められる場合も、(注)1の平均値を使用することができる。
|
1 当該事業年度終了の日の電信
|
| 13の2-2-8(2以上の先物外国為替契約等を締結している場合の契約締結日の特例) | |
|
(注) 1 当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
|
(注)
|
|
2 令第122条の9第3項(為替予約差額の月数按分の特例)の規定に基づく月数による按分は継続適用を前提として認められているものであるが、本文の適用は、同項の規定の適用を受けている場合に限られないことに留意する。
|
1 当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない
|
| 13の2-2-10(為替相場の著しい変動があった場合の外貨建資産等の換算) | |
|
(注) 1 算式中の「当該事業年度終了の日の為替相場」は、13の2-2-5に定めるところによる。
|
(注)
|
|
2 多数の外貨建資産等を有するため、個々の外貨建資産等ごとに算式による割合の計算を行うことが困難である場合には、外国通貨の種類を同じくする外貨建債権、外貨建債務、外貨建有価証券、外貨預金又は外国通貨のそれぞれの合計額を基礎としてその計算を行うことができるものとする。
|
1 算式
|
|
3 外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等につき上記の算式により計算した割合がおおむね15%に相当する割合以上となるものが2以上ある場合には、その一部についてのみ同項の規定による円換算を行うことはできないことに留意する。
|
2
|
|
4 本文の取扱いは、同条第2項に規定する適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等について準用する。この場合、算式中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「当該適格分割等のあった日の前日」とする。
|
3 外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等につ
|
| 13の2-2-12(期限徒過の外貨建債権) | |
|
13の2-2-12 外貨建債権で既にその支払期限を経過し支払が延滞しているものは、令第122条の4第1号(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する短期外貨建債権に該当しないものとして取り扱う。(平12年課法2-7「二十」により追加、令7年課法2-7「十五」により改正)
|
13の2-2-12 外貨建債権で既にその支払期限を経過し支払が延滞しているものは、短期外貨建債権に該当しないものとして取り扱う。(平12年課法2-7「二十」により追加)
|
| 13の2-2-18(外貨建資産等の支払の日等につき繰延べ等があった場合の取扱い) | |
|
(注) 1 当該事業年度が当該外貨建資産等に係る債権債務の支払の日の属する事業年度である場合には、当該為替予約差額の残額から当該事業年度の前事業年度(繰延事業年度以後の事業年度に限る。)までの間に益金の額又は損金の額に算入した金額を控除して得た金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入することに留意する。
|
(注)
|
|
2 月数又は日数は、暦に従って計算し、月数につき1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
|
1 当該事業年度が当該外貨建資産等に係る債権債務の支払の日の属する事業年度である場合には、当該為替予約差額の残額から当該事業年度の前事業年度(繰延事業年度以後の事業年度に限る。)までの間に益金の額又は損金の額に算入した金額を控除して得た金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入することに留意する。
|
|
3 外貨建資産等に係る債権債務の支払の日又は当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の履行の日につき繰延べ等が行われたことに伴い、当該外貨建資産等に係る円換算額が確定しないこととなった場合には、13の2-2-16(先物外国為替契約等の解約等があった場合の取扱い)の取扱いによる。
|
2 月数又は日数は、暦に従って計算し、月数につき1月に満たない端数を生じたときは、
|
| 16-3-9(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算) | |
|
16-3-9 法第69条第4項第1号(国外事業所等に帰せられるべき所得)に掲げる国外源泉所得(以下この節において「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算に当たり、令第141条の3第2項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に基づき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算する場合には、次のことに留意する。(昭58年直法2-3「六」、平2年直法2-1「十三」、平23年課法2-17「三十五」、平24年課法2-17「七」、平26年課法2-9「四」、平27年課法2-26「一」、平30年課法2-28「五」、令7年課法2-7「十六」により改正)
|
16-3-9 法第69条第4項第1号(国外事業所等に帰せられるべき所得)に掲げる国外源泉所得(以下この節において「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算に当たり、令第141条の3第2項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に基づき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算する場合には、次のことに留意する。(昭58年直法2-3「六」、平2年直法2-1「十三」、平23年課法2-17「三十五」、平24年課法2-17「七」、平26年課法2-9「四」、平27年課法2-26「一」、平30年課法2-28「五」により改正)
|
|
(1) 減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、法第22条の2第2項(収益の額)の規定に準じて収益の額を益金算入しようとする場合に行われる収益の計上等については、法人税に関する法令の規定により、内国法人の仮決算又は確定した決算において経理することを要件として適用されることとなる。
(注)内国法人が単に国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この節において同じ。)の帳簿に記帳するだけでは、これらの規定の適用がないことに留意する。 |
(1) 減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、
(注)内国法人が単に国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この節において同じ。)の帳簿に記帳するだけでは、これらの規定の適用がないことに留意する。 |
| 16-3-9の3(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する場合の準用) | |
|
16-3-9の3 内国法人の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するに当たっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる取扱いを準用する。(平26年課法2-9「四」により追加、平27年課法2-26「一」、令7年課法2-7「十六」により改正)
|
16-3-9の3 内国法人の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するに当たっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる取扱いを準用する。(平26年課法2-9「四」により追加、平27年課法2-26「一」により改正)
|
|
(1) 内部取引から生ずる国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する場合 20-5-2(内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)、20-5-4(外国法人における短期保有株式等の判定)、20-5-5(損金の額に算入できない保証料)、20-5-7(損金の額に算入できない償却費等)、20-5-8(販売費及び一般管理費等の損金算入)、20-5-8の3(賃貸借取引に係る費用の損金算入)、20-5-33(繰延ヘッジ処理等における負債の利子の額の計算)及び20-5-34(資本等取引に含まれるその他これらに類する事実)の取扱い
|
(1) 内部取引から生ずる国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する場合 20-5-2(内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)、20-5-4(外国法人における短期保有株式等の判定)、20-5-5(損金の額に算入できない保証料)、20-5-7(損金の額に算入できない償却費等)、20-5-8(販売費及び一般管理費等の損金算入)、20-5-33(繰延ヘッジ処理等における負債の利子の額の計算)及び20-5-34(資本等取引に含まれるその他これらに類する事実)の取扱い
|
| 16-3-12(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦) | |
|
(注) 1 内国法人(金融及び保険業を主として営む法人を除く。)の国外業務に係る収入金額の全部又は大部分が利子、配当等又は使用料であり、かつ、当該事業年度の所得の金額のうちに調整国外所得金額(令第142条第1項(控除限度額の計算)(通算法人にあっては、令第148条第2項第3号(通算法人に係る控除限度額の計算))に規定する調整国外所得金額をいう。)の占める割合が低いなどのため課税上弊害がないと認められる場合には、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額のうち国外業務に関連することが明らかな費用の額のみが共通費用の額であるものとして国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。
|
(注)
|
|
2 内国法人の国外業務に係る収入金額のうちに法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける配当等(以下16-3-13までにおいて「外国子会社配当等」という。)の収入金額がある場合における外国子会社配当等に係る「国外業務に係る売上総利益の額」は、外国子会社配当等の収入金額から当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されない金額を控除した金額によることに留意する。
|
(新設)
|
| 16-3-13(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦) | |
|
(注) 1 (1)の算式の「国外事業所等に係る資産」及び(2)の算式の「国外事業所等に係る貸付金、有価証券等」には、当該事業年度において収益に計上すべき利子、配当等の額がなかった貸付金、有価証券等を含めないことができる。
|
(注)
|
|
2 (1)の算式の「国外事業所等に係る資産」及び(2)の算式の「国外事業所等に係る貸付金、有価証券等」に、外国子会社配当等に係る株式又は出資がある場合には、これらの算式における当該株式又は出資に係る「国外事業所等に係る資産の帳簿価額」及び「有価証券等の当該事業年度中の平均残高」の計算は、当該株式又は出資の帳簿価額から当該帳簿価額に当該事業年度における外国子会社配当等の収入金額のうちに法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により益金の額に算入されない金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額による。
|
(新設)
|
|
3 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額によるものとし、法人が税効果会計を適用している場合において、確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する。
|
(新設)
|
|
4 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。
|
(新設)
|
| 16-3-15(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における引当金の繰入額等) | |
|
(注) 1 内国法人が単に国外事業所等の帳簿に記帳した金額は、仮決算又は確定した決算において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額に該当しないことに留意する。
|
(注)
|
|
2 内国法人が国外事業所等の帳簿において貸倒引当金を記帳していない場合であっても、国外事業所等に帰せられる金銭債権につき仮決算又は確定した決算において貸倒引当金勘定への繰入れを行っているときは、当該金銭債権について、(1)又は(2)の適用があることに留意する。
|
(新設)
|
|
3 内国法人が、全ての国外事業所等につき、国外事業所等貸倒実績率に代えて同項に規定する貸倒実績率により計算を行っている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。
|
(新設)
|
| 16-3-19の3(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦) | |
|
(注) 1 内国法人(金融及び保険業を主として営む法人を除く。)の国外業務に係る収入金額の全部又は大部分が利子、配当等又は使用料であり、かつ、当該事業年度の所得の金額のうちに調整国外所得金額(令第142条第1項(控除限度額の計算)(通算法人にあっては、令第148条第2項第3号(通算法人に係る控除限度額の計算))に規定する調整国外所得金額をいう。)の占める割合が低いなどのため課税上弊害がないと認められる場合には、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額のうち国外業務に関連することが明らかな費用の額のみが共通費用の額であるものとしてその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。
|
(注)
|
|
2 内国法人の国外業務に係る収入金額のうちに法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける配当等(以下16-3-19の4までにおいて「外国子会社配当等」という。)の収入金額がある場合における外国子会社配当等に係る「国外業務に係る売上総利益の額」は、外国子会社配当等の収入金額から当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されない金額を控除した金額によることに留意する。
|
(新設)
|
| 16-3-19の4(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦) | |
|
(注) 1 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」には、当該事業年度において収益に計上すべき利子、配当等の額がなかった貸付金、有価証券等を含めないことができる。
|
(注)
|
|
2 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」に、外国子会社配当等に係る株式又は出資がある場合には、これらの算式における当該株式又は出資に係る「有価証券等の帳簿価額」及び「有価証券等の当該事業年度中の平均残高」の計算は、当該株式又は出資の帳簿価額から当該帳簿価額に当該事業年度における外国子会社配当等の収入金額のうちに法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により益金の額に算入されない金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額による。
|
(新設)
|
|
3 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額によるものとし、法人が税効果会計を適用している場合において、確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する。
|
(新設)
|
|
4 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。
|
(新設)
|
| 16-3-26(外国法人税額に増額等があった場合) | |
|
(注) 1 外国法人税の額の減額があった場合において、当該外国法人税につき、減額された外国法人税の額を超えて控除対象外国法人税額を減額することとなるときは、当該超える部分の控除対象外国法人税額に相当する金額については、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する。
|
(注) 1外国法人税の額の減額があった場合において、当該外国法人税につき、減額された外国法人税の額を超えて控除対象外国法人税額を減額することとなるときは、当該超える部分の控除対象外国法人税額に相当する金額については、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する。
|
|
2 通算法人の法第69条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る本文の取扱いの適用に当たっては、「及び第9項」とあるのは「、第9項及び第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)」と読み替える。
|
(注)
|
| 17-1-5(組織再編成に係る確定申告書の添付書類) | |
|
17-1-5 規則第35条第1項第7号(確定申告書の添付書類)に規定する明細書は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平14年課法2-1「四十一」により追加、平16年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十六」、平19年課法2-17「三十四」、平22年課法2-1「四十三」、平28年課法2-11「十二」、平29年課法2-17「二十四」、平30年課法2-12「七」、令元年課法2-10「十」、令3年課法2-21「十四」、令4年課法2-14「六十二」、令5年課法2-8「十一」、令7年課法2-7「十七」により改正)
|
17-1-5 規則第35条第1項第7号(確定申告書の添付書類)に規定する明細書は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平14年課法2-1「四十一」により追加、平16年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十六」、平19年課法2-17「三十四」、平22年課法2-1「四十三」、平28年課法2-11「十二」、平29年課法2-17「二十四」、平30年課法2-12「七」、令元年課法2-10「十」、令3年課法2-21「十四」、令4年課法2-14「六十二」、令5年課法2-8「十一」により改正)
|
| 20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲) | |
|
20-2-4 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21(恒久的施設に帰せられる資産の意義)の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第13条第8号イからナまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」、令6年課法2-14「十」、令7年課法2-7「十八」により改正)
|
20-2-4 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21(恒久的施設に帰せられる資産の意義)の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第13条第8号イからネまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」、令6年課法2-14「十」により改正)
|
| 20-5-2(内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) | |
|
20-5-2 内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算については、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配、適格株式交換等及び適格株式移転に係る取扱いを除き、次に掲げる取扱いを準用する。(平26年課法2-9「九」により追加、平29年課法2-17「二十七」、平30年課法2-8「二十四」、平30年課法2-28「七」、令7年課法2-7「十九」により改正)
|
20-5-2 内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算については、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配、適格株式交換等及び適格株式移転に係る取扱いを除き、次に掲げる取扱いを準用する。(平26年課法2-9「九」により追加、平29年課法2-17「二十七」、平30年課法2-8「二十四」、平30年課法2-28「七」により改正)
|
|
(注) 第2章第1節(収益等の計上に関する通則)の取扱いを準用するに当たっては、資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に相当する内部取引について収益認識基準の適用対象となるものとする。
|
(注) 第2章第1節(収益等の計上に関する通則)の取扱いを準用するに当たっては、資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に相当する内部取引について
|
|
(8) 第12章の5(リース取引及び賃貸借取引)の取扱い(12 の5-3-2(無償等賃借期間を含む賃貸借取引に係る支払額の損金算入)の取扱いを除く。)
|
(8) 第12章の5(リース取引)の取扱い
|
| 20-5-3(外国法人における損金経理等) | |
|
20-5-3 外国法人が恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、法第22条の2第2項(収益の額)の規定に準じて収益の額を益金算入しようとする場合に行われる収益の計上のように法又は措置法の規定により決算又は確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が恒久的施設帰属所得に係る事業等に関して作成する帳簿及び当該帳簿に基づいて作成する規則第61条の3第1号ハ(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)又は規則第61条の5第1号ヘ(確定申告書の添付書類)に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって当該要件を満たすものとして取り扱う。(平26年課法2-9「九」により追加、平30年課法2-28「七」、令7年課法2-7「十九」により改正)
|
20-5-3 外国法人が恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、
|
| 20-5-8の3(賃貸借取引に係る費用の損金算入) | |
|
20-5-8の3 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、令第184条第1項(第14号ロに係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用に当たっては、20-5-8(販売費及び一般管理費等の損金算入)の例による。(令7年課法2-7「十九」により追加)
|
(新設)
|
| 20-5-10の2(負債の利子の額の配賦) | |
|
(注) 1 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、確定した決算に基づく外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額につき、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額によるものとし、外国法人が税効果会計を適用している場合において、当該貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する。
|
(注)
|
|
2 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。
|
(新設)
|
| 20-5-35(恒久的施設に係る資産等の円換算) | |
|
20-5-35 恒久的施設に係る外貨建ての資産、負債等の円換算等については、13の2-1-1から13の2-1-5まで及び13の2-1-9から13の2-2-18まで(外貨建取引等の換算等)の取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその本店等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則として当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する外国法人が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める。(平26年課法2-9「九」により追加、令7年課法2-7「十九」により改正)
|
20-5-35 恒久的施設に係る外貨建ての資産、負債等の円換算等については、13の2-1-1から13の2-1-7まで及び13の2-1-9から13の2-2-18まで(外貨建取引等の換算等)の取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその本店等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則として当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する外国法人が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める。(平26年課法2-9「九」により追加)
|
| 2-1-1(収益の計上の単位の通則) | |
|
(削除)
|
1 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、次のいずれかに該当する場合には、当該複数の契約を結合したものを一の契約とみなしてただし書の(2)を適用する。
|
|
(削除)
|
(1) 当該複数の契約が同一の商業目的を有するものとして交渉されたこと。
|
|
(削除)
|
(2) 一の契約において支払を受ける対価の額が、他の契約の価格又は履行により影響を受けること。
|
|
(削除)
|
(1) 当事者間で合意された実質的な取引の単位を反映するように複数の契約(異なる相手方と締結した複数の契約又は異なる時点に締結した複数の契約を含む。)を結合した場合のその複数の契約において約束した工事の組合せ
|
|
(削除)
|
(2) 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、ただし書の(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合(ただし書の(2)にあっては、上記(注)1においてみなして適用される場合に限る。)におけるそれぞれただし書の(1)又は(2)に定めるところにより区分した単位
|
|
(削除)
|
3 一の資産の販売等に係る契約につきただし書の適用を受けた場合には、同様の資産の販売等に係る契約については、継続してその適用を受けたただし書の(1)又は(2)に定めるところにより区分した単位ごとに収益の額を計上することに留意する。
|
| 2-1-1の6(ノウハウの頭金等の収益の計上の単位) | |
|
(削除)
|
1 ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の額がノウハウの開示のために現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、その期間に係る部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。
|
|
(削除)
|
2 ノウハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与する場合には、その選択権の提供を当該ノウハウの設定とは別の取引の単位としてその収益の額を計上する。
|
| 2-1-1の10(資産の引渡しの時の価額等の通則) | |
|
(削除)
|
1 なお書の場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、令第18条の2第1項(収益の額)の規定の適用を受ける場合を除き、その差額に相当する金額につきその確定した日の属する事業年度の収益の額を減額し、又は増額する。
|
|
(削除)
|
2 引渡し時の価額等が、当該取引に関して支払を受ける対価の額を超える場合において、その超える部分が、寄附金又は交際費等その他のその法人の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの、剰余金の配当等及びその法人の資産の増加又は負債の減少を伴い生ずるもの(以下2-1-1の16までにおいて「損金不算入費用等」という。)に該当しない場合には、その超える部分の金額を益金の額及び損金の額に算入する必要はないことに留意する。
|
| 2-1-1の11(変動対価) | |
|
(削除)
|
1 引渡し等事業年度終了の日後に生じた事情により令第18条の2第3項(収益の額)に規定する収益基礎額が変動した場合において、資産の販売等に係る収益の額につき同条第1項に規定する当初益金算入額に同項に規定する修正の経理(同条第2項においてみなされる場合を含む。以下2-1-1の11において「修正の経理」という。)により増加した収益の額を加算し、又は当該当初益金算入額からその修正の経理により減少した収益の額を控除した金額が当該資産の販売等に係る法第22条の2第4項に規定する価額又は対価の額に相当しないときは、令第18条の2第3項の規定の適用によりその変動することが確定した事業年度の収益の額を減額し、又は増額することとなることに留意する。
|
|
(削除)
|
2 引渡し等事業年度における資産の販売等に係る収益の額につき、その引渡し等事業年度の収益の額として経理していない場合において、その後の事業年度の確定した決算において行う受入れの経理(その後の事業年度の確定申告書における益金算入に関する申告の記載を含む。)は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って行う修正の経理には該当しないことに留意する。
|
| 2-1-21の5(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の額の算定の通則) | |
|
(削除)
|
(注)
|
| 2-1-21の6(履行義務の充足に係る進捗度) | |
|
(削除)
|
(注)
|
| 2-1-21の7(請負に係る収益の帰属の時期) | |
|
(削除)
|
(注)
|
| 2-1-21の12(短期売買商品等の譲渡に係る損益の計上時期の特例) | |
|
(削除)
|
1 短期売買商品等の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品等を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、令第118条の6第1項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定の適用についても同様とする。
|
|
(削除)
|
2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。
|
| 2-1-23(有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例) | |
|
(削除)
|
1 有価証券の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、同条第1項の規定の適用についても同様とする。
|
|
(削除)
|
2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。
|
| 2-1-23の4(売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引) | |
|
(削除)
|
1 同時の契約がない場合であっても、これらの契約があらかじめ予定されたものであり、かつ、売却価額と購入価額が同一となるよう売買価額が設定されているとき又はこれらの価額が売却の決済日と購入の決済日との間に係る金利調整のみを行った価額となるよう設定されているときは、同時の契約があるものとして取り扱う。
|
|
(削除)
|
2 本文の適用を受ける取引に伴い支出する委託手数料その他の費用は、当該有価証券の取得価額に含めない。
|
|
(削除)
|
3 購入の直後に売却が行われた場合の当該購入についても同様に取り扱う。
|
| 2-1-24(貸付金利子等の帰属の時期) | |
|
(削除)
|
1 例えば借入金とその運用資産としての貸付金、預金、貯金又は有価証券(法第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(以下「受益者等課税信託」という。)の信託財産に属するこれらの資産を含む。)がひも付きの見合関係にある場合のように、その借入金に係る支払利子の額と運用資産から生ずる利子の額を対応させて計上すべき場合には、その運用資産から生ずる利子の額については、ただし書の適用はないものとする。
|
|
(削除)
|
2 資産の販売等に伴い発生する売上債権(受取手形を含む。)又はその他の金銭債権について、その現在価値と当該債権に含まれる金利要素とを区分経理している場合の当該金利要素に相当する部分の金額は、2-1-1の8又は2-1-1の9の取扱いを適用する場合を除き、当該債権の発生の基となる資産の販売等に係る売上の額等に含まれることに留意する。
|
| 2-1-25(相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例) | |
|
(削除)
|
1 この取扱いにより益金の額に算入しなかった利子の額については、その後これにつき実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
|
|
(削除)
|
2 法人の有する債券又は債券の発行者に上記(1)から(4)までと同様の事実が生じた場合にも、当該債券に係る利子につき同様に取り扱う。
|
| 2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期) | |
|
(削除)
|
1 当該賃貸借契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまで当該使用料等の額を益金の額に算入することを見合わせることができるものとする。
|
|
(削除)
|
2 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には(注)1の取扱いによらないのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。
|
|
(削除)
|
3 収入する金額が期間のみに応じて定まっている資産の賃貸借に係る収益の額の算定に要する2-1-21の6の進捗度の見積りに使用されるのに適切な指標は、通常は経過期間となるため、その収益は毎事業年度定額で益金の額に算入されることになる。
|
| 2-1-30の3(ノウハウの頭金等の帰属の時期) | |
|
(削除)
|
1 2-1-1の6(注)1の取扱いを適用する場合には、その一時金又は頭金の支払を受けるべき金額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
|
|
(削除)
|
2 2-1-1の6(注)2の取扱いを適用する場合には、ノウハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与するために支払を受けるいわゆるオプション料の額については、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
|
| 2-4-2(売買があったものとされたリース取引) | |
|
(削除)
|
(注)
|
|
(削除)
|
1 そのリース取引が行われた日の属する事業年度後の事業年度において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度についての当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は、原則として令第124条に規定する延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とする。
|
|
(削除)
|
2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、リース譲渡(法第63条第1項に規定するリース譲渡をいう。以下2-4-10までにおいて同じ。)の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。
|
|
(削除)
|
3 本文及び(注)1の取扱いは、法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡には適用がないことに留意する。
|
| 2-4-9(契約の変更があった場合の取扱い) | |
|
(削除)
|
(注) 同条第2項の規定の適用についても同様とする。
|
| 2-4-13(契約の意義) | |
|
(削除)
|
2-4-13 法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されているどうかを問わないことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)
|
| 2-4-14(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位) | |
|
(削除)
|
2-4-14 請け負った工事が法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、複数の契約書により工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、当該契約に至った事情等からみてそれらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、当該工事に係る契約全体を一の契約として長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」により改正)
|
|
(削除)
|
(注) 2-1-1(1)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合には、当該単位により判定を行うことに留意する。
|
| 2-4-15(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い) | |
|
(削除)
|
2-4-15 工事の請負に係る一の契約においてその目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、当該工事が法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該一の契約ごとに判定することに留意する。
ただし、その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、個々に独立した契約が一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、当該個々に独立した契約ごとに長期大規模工事の判定を行うことができる。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」により改正) |
|
(削除)
|
(注) 2-1-1(2)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合(当該区分した単位ごとに対価の額が区分されている場合に限る。)には、当該単位により判定を行うことに留意する。
|
| 2-4-16(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い) | |
|
(削除)
|
2-4-16 長期大規模工事に該当する工事について、請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、その着工事業年度後の事業年度において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、その適用しないこととした事業年度前の各事業年度において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を既往に遡って修正することはしないのであるから留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」、平23年課法2-17「七」、令4年課法2-14「五」により改正)
|
| 2-4-17(長期大規模工事の着手の日等の判定) | |
|
(削除)
|
2-4-17 令第129条第7項(長期大規模工事に着手したかどうかの判定)(同条第10項(長期大規模工事以外の工事に着手したかどうかの判定)の規定により準用される場合を含む。)に規定する「その請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」を開始した日がいつであるかについては、当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じその「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」により改正)
|
| 2-4-18(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い) | |
|
(削除)
|
2-4-18 令第129条第2項(支払条件に係る長期大規模工事の判定)に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」により改正)
|
| 2-4-18の2(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用) | |
|
(削除)
|
2-4-18の2 2-1-21の6(注)2は、令第129条第3項(工事進行基準の方法)に規定する「進行割合」の算定について準用する。(平30年課法2-8「五」により追加)
|
| 2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用) | |
|
(削除)
|
2-4-19 法人が、当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、その請負に係る収益の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)のうち当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額(以下「工事損失引当金相当額」という。)を、当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、そのことをもって、法第64条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない。
この場合において、当該工事損失引当金相当額は、同項の規定により当該事業年度において損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る費用の額には含まれないことに留意する。(平20年課法2-5「九」により追加、平30年課法2-12「二」により改正) |
| 2-4-20(外貨建工事に係る契約の時における為替相場) | |
|
(削除)
|
2-4-20 令第129第1項(長期大規模工事の判定)に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、その外貨建工事(請負の対価の額の支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事をいう。以下2-4-22までにおいて同じ。)の請負の対価の額を13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)の本文及び(注)1から3までに定める為替相場(当該外貨建工事の契約の日を同通達に定める取引日とした場合の為替相場をいう。)により円換算した金額とする。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平12年課法2-19「四」により改正)
|
|
(削除)
|
(注) 契約の日までに当該外貨建工事の請負の対価の額の全部又は一部について先物外国為替契約等(法第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等をいう。)により円換算額を確定させている場合であっても、令第129条第1項に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、本通達の本文により円換算した金額とすることに留意する。
|
| 2-4-21(外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い) | |
|
(削除)
|
2-4-21 外貨建工事について、契約後、値増しや追加工事等又は値引きや工事の削減等があったことによりその請負の対価の額が増額又は減額された場合における令第129条第1項(長期大規模工事の判定)の規定の適用については、当該外貨建工事に係る当該増額後又は減額後の請負の対価の額を、当該外貨建工事に係る契約時の外国為替の売買相場(当該外貨建工事につき2-4-20による円換算に用いた外国為替の売買相場をいう。)により円換算した金額とすることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」により改正)
|
| 2-4-22(外貨建工事の工事進行基準の計算) | |
|
(削除)
|
2-4-22 外貨建工事における令第129条第3項(工事進行基準の方法)の規定による計算は、例えば、当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法など、法人が当該外貨建工事につき継続して適用する合理的な方法によるものとする。
また、当該計算の基礎となる金額について円換算を行う場合には、13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)、13の2-1-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)、13の2-1-4(先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等)及び13の2-1-5(前渡金等の振替え)によることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、平23年課法2-17「七」により改正) |
|
(削除)
|
(注) 同項に規定する「工事に係る進行割合」の計算については、工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合によることができるのであるから留意する。
|
| 7-6の2-7(相当短いものの意義) | |
|
(削除)
|
1 一のリース取引において耐用年数の異なる数種の資産を取引の対象としている場合(当該数種の資産について、同一のリース期間を設定している場合に限る。)において、それぞれの資産につき耐用年数を加重平均した年数(賃借人における取得価額をそれぞれの資産ごとに区分した上で、その金額ウェイトを計算の基礎として算定した年数をいう。)により判定を行っているときは、これを認めるものとする。
|
|
(削除)
|
2 再リースをすることが明らかな場合には、リース期間に再リースの期間を含めて判定する。
|
| 7-6の2-9(賃借人におけるリース資産の取得価額) | |
|
(削除)
|
(注)
|
|
(削除)
|
2 リース資産を事業の用に供するために賃借人が支出する付随費用の額は、リース資産の取得価額に含まれる。
|
|
(削除)
|
3 本文ただし書の適用を受ける場合には、当該利息相当額はリース期間の経過に応じて利息法又は定額法により損金の額に算入する。
|
| 7-6の2-11(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額) | |
|
(削除)
|
(注) 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
|
| 12の5-1-1(解除をすることができないものに準ずるものの意義) | |
|
(削除)
|
(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているもの
|
|
(削除)
|
(2) 資産の賃貸借に係る契約において、当該賃貸借期間中に解約をする場合の条項として次のような条件が付されているもの
|
|
(削除)
|
イ 賃貸借資産(当該賃貸借の目的となる資産をいう。以下12の5-1-2までにおいて同じ。)を更新するための解約で、その解約に伴いより性能の高い機種又はおおむね同一の機種を同一の賃貸人から賃貸を受ける場合は解約金の支払を要しないこと。
|
|
(削除)
|
ロ イ以外の場合には、未経過期間に対応するリース料の額の合計額(賃貸借資産を処分することができたときは、その処分価額の全部又は一部を控除した額)を解約金とすること。
|
| 12の5-1-2(おおむね100分の90の判定等) | |
|
(削除)
|
(注) 残価とは、賃貸人におけるリース料の額の算定に当たって賃貸借資産の取得価額及びその取引に係る付随費用(賃貸借資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額をいう。以下この章において同じ。
|
|
(削除)
|
(3) 賃貸借資産の取得者である賃貸人に対し交付された補助金等(当該補助金等の交付に当たり賃借料の減額が条件とされているものに限る。)がある場合には、同項の「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」は、当該賃貸借に係る契約等に基づく賃借料の金額の合計額に当該減額相当額を加算した金額による。
|
|
(削除)
|
(注) 「減額相当額」は、賃借人における賃貸借資産の取得価額には算入しない。
|
| 12の7-2-7(譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等) | |
|
(削除)
|
(注) (2)の判定を行う場合において、法人が、リース譲渡につき2-4-5(延払基準の計算単位)の取扱いにより合理的な区分ごとに一括して延払基準を適用しているときは、その契約の属する区分の差益率を基として当該契約に係る繰延長期割賦損益額を計算している限り、これを認める。
|
| 13の2-1-2 (外貨建取引及び発生時換算法の円換算) | |
|
(削除)
|
(注)
|
|
(削除)
|
(1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値
|
|
(削除)
|
(2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値
|
|
(削除)
|
(1) 当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による。
|
|
(削除)
|
(2) 当該日に為替相場が2以上ある場合には、その当該日の最終の相場(当該日が取引日である場合には、取引発生時の相場)による。ただし、取引日の相場については、取引日の最終の相場によっているときもこれを認める。
|
|
(削除)
|
5 法第61条の9第1項(外貨建資産等の換算額)に規定する外貨建資産等(以下この章において「外貨建資産等」という。)の取得又は発生に係る取引は、当該取得又は発生の時における支払が本邦通貨により行われている場合であっても、本通達の本文及び(注)2から4までを適用し、当該外貨建資産等の円換算を行う。
|
|
(削除)
|
6 いわゆる外貨建て円払いの取引は、当該取引の円換算額を外貨建取引の円換算の例に準じて見積もるものとする。この場合、その見積額と当該取引に係る債権債務の実際の決済額との間に差額が生じたときは、その差額は、13の2-1-11(製造業者等が負担する為替損失相当額等)により益金の額又は損金の額に算入される部分の金額を除き、当該債権債務の決済をした日(同日前にその決済額が確定する場合には、その確定した日)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
|
| 13の2-1-4 (先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等) | |
|
(削除)
|
(注)
|
| 13の2-1-7(リース譲渡に係る債権等につき為替差損益を計上した場合の未実現利益繰延額の修正) | |
|
(削除)
|
(注) リース譲渡に係る短期外貨建債権(令第122条の4第1号(短期外貨建債権債務)に規定する短期外貨建債権をいう。以下この章において同じ。)につき計上した為替差損益に対応する未実現利益の額を法人が継続して調整しないこととしているときは、本文にかかわらずこれを認める。
|
| 13の2-2-5(期末時換算法-事業年度終了の時における為替相場) | |
|
(削除)
|
2 当該事業年度終了の日の電信買相場又は電信売相場が異常に高騰し、又は下落しているため、これらの相場又はその仲値によることが適当でないと認められる場合も、(注)1の平均値を使用することができる。
|
| 13の2-2-8(2以上の先物外国為替契約等を締結している場合の契約締結日の特例) | |
|
(削除)
|
2 令第122条の9第3項(為替予約差額の月数按分の特例)の規定に基づく月数による按分は継続適用を前提として認められているものであるが、本文の適用は、同項の規定の適用を受けている場合に限られないことに留意する。
|
| 13の2-2-10(為替相場の著しい変動があった場合の外貨建資産等の換算) | |
|
(削除)
|
4 本文の取扱いは、同条第2項に規定する適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等について準用する。この場合、算式中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「当該適格分割等のあった日の前日」とする。
|
| 13の2-2-18(外貨建資産等の支払の日等につき繰延べ等があった場合の取扱い) | |
|
(削除)
|
3 外貨建資産等に係る債権債務の支払の日又は当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の履行の日につき繰延べ等が行われたことに伴い、当該外貨建資産等に係る円換算額が確定しないこととなった場合には、13の2-2-16(先物外国為替契約等の解約等があった場合の取扱い)の取扱いによる。
|
| 16-3-12(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦) | |
|
(削除)
|
1 内国法人(金融及び保険業を主として営む法人を除く。)の国外業務に係る収入金額の全部又は大部分が利子、配当等又は使用料であり、かつ、当該事業年度の所得の金額のうちに調整国外所得金額(令第142条第1項(控除限度額の計算)(通算法人にあっては、令第148条第2項第3号(通算法人に係る控除限度額の計算))に規定する調整国外所得金額をいう。)の占める割合が低いなどのため課税上弊害がないと認められる場合には、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額のうち国外業務に関連することが明らかな費用の額のみが共通費用の額であるものとして国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。
|
|
(削除)
|
2 内国法人の国外業務に係る収入金額のうちに法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける配当等(以下16-3-13までにおいて「外国子会社配当等」という。)の収入金額がある場合における外国子会社配当等に係る「国外業務に係る売上総利益の額」は、外国子会社配当等の収入金額から当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されない金額を控除した金額によることに留意する。
|
| 16-3-13(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦) | |
|
(削除)
|
1 (1)の算式の「国外事業所等に係る資産」及び(2)の算式の「国外事業所等に係る貸付金、有価証券等」には、当該事業年度において収益に計上すべき利子、配当等の額がなかった貸付金、有価証券等を含めないことができる。
|
|
(削除)
|
2 (1)の算式の「国外事業所等に係る資産」及び(2)の算式の「国外事業所等に係る貸付金、有価証券等」に、外国子会社配当等に係る株式又は出資がある場合には、これらの算式における当該株式又は出資に係る「国外事業所等に係る資産の帳簿価額」及び「有価証券等の当該事業年度中の平均残高」の計算は、当該株式又は出資の帳簿価額から当該帳簿価額に当該事業年度における外国子会社配当等の収入金額のうちに法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により益金の額に算入されない金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額による。
|
|
(削除)
|
3 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額によるものとし、法人が税効果会計を適用している場合において、確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する。
|
|
(削除)
|
4 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。
|
| 16-3-15(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における引当金の繰入額等) | |
|
(削除)
|
1 内国法人が単に国外事業所等の帳簿に記帳した金額は、仮決算又は確定した決算において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額に該当しないことに留意する。
|
|
(削除)
|
2 内国法人が国外事業所等の帳簿において貸倒引当金を記帳していない場合であっても、国外事業所等に帰せられる金銭債権につき仮決算又は確定した決算において貸倒引当金勘定への繰入れを行っているときは、当該金銭債権について、(1)又は(2)の適用があることに留意する。
|
|
(削除)
|
3 内国法人が、全ての国外事業所等につき、国外事業所等貸倒実績率に代えて同項に規定する貸倒実績率により計算を行っている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。
|
| 16-3-19の3(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦) | |
|
(削除)
|
1 内国法人(金融及び保険業を主として営む法人を除く。)の国外業務に係る収入金額の全部又は大部分が利子、配当等又は使用料であり、かつ、当該事業年度の所得の金額のうちに調整国外所得金額(令第142条第1項(控除限度額の計算)(通算法人にあっては、令第148条第2項第3号(通算法人に係る控除限度額の計算))に規定する調整国外所得金額をいう。)の占める割合が低いなどのため課税上弊害がないと認められる場合には、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額のうち国外業務に関連することが明らかな費用の額のみが共通費用の額であるものとしてその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。
|
|
(削除)
|
2 内国法人の国外業務に係る収入金額のうちに法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける配当等(以下16-3-19の4までにおいて「外国子会社配当等」という。)の収入金額がある場合における外国子会社配当等に係る「国外業務に係る売上総利益の額」は、外国子会社配当等の収入金額から当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されない金額を控除した金額によることに留意する。
|
| 16-3-19の4(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦) | |
|
(削除)
|
1 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」には、当該事業年度において収益に計上すべき利子、配当等の額がなかった貸付金、有価証券等を含めないことができる。
|
|
(削除)
|
2 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」に、外国子会社配当等に係る株式又は出資がある場合には、これらの算式における当該株式又は出資に係る「有価証券等の帳簿価額」及び「有価証券等の当該事業年度中の平均残高」の計算は、当該株式又は出資の帳簿価額から当該帳簿価額に当該事業年度における外国子会社配当等の収入金額のうちに法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により益金の額に算入されない金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額による。
|
|
(削除)
|
3 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額によるものとし、法人が税効果会計を適用している場合において、確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する。
|
|
(削除)
|
4 (2)の算式の「自己資本の額」は、確定した決算に基づく貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。
|
| 20-5-10の2(負債の利子の額の配賦) | |
|
(削除)
|
1 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、確定した決算に基づく外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額につき、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額によるものとし、外国法人が税効果会計を適用している場合において、当該貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する。
|
|
(削除)
|
2 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。
|
アプリの改修
- 横画面でも使用できるようになりました。iPad などの大きい画面ではメニューと条項表示画面の二分割構成になります。ただし、現バージョンでは横画面と縦画面で状態が分別管理されているため、基本的には法令一覧画面で使用する向きを確定させてからご利用ください。中期的にはデザインの不整合も直したうえで、シームレスに変更できるようにする予定です。

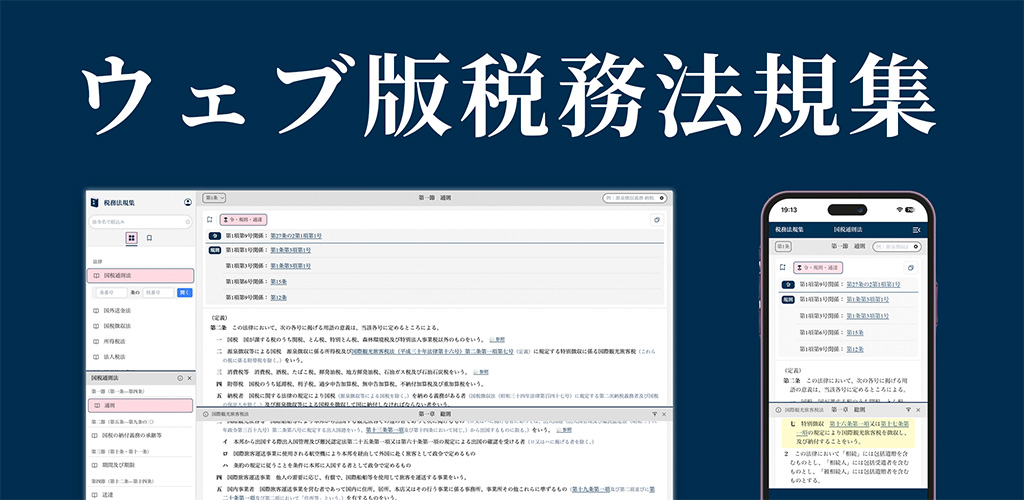



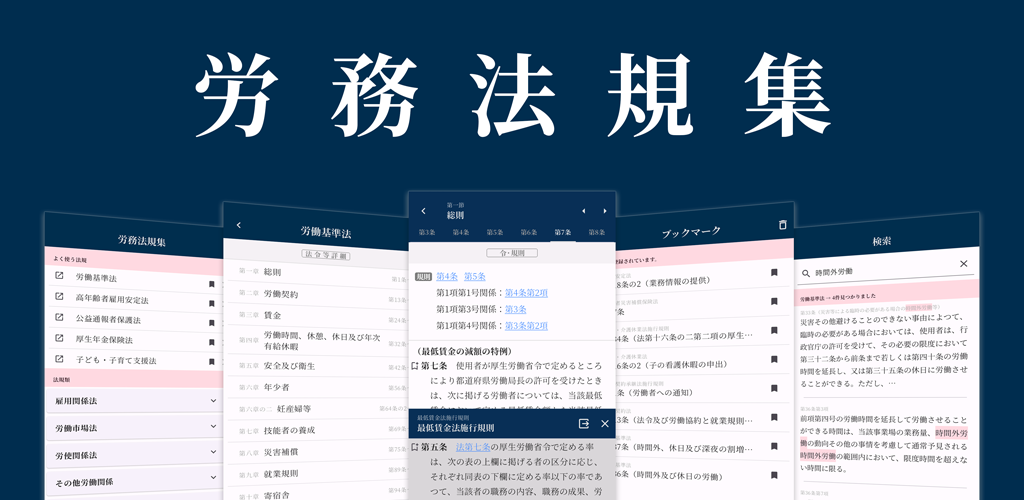
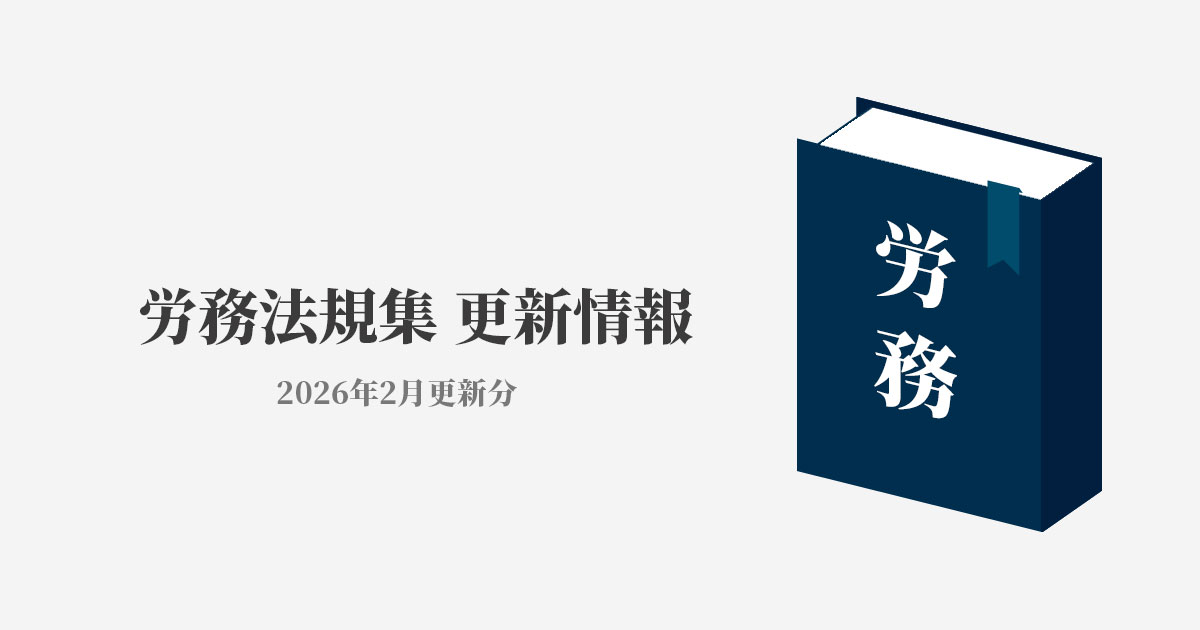

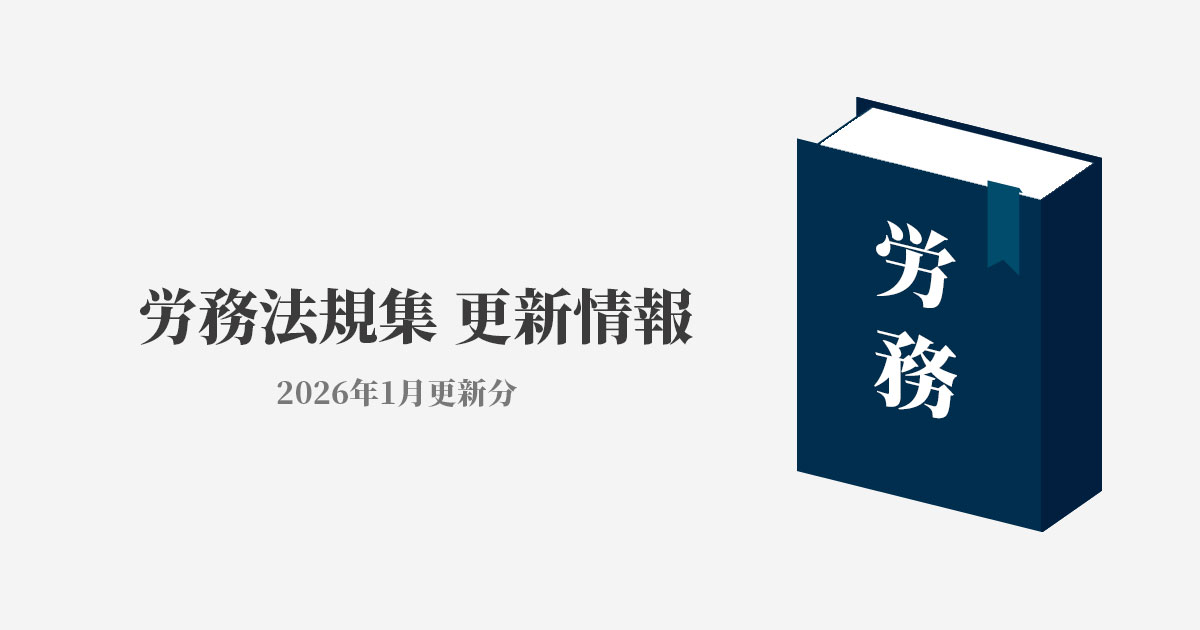
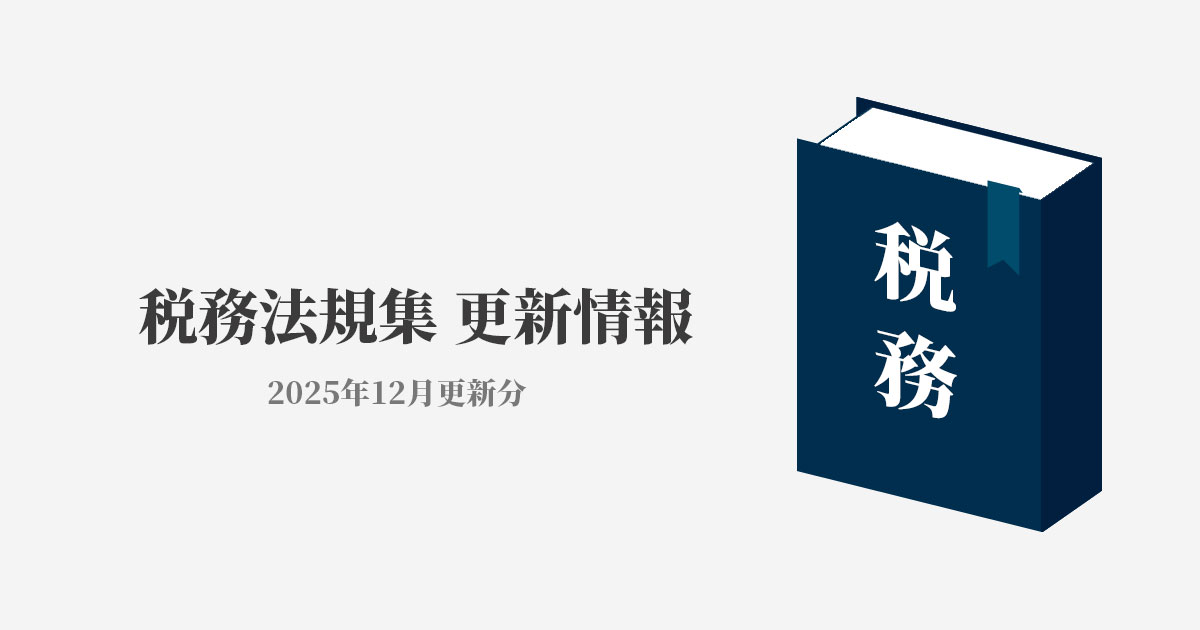
この記事をシェアする
Twitter
Google+
Facebook
はてなブックマーク
Reddit
LinkedIn
StumbleUpon
Email